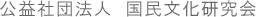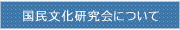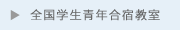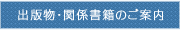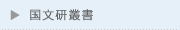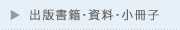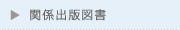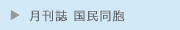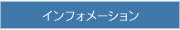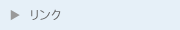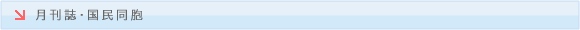
第679号
| 執筆者 | 題名 |
| 合宿教室(東日本)運営委員長 池松伸典 |
人としての「まことの道」を見つめ直さう! - 変化激しき時代の中で、大事なものを忘れてはゐないか - |
| 中村 正和 | 勝海舟の武士道 - 「智の人」にして「仁の人」 - |
| 『日本への回帰』第53集(はしがき)から 米朝対峙で、自立意志の如何が問はれてゐる ― 憲法改正は「国の誇り」を取り戻す第一歩― |
|
| 大岡 弘 | 女性天皇に課せられた不文律(中) - 女性天皇の事例と『女帝考』 - |
| 小柳陽太郎著作集 展転社 2,700円 『日本のいのちに至る道』 |
「働き方改革」が議論されるやうになって企業では生産性の向上やスキルアップといふ掛け声の下、労働時間短縮などで快適な職場環境を実現しようとしてゐる。また家庭においては、IОT(Internet of Thingsモノのインターネット、様々なモノをインターネットにつなぐこと)やAI(人工知能)などの言葉で示されるやうに、かつては夢の如くに思ひ描かれてゐた「未来の快適な生活」が現実のものとなりつつある。
以前と比べると随分と便利になったのは人類の叡智の結集の賜物であらうと感心するのであるが、その一方で変化がどんどん早くなってゐる中で、それに追ひつくのが忙しく、「何か大事なものを置き忘れてゐる」やうにも思はれるのである。
長年、私が携はってゐる建築の分野でも以前からすると相当効率的になって、工事の管理も多岐に渡って可能になってはゐるが、相変らずミスも生じてゐるから大幅に楽になったわけではない。逆に情報が多くなった分だけ作成する書類がふえて、その整理のために現場を見る時間が少なくなり、現場での問題点をいち早く見つける眼力や、突発的に起きる事柄に対して臨機応変に対処していかうとする意志力が衰へてきてゐるやうにも感じられる。
今年は明治維新150周年で、当時の人々の生き方が注目されてゐるが、明治の人達の逞(たくま)しさや精神性の強さなどに私も引きつけられてゐる。彼らの遺した言葉を通して、その思ひを辿っていくことは、この「忘れてきてしまった何か大事なもの」に気づく大きな手立てになるのではないかと思はれる。
明治天皇は生涯93,000首を超える驚異的な数の和歌をお詠みになったが、中でも近代西洋と国運をかけて戦った日露戦争の最中の明治37年には6,500首近くもの御歌をお詠みになってゐる。その中の一つに次の御歌がある。
思ふことありのまにまにつらぬる がいとまなき世のなぐさめにして
「まにまに」は「随に」と書き、「したがふ、ままに」といふ意味で、思ってゐることをそのままに、ありのままに言葉を並べていくと歌が出来てくる、そのことが気の安まることのない戦中にあって、自分の心の慰めとなってゐるとの御意と拝される。一口に「ありのままの思ひを見つめる」といっても容易なことではない。国家の危機に直面して、その重責重圧を担はれながら「いとまなき」中の僅かな「いとま」に短歌をお詠みになってゐる明治天皇のお姿を拝察すると、現実からお目をそらされることなく、ありのままを御覧になる中で人のまことをしみじみとお感じになってをられるお姿が浮んでくる。
また、明治維新で活躍した志士達に大きな影響を与へた吉田松陰が野山獄で行った孟子の講義録「講孟劄記」の序には、次の言葉がある。
〝道は則ち高し、美し、約なり、近なり。人徒(ただ)其の高く且つ美しきを見て以て及ぶ可からずと為し、而も其の約にして且つ近、甚だ親しむ可きことを知らざるなり〟
「人が踏み行ふ道は高貴で美しく、同時に分りやすく身近なものであるはずであるが、私達はその高貴さと美しさとを見てとても自分には叶はないと思って、それが身近なもので大いに親しむべきものであることを知らうとしない」と松陰は言ってゐるのだ。続けて、裕福になると欲望におぼれ、貧乏になれば苦しみもがく。どちらも人としての「まことの道」を見失ってしまひそこから抜け出られなくなってゐると説いてゐる。
世の中の変化が激しく、便利になればなるほど人としての生きる根本のあり方が見え難(にく)くなるものである。そして世の中がどんなに変って便利に効率的にならうとも、次々に問題が生起して課題が消えてしまふことはない。さうした根本の事実を見つめ直すことが、いよいよ大事になってゐるのではないかと思はれる。
今年の第63回全国学生青年合宿教室は東日本と西日本の二箇所で開催される(5頁参照)。全国各地からの参加を得て、悠久の昔から培はれてきた「日本の姿」を偲び、国内外の問題にも触れながら、自らの生き方をともに考へていきたいものとと思ってゐる。率直な思ひを互ひにに吐露したいものである。
(若築建設(株)東京支店)
はじめに
ことしは慶応4年改め明治元年(1868)から満百50年である。
幕臣で剣・禅・書を能(よ)くして、「江戸無血開城」にも尽力した山岡鐵舟(のち明治天皇の侍従)は「幕末維新の大業は、武士道で出来た」と言ってゐるが、ここで改めて「武士道」に関して述べてみたい。
黒船が近海に出没し、列強の脅威に晒された時、心ある「もののふ」は、その侮りを座視することなどできなかった。わが国の武士道がそれを許さなかった。廉恥と勇気を重んじる武士たちは、国を守らんとして次々に敢然と立ち上がって行った。
その憂国の志士たちの中にあって、幕末の三舟(勝海舟、山岡鉄舟、高橋泥舟)は、官軍と幕府軍との決定的対立を避け、わが国を悲惨な内乱から救はうとした。官軍も幕府軍も、また数多(あまた)の民も、ともに皇国の一民である。三舟は互ひに連携し、皇国の民を一つに和合させ、維新へと導いたのである。
武士道とは、至誠、忠孝、廉恥である。自分の国を愛し、祖国と人々のために己を尽すこと。己を捨て、いま自分にできることを一所懸命に行ふこと。死を覚悟して本気で生きること。武士道とはかうした日本人の魂のことである。
わが国は、本来、尚武の国である。
そして、わが国の武士道は、これからの世界と若者を導く高貴なる道標(みちしるべ)となるものである。この「尚武のこころ」を教へなければ日本人の魂は育たない、私はさう思ってゐる。
海舟の「武士道」
勝海舟の書画の中で、際立つのが小品「錨(いかり)画賛」である(『筆禅』第38号所載)。錨が強く立体的に描かれ、その錨の真ん中に奇抜な印を押し、その賛は紙に食ひ込む深い線で「かけとめむ ちびきのいかりつなをなみ ただよふ船の行へしらずも」と書かれてゐる。「千引きの錨」とは千人でやっと引けるほどの重さの錨といふ意味で、漂ふ日本丸をこの錨でなんとか繋ぎとめたいといふ海舟の憂国の情を詠んだものと思ふ。
勝海舟は、万延元年(1860)、咸臨丸に乗り込み、日本人の操舵で初めて太平洋を横断し、「日本海軍」を創設した英雄である。また、直心影流(じきしんかげりゅう)の免許皆伝を受けた剣の達人であった海舟は、知力と胆力を兼ね備へて、アジアといふ広い視野の中で日本を捉へた政治家でもあった。海舟は、後年、日・清・韓の三国合従の策を主唱して、明治政府の要人の中でただ一人、日清戦争に反対した。この勝海舟の武士道とは如何なるものであったのか。
海舟は、貧しい下級武士の家に生れた。父勝小吉は将軍家の直臣ではあったが小普請組の無役で禄高は40俵、海舟は極貧の中で育った。しかし、父小吉は憂国の人平山子龍(し りょう)の「必死三昧」「純一無雑」の剣理に傾倒心酔し、その国防の志を学んだ人であった。そもそも小吉の従弟が直心影流の達人「幕末の剣聖」と呼ばれた男谷(を だに)信友(のぶ とも)であり、海舟を男谷信友の一番弟子であった島田虎之助に預けたのも父小吉であった。海舟は、この島田虎之助から剣を学び、禅を勧められたのである。また海舟の義侠心は父譲りのものであった。
海舟は「智の人」といはれる。しかし、私は、「公」の高処(たか み)に立ち、不惜身命のこころざしをもって国を救はうとしたところに海舟の武士道を見る。この「公」の志とは、戦後の日本人が「忘れさせられた」(江藤淳)「尚武のこころ」である。
山鹿素行は「真武真文を学び、身を修め心を正しうして、国を治め天下を平らかにすること、是れ士道なり」(『武教小学』)と述べてゐる。海舟は、幕末に「治国平天下」の武士としての使命を背負ひ、わが国を列強の侵略から守るために、幕臣でありながら敗軍の将となって徳川幕府の幕を引いた偉丈夫であった。
海舟と象山、小楠、南洲
海舟を「公」の志へと覚醒させたのは、佐久間象山と横井小楠である。佐久間象山は洋学を研究し、攘夷の先を行く「開国論」を唱へた人で、その門下には吉田松陰、橋本左内、河合継之助、そして勝海舟、坂本龍馬らがゐる。海舟の号も象山の書いた「海舟書屋(しよ おく)」といふ額に由来し、後年、海舟の妹お順は象山に嫁いでゐる。
横井小楠は、象山の公武合体論をさらに一歩進め、徳川幕府を「公議公論の政体」へと変革し、開国によって富国する道を説いた。海舟は「おれは、今までに天下で恐ろしいものを二人見た。それは、横井小楠と西郷南洲とだ」(『氷川清話』)と述懐してゐる。幕府の政事総裁職(大老格)の補佐役としての己れの立場を根底から覆(くつがへ)すこの小楠の思想に、海舟は戦慄したのである。
しかし、海舟は怯まなかった。海舟は西郷南洲(隆盛)とともに、この小楠の公議政体論を押し進め、本当に幕府を潰してしまふ。そして、その思想は、さらに海舟が育てた坂本龍馬の「船中八策」に受け継がれ、小楠の弟子由利公正が起草した明治天皇の「五箇条の御誓文」へと結実して行くのである。
海舟は、幕府の幕引をした30年前の昔を振り返り、次のやうに語ってゐる。「おれも国家問題のためには、群議を斥けてしまって、徳川300年の幕府をすら棒に振って顧みなかった。当時には、一身の死生はもとより、徳川氏の存亡も眼中にはおかなかった」(『氷川清話』)。
西郷南洲の受けた衝撃
海舟が西郷南洲に初めて会ったのは、元治元年(1864)の第一次長州征伐の折のことである。軍艦奉行として幕府の中核にあった海舟は、幕府にはもう日本を救ふ力のないことを正直に吐露し、列藩同盟による新しい政体を結成する他に道はないと説いたといふ。南洲は、その時に海舟から受けた衝撃を国元の大久保利通に手紙で知らせてゐる。
「勝氏へ初めて面会仕り候処、実に驚き入り候人物にて、最初は打ち叩くつもりにて差し越し候処、頓と頭を下げ申し候。どれだけか知略のあるやら知れぬ塩梅に見受け申し候。先ず英雄肌合の人にて、佐久間より事の出来候は、一層も越え候はん」(『西郷隆盛と薩摩士道』)。
西郷南洲に、藩の意識を超えて国家・国民を救ふ高処に立つ武士道を示唆し、南洲をして討幕維新へと決意させたのは、実にこの海舟の言葉であった。やがてこの海舟と南洲の両雄は、幕府方軍事総裁と官軍方参謀といふ互ひに敵と味方の代表として再び相まみえることになる。慶応4年(1868)の「江戸開城談判」である。
江戸百万の民の命を救ふ、いや虎視眈々と侵略の間隙を狙ふ列強から日本を守るためのまさに正念場であった。この重大な会談に臨み、海舟は身の危険を顧みず、従者を一人連れたばかりで江戸の薩摩屋敷に出かけて行った。海舟が一室に案内されて待ってゐると、南洲もまた、いつもの熊次郎といふ忠僕を従へただけで、平気な顔でやってきた。その時の模様を海舟はかう述べてゐる。
「さて、いよいよ談判になると、西郷は、おれのいふ事を一々信用してくれ、その間一点の疑念も挟まなかった。『いろいろむつかしい議論もありませうが、私が一身にかけて御引受けします』西郷のこの一言で、江戸百万の生霊も、その命と財産とを保つことが出来、また徳川氏もその滅亡を免れたのだ。(略)この時、おれがことに感心したのは、西郷がおれに対して、幕府の重臣たるだけの敬礼を失はず、談判の時にも、始終座を正して手を膝の上に載せ、少しも戦勝の威光でもって、敗軍の将を軽蔑するといふやうな風が見えなかった事だ」(『氷川清話』)。
日本を救ふために我が身を捨てて少しも顧みない海舟の武士道が南洲の魂に深く響いたのである。「士は己を知る者の為に死す」といはれるが、暗殺者が跋扈する危険な世相の中で、互ひに己の命を差し出し、誠を尽すこの二人の武士によって「江戸無血開城」は成ったのである。
「我徳川氏の士民と雖も皇国の一民なり」 ―南洲宛の書翰―
実は、「江戸開城談判」は三舟の連携協働ではじめて実現したものである。東征軍参謀西郷南洲が江戸総攻撃を決意して駿府まで攻め寄せた時、鉄舟の義兄高橋泥舟は将軍慶喜に恭順論を説き、恭順の意を伝へるために自分の代りに義弟鐵舟を駿府へ派遣することを求めた。この駿府行きが決まった鐵舟に、海舟が託した南洲宛ての手紙がある。
| 「無偏無党、王道堂々矣(たり)。今官軍鄙府(ひふ)(江戸)に逼(せま)ると雖(いへど)も、君臣謹んで恭順の礼を守るは、我徳川氏の士民と雖も皇国の一民たるを以ての故なり。且は皇国当今の形勢、昔時に異なり、兄弟(けいてい)牆(かき)に鬩(せめ)げども、外其侮を防ぐの時なるを知ればなり」(『幕末の三舟』) |
いかなる党派にも属さず超然として王道をゆく。君臣ともに恭順の礼を守るのは、徳川幕府の士民といへども同じ皇国の民だからである。わが国はいま、兄弟が内輪もめをしてゐる場合ではない。今こそ、欧米列強の外からの侮りを防ぐまさにその時ではないのか。実にこの書面に、私心を捨てた「公」の高処に立ち、わが国を救はうとする海舟の武士道がみごとに顕れてゐる。
海舟は江戸開城談判の裏で、談判に失敗し、江戸が総攻撃される最悪の事態にも備へてゐた。海舟は、自ら借金をしてこれを侠客の新門辰五郎に渡し、舟をかき集めて江戸から難民を救済する措置を講じてゐた(『人間勝海舟』)。また、江戸幕府が瓦解した維新後も、七十万石大名となった徳川旧将軍家の財政を支へて、困窮した旧幕臣の生活を援助し、敗戦の処理にも力を尽した。「智の人」といはれる海舟は、父小吉の義侠心を譲り受けた誠実な「仁の人」でもあったのである。
「(おれは)いつもまづ勝敗の念を度外に置き、虚心坦懐、事変に処した。それで小にして刺客、乱暴人の厄を逃れ、大にして瓦解前後の難局に処して、綽々(しゃくしゃく)として余地を有った。これ畢竟、剣術と禅学の二道より得来った賜(たまもの)であった」(『氷川清話』)と海舟は述べてゐる。
海舟は、頭、脇腹と足の三ヶ所に傷があり、20回ほど刺客に襲はれたといふ。海舟は剣術の達人でありながら、しかし、一度も刀を抜くことをしなかった。「戈(戦ひ)を止めるを武と為す」といふ「武」の本当の意味を知ってゐたからである。真の勇気は刀を抜くことではない。私を捨て去り、治国平天下に身命を賭すことにある。凛然として「公」のために誠を尽す「尚武のこころ」とその魂魄にこそ、海舟の武士道があったのである。
(神奈川県立小田原高校定時制教諭)
米朝対峙で、自立意志の如何が問はれてゐる
― 憲法改正は「国の誇り」を取り戻す第一歩―
米大陸に達する北のミサイル!
昨平成29年7月28日深夜、北朝鮮から発射された大陸間弾道ミサイル(ICBM)は北海道の奥尻島北西150キロ、日本海のわが国の排他的経済水域(EEZ)に落下した。高度は3,500キロに達して、通常軌道ならば北米大陸東海岸に到達しようかといふものだった。その三週間あまり前の7月4日、即ち米国の独立記念日にもその鼻を明かすかのやうに高度2,800キロのICBMを発射してゐた。ICBMは戦略核の運搬手段となるもので、つひに北朝鮮は米国本土に達するミサイル発射の能力を持ったのである。
当然に米国側が厳しく反撥して、原子力空母や戦略爆撃機の派遣、国連での経済制裁決議採択など、軍事と外交の両面で北朝鮮に圧力を掛けてゐることは周知の通りである。
何としても米国の眼を自国に向けさせて対米直接交渉に持ち込みたいと挑発行為を繰り返す北朝鮮は、さらに9月3日、六度目の核実験を実施し、11月29日には新型のICBM「火星15型」の発射実験に成功したと発表した…。
体制維持のため狡知の限りを尽すかに見える北朝鮮に対して、米国はその核放棄に向けて軍事力の行使を含むあらゆる手立てを執ると公言してゐる。
北への怒りが本当にあるのか―拉致とミサイルの上空通過―
問題はわが日本である。
米国を射程に収める北朝鮮のミサイルは、日本列島など目ではない。既に20年前の8月、中距離弾道ミサイル「テポドン1号」が日本上空を通過して三陸沖に落下してゐた。
昨年9月15日発射のミサイルは六度目の上空通過となって、北海道襟裳岬の東約2,200キロの北太平洋に落下した。米朝の対立対決が軍事衝突につながることを危惧する声は聞くが、ミサイルの上空通過への怒りの声が、かつても今もどれだけあっただらうか。軍事衝突は避けられるに越したことはないが、邦人拉致についてもさうだったが、ストレートな怒りの声がどれだけ挙がっただらうか。確かに国会は何度か非難決議を採択したが、それだけで済まされることではない。ミサイルの上空通過を自らの危機として真に受け止めてゐるのだらうか。拉致事件にしても、それは許し難い人権侵害であるばかりか、北朝鮮の工作員がどこからともなく密入出国を繰り返してゐたといふ重大なる国権の侵犯事案でもあるのだ。
今春、国民文化研究会事務局に届いた年賀状の中に左のやうな一首があった。
北の脅威つづく
国挙げて迷ふことなく今こそは民が一つにしたたかに立て
まことに歌意簡明で、わが国の現状へのもどかしい思ひが直截に詠み込まれてゐる。
ミサイルの上空通過は国防上の最大級の危機であって、日本列島全体が人質に取られたやうなものである。並の国家ならば、「国挙げて迷ふことなく」怒りの声が発せられ、メディアはこぞってわが防禦策は大丈夫かと政府を問ひただし、その尻をたたくことだらう。
内憂外患とか国難とかといふ言葉があるが、「民が一つにしたたかに立て」なくなってゐることが、内憂でありそれが外患を呼び寄せてゐる。かうした現状こそが国難なのである。
朝日新聞の信じがたい社説
例へば、度重なるミサイル発射を前にして、やうやく防衛省は、12月8日、戦闘機に搭載する巡航ミサイルの導入を決めた。これに対して朝日新聞は「専守防衛の枠を超える」として、早速に異を唱へた(12月13日付社説)。その理由は「航空自衛隊の戦闘機に搭載する米国製ミサイルは射程900キロ。日本海から発射すれば北朝鮮全域に届く。(略)長距離巡航ミサイルの導入は、専守防衛の枠を超えると言うほかはない」といふものだった。この期に及んで猶も朝日の社説は「日本海から発射すれば北朝鮮全域に届く」などと妄言を弄してゐる。かうした論説が「国挙げて迷ふことなく…」とはならなくさせてゐる。社説の矛先は「なし崩しに安全保障政策の転換をはかる安倍政権の姿勢は危うい」と内に向けられてゐる。北朝鮮に届くミサイルの装備は、多少なりとも抑止力になるとは考へないのだらうか。
自国不信の根柢ある「米軍の『矛』」への甘え
この社説では巡航ミサイル導入方針を次のやうにも批判してゐる。
「日本の安全保障は、米軍が攻撃を担う『矛』、自衛隊が守りに徹する『盾』の役割を担ってきた。この基本姿勢の変更と受け止められれば、周辺国の警戒を招き、かえって地域の安定を損ねる恐れもある」
自国の防衛のために、米国が「矛」を振りまはして「攻撃を担う」ことは構はないが、わが国は「矛」さへ持ってはならないといふのだから絵に描いたやうな自国不信である。日本が「矛」を少しでも持てば「周辺国の警戒を招き、かえって地域の安定を損ねる恐れもある」といふのだから正気の沙汰ではない。北朝鮮ばかりか、疾(と)うの昔にロシア、中国は射程1万キロ以上のICBMを保有してゐて日本列島は彼らの射程距離に入ってゐるのだ。かうした自国不信は「米軍の『矛』」に頼り切った甘えと表裏してゐる。
恐るべき「誇りの欠如」
このやうな社説が麗々しくも代表的な全国紙!?を飾る根源に「平和憲法」と通称されてゐる〈日本国憲法〉があることはいふまでもないだらう。それはかつて「日本の弱体化」を企図した米国主体の占領軍の起草によるもので、前文で「自国の安全を他国にゆだねる」と自存努力の放棄が宣言され、第九条に「戦力の不保持」と「交戦権の否認」が謳はれてゐる。字面(じづら)から言へば「盾」を用意してゐることさへ違憲だといふことになる。憲法学者の七割が自衛隊違憲論に立つといふのも分らなくはない。しかもその多くがこの「平和憲法」のままでいいといふのだから、自国不信、否「誇りの欠如」もここに極まれりである。
相互性ある対米関係を目指せ
現今の米朝対峙では、わが国の自立意志の如何が改めて問はれてゐるのである。
文字通りの「波静かな太平洋」は、わが国の存立にとって欠かせない要件であることはいふまでもない。そのためには、かつて「平和憲法」を強要して「日本の弱体化」を図った米国といへども協力関係が不可欠である。その「日本弱体化」(戦後体制)の軛(くびき)から、どう脱するか。平等互恵の日米関係をどう打ち立てるか。それは偏(ひとへ)に我ら日本国民の肩に掛かってゐる。〈日本国憲法〉の根本的見直し、改正は、そのためのほんの第一歩に過ぎない。
我らは昨夏、62回目の宿泊研修「合宿教室」を営んだ。そこでは聖徳太子が語られ、万葉集が語られ、わが「国柄の特質」が語られた。参加者全員が「国語のいのち」に触れるべく短歌創作に取り組んだ。それは「先人の心」を仰ぎ「先人の生き方」に学ぶことこそが、日本人に本来、そなはってゐる伸びやかな精神につながる道であると信じるからである。(略)
(標題、小見出しは加筆した)
昨夏の福岡合宿教室の記録『日本への回帰』第53集
学問と人生―小林秀雄に学ぶ― 埼玉県企業立地課 飯島隆史
国の目覚めと万葉集の心 原土井病院院長 小柳左門
聖徳太子の御言葉に触れて (株)IHIエアロスペース 内海勝彦
日本の「国柄」―私たちの文化― 元拓殖大学日文研客員教授 山内健生
短歌創作導入講義 若築建設(株)池松伸典
創作短歌全体批評 熊本県立第二高校教諭 今村武人
頒価900円 送料215円
5.女性天皇の事例と宮家女性 当主の事例
それでは、「女帝」は、御即位以前は総て「内親王」であられたのか。また、「女帝の子」とは、女帝が御即位以前にお生みになった御子を指すのか、それとも、御即位以後にお生みになった御子を指すのか。歴史上の十代八方の女性天皇の事例を、以下の各期に分けて述べてみよう。
ここで、大宝令成立以前(第1代・神武天皇から第42代・文武天皇まで)を第一期、大宝令成立以降明治前期まで(第43代・元明天皇から第122代・明治天皇まで)を第二期、明治の皇室典範成立以降今日まで(第123代・大正天皇から第125代・今上陛下まで)を第三期と区分して、女性天皇史を中心に概観すると、以下のやうになる。
第一期
女性天皇は三方で、総て皇統に属する男系の皇親であられた。第23代・推古天皇と第41代・持統天皇のお二方は内親王(皇女)であられたが、第35代・皇極天皇(重祚して第37代・斉明天皇)は特殊で、御即位以前の父系系譜上の御身分は、三世女王であられた。しかも、第34代・舒明天皇とは御再婚で、前夫の高(たか)向(むく)王(第31代・用明天皇の二世王)との間に漢(あやの)皇(み)子(こ)をまうけてをられた。
ここで仮に、後に制定された大宝継嗣令第一條の本注規定を、遡って皇極天皇のお子様達にあてはめてみると、以下のやうになるであらう。すなはち、
「皇極天皇が御自身の御即位以前に舒明天皇との間にまうけられた御子達(後の第38代・天智天皇や第40代・天武天皇等)は、舒明天皇、すなはち、御子達の父君が即位された時点で既に親王(皇子)となられたが、一方、漢皇子は高向王との間にお生れであったので、この時点では、父系系譜上は依然三世王であられた。だが、その後、母君が天皇になられたので、この時点で「女帝の子」となられた漢皇子は、早速「親王の御身分に昇格してしんぜよ」といふことになり、この時点から一躍、親王の御身分に昇格されることになった」
といふ筋書きとならう。
このやうな皇極天皇のお子様の実例が存したので、その後に制定された大宝継嗣令では、このやうなことが起きても対処できるやうにと、この「本注」が第一條に書き込まれることになったものと思はれる。
また、大宝継嗣令第一條「本注」に対する「古記」の注釈には、「女帝になるには内親王であること」と読み取れるやうな注釈は、一切見られない。これは、皇極天皇の御即位前の御身分が、内親王ではなく下位の三世女王であられたことの反映とも思はれてくる。
なほ、女性天皇お三方は総て天皇の寡(か)婦(ふ)であられて、御在位の期間とそれ以降は、生存する配偶者を持たれてはゐない。
第二期
女性天皇は五方で、総て皇統に属する男系の皇親であられた。第43代・元明天皇、第46代・孝謙天皇(重祚して第48代・称徳天皇)、第109代・明正天皇、第117代・後桜町天皇の四方は内親王(皇女)であられたが、第44代・元正天皇だけはやや特殊で、御即位前の父系系譜上の御身分は二世女王であられた。ただし、弟宮が697年に先に即位されたので(第42代・文武天皇)、もし大宝令制定以前に継嗣令第一條に類する規定が存してゐたとすれば、姉君の元正天皇は、この時点で内親王に昇格されたであらう。また、慶雲四年(707)には母君の元明天皇が即位されたので、遅くともこの時点で、大宝継嗣令第一條の「本注」規定・「女帝の子も亦同じ」に則って、二世女王から内親王の御身分に昇格されたはずである。なほ、この元正天皇の御退位から14年後の天平10年(738)頃に、大宝令の注釈書「古記」が出来上った。大宝継嗣令第一條に既に「本注」が存したとする説は、この「古記」の注釈文に根拠を置いてゐる。また、元正天皇の父君の草壁皇子は皇太子のまま薨(こう)去(きょ)されたが、第47代・淳仁天皇の御代に、文武・元正両天皇の父君であられたことにより「岡宮天皇」と追尊されて、追尊天皇の初例となられた。
なほ、五方は総て、御在位の期間とそれ以降は、生存する配偶者を持たれてはゐない。元明天皇お一方だけが皇太子の寡婦、それ以降に順次即位された四方は、未婚のまま、終生独身を貫かれた。特に、元正天皇は美貌であられたが、36歳で御即位、45歳で御退位、崩御は69歳で、終生「独り身」を持された。若き日に元正天皇が婚姻なさらなかったのは、文武天皇の御子による直系継承を強く望まれた持統天皇の御意向に沿って、万一の場合の「中継ぎ天皇」の役目を自覚され自重されたためであらうとする説がある。
第二期においては、時代が下るにつれて、内親王や女王が臣下の男性と婚姻される場合が出てきた。しかし、そのやうな場合でも、婚姻を通じて臣下の者を皇親になさることは決してなかった。なぜなら、皇親とは、生れながらの血統上の御身分だったからである。その結果、皇胤にあらざる男性が皇親になることは、史上一度もなかったのである。従って、皇親の範囲内には皇胤以外の種の保有者は皆無であった。その意味で、天皇と皇親からなる「皇室」は、聖域であり続けたのである。
なほ、女性天皇とは異なるが、幕末から明治前期にかけて、桂宮家に、宮家史上唯一の女性当主が現れた。仁孝天皇の皇女、淑(すみ)子(こ)内親王である。淑子内親王は、当主御就任の期間とそれ以降は、女性天皇に課せられた不文律に従はれるかのやうに配偶者を持たれず、ひたすら、宮家後継の当代皇子の誕生・成長を待ち続けられた。だが、それも叶はず、明治14年に未婚のまま薨去され、桂宮家はこの代で絶家となった。
(第三期については、後述する。)
六.明治皇室典範の立案過程における検討
明治皇室典範の立案に中心的役割を果した井上毅が、その途中で有益なヒントを得たものに、小中村清矩の『女帝考』がある。これは、東大教授だった小中村が、明治18年10月頃に宮内省の制度取調局に提出した資料体裁の短編である。第14代・仲哀天皇の皇后で、第15代・応神天皇の母君でもあられた神(じん)功(ぐう)皇后、並びに、第23代・顕(けん)宗(ぞう)天皇と第24代・仁賢天皇両御兄弟の姉君であられた飯(いひ)豊(とよ)青(あをの)尊(みこと)、さらに、前述した10代八方の女性天皇を含めて、その方々の略歴を紹介した後、附録として実に貴重な一文を残してゐる。それは、養老継嗣令第一條「本注」の『令義解』公権注釈に対する、彼自身の以下の解釈である。
「此女帝ノ子トイヘル事、令中ノ難儀ナルヲ、熟考スルニ、義解ノ趣ニテハ、女帝未ダ内親王タリシ時、四世以上ノ諸王ニ嫁シテ(中略)生玉ヒシ子アラバ、即位ノ後、親王ト為ヨトノ義ト聞エタリ。
サテ、遠ク古(こ)蹤(しょう)ヲ考ルニ、皇極天皇ハ、初メ用明天皇ノ孫高向王ニ嫁シ玉ヒテ漢皇子ヲ生玉ヒシ。(中略)此ノ漢皇子ノ類ヲ以テ女帝ノ子ト称スベキ歟(か)。(此説ハ、予ガ私考ニアラズ、河村秀根ノ講令備考ニ云ヘルナリ。)(中略)皇極天皇ノ先蹤ニヨリ将来ヲ想像シ、此條ヲ立ラレシモノト覚ユルナリ」(所 功著『近現代の「女性天皇」論』に所収、展転社、平成13年)。
ここに言ふ河村秀根(ひでね)とは、名古屋藩士で国学者の河村秀根のことである。江戸時代後期の文政年間に、河村秀穎(ひでかい)(秀興)・河村秀根兄弟を中心に『令義解』の研究が行はれ、その成果として『講令備考』が著された。秀穎らは、『日本書紀』斉明紀の漢皇子の事例を挙げ、令に云ふ「女帝の子」とは、皇極女帝が御即位の前にお生みになった漢皇子の類ひであるとした。
小中村は、これに眼をとめて同意した。悩みの種が氷解したのである。
『令義解』が説くところの「本注」の意味とは、「女帝がまだ天皇になられる前の内親王であられた時に、四世以内の諸王に嫁してお生みになった御子があるならば、女帝御即位の後に、その御子を親王とせよ」といふ意味に受けとれるとしたのである。
さて、井上毅は、神功皇后と飯豊青尊お二方を、皇位空位の間、皇位には即かれず摂政に似た立場にあられた方々と看做し、以後の10代八方の女性天皇を皇位に即かれた方々と観た。また、歴史上の女性天皇は、総て一時的に已むを得ず皇位に就かれた方々であって、これらの御即位は、次の男子皇嗣に皇位を伝へるまでの「権宜」(便宜の処置)に外ならなかったと判断した。なほ、小中村は、明治22年2月に「女帝論」と題する講演を行ってをり、その中で、我が国の女帝は夫(皇婿)の有る欧(ヨー)羅(ロッ)巴(パ)の女帝とは異なること、また、女帝の御即位事情には三種があり、推古天皇・皇極天皇は、時の政治的事情によって御即位になり、孝謙天皇・明正天皇は、女帝の例があるが故に父帝の個人的御意思によって御即位になり、持統天皇・元明天皇・(元正天皇)・後桜町天皇は、皇太子御成人までの中継ぎ役として御即位になったと述べてゐる(小林 宏「井上毅の女帝廃止論―皇室典範第一条の成立に関して―」、梧陰文庫研究会編『明治国家形成と井上 毅』所収、木鐸社、平成4年)。
明治の皇室典範は、女性天皇を認めず、代って、女性摂政を認めることになった。それは、上述のやうな認識のもとに立案されたのである。
(元新潟工科大学教授)
本書は、大きく分けて、①高校生・大学生に向けて語られたもの、②大学の紀要に寄せられた論文、③天皇についての論考といふ三部構成をとってゐるが、始めの部だけでなく②、③の部分の文章も、難しい言葉文章には必ず平易な説明、解釈が付されてゐて、辞書的な意味では勿論のこと体験的な意味でも、読み手にわかるやう細やかな配慮が為されてゐる。このことは小柳陽太郎先生の文章制作における厳しいご内省と同時に、先生が、いつも文章を、人生をより良く生きようと志す高校生、大学生等の若い人達に読んで貰ふことを念頭に、書かれてゐたのではないかと思はせられるところである。
編集上の配慮も行き届いてゐて、本の大きさ、厚み、重さにおいても、手に取って読み易い一冊になってをり、その意味でも本書は若い人向けの「人生の学問」の恰好の入門書になってゐる。
ただし細やかな配慮がなされてゐるからといって、内容が平易といふ訳ではない。例へば次のやうである。
「宣長にとって学問をするということは、宇宙全体に心を拡げていく、あらゆるものを自分の中に吸収していくということなのです」(「日本の伝統に見られる教育思想」)
江戸時代の学者本居宣長の、儒教的倫理観で頑(かたく)なになった友人への、素直で柔軟な心のあらはれた手紙についての先生の評言であるが、大事なのはこの「宇宙全体に心を拡げていく、あらゆるものを自分の中に吸収していくということ」が、先生ご自身が拘りを離れて、伸びやかに「心を拡げて」「あらゆるものを自分の中に吸収して」いかうとされて周りの人々と付き合ってをられるご体験から生れた言葉に違ひないことである。
また、次も、つくづく考へさせられるご指摘である。「われわれが一つの漢字を、一字一画誤ることなく、しかも正しい筆順で書くことを訓練されてきたのは、その文字の中に、祖先の情感のあとを偲び、それを正しくうけとめるための大事な作業であった」(「国語教科書批判」)
パソコンで文章を書くことが多い私には、耳が痛いお言葉である。今は、一字一画を手で書かないだけでなく、他所の文章を簡単にコピーして貼り付けられるので、言葉の思ひを受け止める、言葉に思ひを籠めることがより疎かになってゐるやうに思ふ。一字一句に思ひの籠る文章とはかういふものかと、本書を感嘆しながら読む中で、自分もかくありたいと思はされるのである。
そんな、生きる上での本質的な難しさを何とか伝へようと、優しく平易な言葉で綴られたのが、先生の文章であった。
本書編集の願ひが、「はしがき」(山口秀範氏)の結びに尽されてゐると思はれるので、見ておきたい。
「世代を超えた学び合いが本書を通じて始まり、『日本のいのちに至る道』を実感する若者が一人でも多く生まれることを、誰よりも著者は望んでいるに違いない」
『いのち』とは、感動の源泉となるものであらう。それは国家公共のために生命を燃焼させて生きた先人達の生き方や言葉であったり、美しい自然であったり、とにかくそれによって我々が感動して語り合ひ、心が通ふよろこびを味はへる全てのことだと思ふ。そこに『至る道』とは例へば本書である。感動の源泉に至るには、具体的な方法、道が必要である。その一つがこの本であらう。そこで、最後に『日本の』であるが、これは端的に、私達にとって一番身近で親しくなつかしいのが、国語によって、今の世も祖先達とも、心が結びつけられてゐるこの祖国日本の、といふ意味合があると思ふ。
本書は、内容と文章の良さで比類なく、多くの人に読まれ、世代を超えて語り継がれるに違ひない。そのひろやかな心の交流の世界に連なる事を得た一人として、感想の一端を述べさせていただき、本書の紹介とさせていただく。
(元(株)アルバック 北濱 道)
小柳陽太郎著作集
『日本のいのちに至る道』読者特別頒価 送料込2,500円
申込先03-(5468)6230
春の吟詠会の御案内
主催 国民文化研究会東京短歌の会
昨年秋の吟詠会に引き続き薫風香る万葉植物園を散策し、吟詠した詠草を互ひに感想を述べ合って有意義なひとときを過したいと企画いたしました。本紙の購読者の皆様の御参加をお待ちしてをります。
連絡先: 国文研事務局 03(5468)6230
日 時: 5月26日(土)集合場所 武蔵野線市川大野駅前
(改札1ヶ所です)10時45分
会 場: 市川市万葉植物園 (駅から徒歩5分です)
費 用: 交通費のみご負担下さい。
スケジュール(予定) ・庭園散策(短歌創作)11時~12時
・昼食12時(弁当各自持参)
・短歌相互批評 午後1時~3時
・聖徳太子勉強会の紹介~4時半
・メモ用紙、筆記具はご用意下さい。
当日の連絡先
宇野 090(4058)2069
奥冨 080(3000)2321
編集後記
「明治百年」が話題になってゐた昭和43年前後、まだ学生の身だったが、左右を問はず“公共心”が横溢してゐたやうに想ふ。我利我利亡者は稀だった。今は専ら功利効率の追求だ。それは教育界にも及ぶ。
(山内)