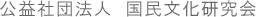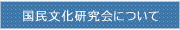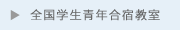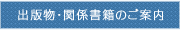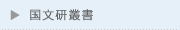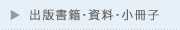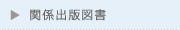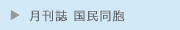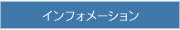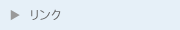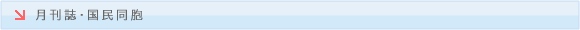
第675号
| 執筆者 | 題名 |
| 理事長 今林賢郁 | 〝男子の本懐〟 - 「国民の負託」に応へて憲法改正に取り組め! - |
| 廣木 寧 | 歌碑と独立樹(上) - 斎藤茂吉と小林秀雄 - |
| 小野 吉宣 | 過ぎ来し日を思ひ、いま思ふこと - 国民文化の精髄を守らう - |
| 横畑 雄基 | サムライ科学者 高峰譲吉 - 「日本人科学者」として生きた、その気概に学べ! - |
| 小柳陽太郎先生の【古典の窓】から |
昨秋の国政選挙で自民党は初めて「憲法改正」を公約として掲げ、周知の通り選挙に大勝し、昨年11月1日、第四次安倍内閣が発足した。戦後の首相で第四次まで組閣したのは昭和27年の吉田茂以来であり、今秋の自民党総裁選で安倍首相が三選されて政権が続けば、来年11月には桂太郎の首相在任期間(2886日)を抜いて憲政史上最長になると言ふ。戦後政治の最重要にして最難関課題である憲法改正実現のためにはさうあって欲しいと思ふが、政権の長期化と共に世論の反発や人心の離反が起るのも又避けがたい。
殊に厄介なのはその時の気分や好悪の感情で動く世論である。政治指導者には国家の向ふべき方向を見定める先見力、その実現を見通す洞察力、危機に動じない胆力、そして何よりも決断力が必要とされる。だが指導者の力量がいかに優れたものであっても世の先を行き過ぎると必ず世論の反発に遭ふ。加へて一部新聞やテレビなどによる一面的な情報が連日流されると、世論は政治指導者の資質や理念、政策の是非を問ふ前に指導者を好きか嫌いかといった低次元の方向に誘導されてしまふ。
例へば「安倍一強」だが、この言葉には安倍晋三といふ男が、絶大な権力を好き勝手に行使し、独裁者として国政を私物化してゐるかの如き印象操作の罠がある。「新聞で見分けるフェイク知るファクト」─これは昨年の新聞週間標語であったが、こんな虚報もどき標語に惑はされてはならない。今問はれてゐるのは読者自身のフェイク(嘘)とファクト(事実)とを識別する眼力である。
ともあれ国民は安倍政権の5年間の仕事を評価し今後の国政を自民党に委ねたのである。驕らず丁寧な政権運営に努めて貰ひたいと思ふ。
昭和四年に公開された映画「大学は出たけれど」(小津安二郎監督)は、大学卒業者の就職率が30%といふ世相を反映して国民から広い共感を得たが、この年の7月、民政党の浜口雄幸(おさち)内閣が誕生した。浜口はその風貌から「ライオン宰相」と呼ばれたが、その実直、公明正大、誠実な人柄は国民から信頼と親しみをもって迎へられた。特段の趣味道楽を持たなかった浜口に対して、世人が浜口にとって政治が「唯一の趣味道楽」であると言った時、浜口は怒った。「政治が趣味道楽であってたまるものか、凡そ政治程真剣なものはない、命懸けでやるべきものである。苟(いやしく)も政治は趣味道楽であると言ふ思想が一片たりとも政治家や国民の頭脳に存在する以上は、それが戯談でない限り一国の政治の腐敗するのは寧ろ当然である」(遺稿『随感録』)。
この信念で組閣の大命を拝した浜口は、「爾来、家族のものにそれとなく其の決心を告げ、まさかの場合に狼狽せぬやう覚悟をなさしめ…何れ一度は死ぬる命だ。国家のために斃るれば寧ろ本懐とする所だ」(同)と考へてゐた。ロンドン軍縮会議における協定案が海軍軍令部の強硬な反対で成立が危ぶまれた時、浜口は「自分が政権を失うとも民政党を失うともまた自分の身命を失うとも奪うべからざる堅き決心なり」と述べ条約を締結に導いた(波多野 勝『浜口雄幸』)。浜口の決意と豪胆を如実に示す言葉である。内閣の今ひとつの主要課題であった金解禁も断行したが、軍縮条約が批准されてから1ヶ月後、浜口は東京駅のプラットホームで近くに居た青年に狙撃されて重傷を負った。偶々東京駅にゐた幣原喜重郎(浜口内閣外務大臣)が駆けつけると「男子の本懐」と漏らしたと伝へられてゐる。首相在任期間ほぼ2年、謹厳実直な人柄そのままに、嘘のない政治生活を貫き通した政治家であった(狙撃から9ヶ月後に死去。62歳)。
憲法改正は政治家の政治生命を賭けるに足る大一番である。政治の劣化と政治家の資質の低下が指摘される今日、自民党の議員諸氏は、かつてこの政治の世界に、国家のためであれば自分の政権も自分の政党も、自分の命すら投げ出す覚悟で戦った政治家がゐたことに思ひを致し、諸氏の政治生活が「男子の本懐」と最後に総括できるやうなものであることを望みたい。それが国民の負託に応へる責務といふものであらう。
1
歌人斎藤茂吉(さいとうもきち)の歌碑は現在全国各地に建ってゐるが、生前に茂吉が建立を許した歌碑はただ一基のみである。
事の起りは、茂吉のふるさと山形の地元青年団と茂吉の実弟で上山(かみのやま)に山城屋といふ旅館を営む高橋四郎兵衛とが諮(はか)ったもののやうである。
昭和9年―この年茂吉は52歳になる―6月20日付四郎兵衛宛ての茂吉書簡に、「歌碑建立の件は、最初から余り賛成でなかつたのであるが、いよいよ建てると決心した以上は飽くまで、徹底的にやる」とある。その9日前の同じく四郎兵衛宛ての書簡には、
| 《歌碑は秘密にするぐらゐにして仕事を進めること大切也(なり)さにあらずばこまるべし一、広告にしたり、利用したり、お祭騒ぎ等一切いかぬ、これが実行出来なければはじめよりやめる一、高湯青年団はどういふ気持で好意を持つてくれるのだか、(中略)一、黙つて建て、黙つて置くやうにして、建てたいのである。一体四郎兵衛の気持にこの覚悟ありや否や、若しこの覚悟があるのなら、「高橋四郎兵衛建之」と彫つてもいゝ。一、登山者が、計らず見付けるやうならばよろしからむ》 |
と記されてゐる。
茂吉の同年6月4日の日記に、「月曜、晴、午前中部屋掃除ヲナス 午(ご)睡(すい)、午后(ごご)ヨリ夜ニカケテ、蔵王山ノ歌碑、犬飼氏墓表、牛尾氏墓ノ歌ヲカク。ヘトヘトニツカル。夕方、世田谷ニ往診ス」とある。茂吉の歌碑は山形、宮城両県の境に立つ蔵王連峰の山上に建てることになってゐた。先に引いた6月11日付の四郎兵衛宛ての書簡に「御申越どほり四尺五寸(136.4センチ)に二尺六寸(78.4センチ)にしてかいた」とある。
茂吉が歌碑のために詠んだ歌は、「6月4日、舎弟高橋四郎兵衛が企てのままに蔵王山上歌碑の一首を作りて送る」といふ詞書(ことばがき)のある次のものである。
陸奥(みちのく)をふたわけざまに聳(そび)えたまふ蔵王の山の雲の中に立つ
なほ、6月4日の日記に「夕方、世田谷ニ往診ス」とあるのは、茂吉が東大医学部卒業の精神科医であることによる。
茂吉が蔵王山上に建った歌碑を見るのは建碑から五年後の昭和14年7月8日のことである。「黙つて建て、黙つて置くやうにして、建てたい」と話したことを茂吉自身も実行したかのやうである。
「歌碑行」といふ詞書のある連作十一首の冒頭に
いただきに寂しくたてる歌碑見むと蔵王の山を息あへぎのぼる
とある。
そして、いよいよ歌碑の前に立った歌が来る。「7月8日歌碑を見むとて蔵王山に登る。同行岡本信二郎、河野與一、河野多麻、結城哀草果、高橋四郎兵衛の諸氏」といふ詞書のある連作十一首である。五首を引く。
歌碑のまへにわれは来りて時のまは言(こと)ぞ絶えたるあはれ高山(たかやま)や
わが歌碑のたてる蔵王につひにのぼりけふの一日(ひとひ)をながく思はむ
一冬(ひとふゆ)を雪にうもるる吾が歌碑が春の光に会(あ)へらくおもほゆ
この山に寂しくたてるわが歌碑よ月あかき夜(よ)をわれはおもはむ
みちのくの蔵王の山に消(け)のこれる雪を食ひたり沁みとほるまで
7月8日は、蔵王山頂から鳥海山がのぞまれるほど晴れてゐた。日記に、「歌碑ノ前ニテ食事ス。歌碑ハ大キク且ツ孤独ニテ大(おおい)ニヨイ。残雪ヲ食タ。風強イ。午後4時高湯着」とある。
蔵王山上歌碑建立の話が持ち上がって動いてゐたころ、茂吉年少の歌友中村憲吉が5月5日に死んだ。憲吉歌碑のことで、憲吉の治療に尽力した医師高亀良樹宛て書簡で茂吉は、「どつしりしたもので、あまり奇でなくひよろひよろせぬものがよろしかるべきか」と意見を述べてゐるが、蔵王山上の歌碑も「大キ」かった。碑身の高さと幅195センチと117センチで、台座を含めた全体の高さは342センチである。門弟の柴生田(しぼうた)稔(みのる)には、「哥碑(か ひ)は立派に御座候(ござそうろう)」と報告してゐる。
歌碑建立は茂吉本人が建碑五年後に歌碑に見参してゐるのだから、「黙つて建て、黙つて置くやうにして、建て」られたことになる。「お祭騒ぎ等一切」なかった。茂吉はそれを「孤独ニテ大ニヨイ」と表現した。歌碑建立は所期のとほり運んだのである。
昨年(平成29年)5月に上山
市にある斎藤茂吉記念館を訪ねる機会をもった。豊富な展示物に充実した時間があった。茂吉の長男、次男が生前に父茂吉について語ってゐる映像に見入ったが、その最後に、蔵王山上の歌碑が映し出された。「一冬を雪にうもるる吾が歌碑」はどういふ姿をしてゐるのかを眼前に見ることになった。雪が凍りついて樹氷の状態となってゐた。歌碑は風雪に真向からこそ、自己の充足を表現してゐる。息をのむ思ひであった。唐突だが、僕は小林秀雄のことを思ったのである。
2
小林秀雄歿後20年の平成15年に、『小林秀雄の思ひ出』の著者郡司勝義は「桜と小林秀雄」を発表した。郡司は著書の中で、小林の「近くにゐて終始接してゐる者」と自ら述べてゐる人である。「桜と小林秀雄」の冒頭に、
| 《「さくら」と言ふと、小林秀雄の名に結びつけて語られる慣(なら)はしとなつたのは、ここ40年来のことである。》 |
と書いてゐる。郡司のいふ「40年」前頃に、小林は「花見」といふ文を発表してゐる。「花見」は、昭和39年5月初旬に東北地方(酒田、弘前)を講演旅行したときに覚えた「さくら」をめぐる歴史随想といった趣きのものである。
| 《弘前城の花は、見事な満開であつた。背景には、岩木山が、頂の雪を雲に隠して、雄大な山裾を見せ、落花の下で、人々は飲み食ひ、狂ほしいやうに踊つてゐた。(中略) その夜も亦、新築の立派な市民会館で、「今日は、結構なお花見をさせて戴きまして」と言つて、文化講演とやらには全くそぐはない気持ちになつて了つた。外に出ると、たゞ、呆(あき)れるばかりの夜桜である。千朶万(せんだまん)朶(だ)枝を圧して低し、といふやうな月並な文句が、忽ち息を吹返して来るのが面白い。》 |
郡司によると、弘前城の桜を見た昭和39年に、小林は岐阜の山奥に樹齢千年を超えて生命を保ち続けてゐる桜があることを知った。小林は興奮し、眼はぎらぎらと輝いた。翌年の4月上旬に、小林はこの飛騨根尾谷の淡墨(うすずみ)桜を見に出掛けた。
| 《この名高い彼岸桜の開花を見た時、非常に強い印象を受けた。樹齢千年を越えると伝へられる老木の幹は巨巌の如く、そこから枝は四方に延び、細分して、網の目のやうに空を覆ふところで、いかにも老木らしい小粒な、淡い花が、満開であつた。それは、梢の黒い細線を、一面に透かし、まさに淡墨を流した風情に見えたのに驚いた事がある。》(「土牛素描」・傍点引用者) 郡司は、小林のいふ「非常に強い印象を受けた」とは何か、を語る、 《昭和40年の淡墨桜見学行は、小林の思索を一段と充実させた。ここ数年、氏を領してゐた「独」といふ思想――「天地の間に己れひとり生きてありと思ふべし」といふ思想と、この名桜がおのづと絡み合ひ、また、逆にそこから再びさくらへ反映させる。「この年頃になると、桜を見て、花に見られてゐる感が深い」と前年に書いたのが、さらに今度は生命力と 「独」との不可思議な結合へと導くこととなる。これがさくらの群生樹から独立樹へと、小林を向はせる切掛けとなつた。》(「桜と小林秀雄」) |
昭和39年に小林が弘前城に見た桜は「群生樹」であらう。弘前城にある弘前公園には80種2,500本を超える桜があるといふ。
(次号に続く)
(寺子屋モデル)
卒業式の国歌斉唱と朝日の記者
私が小学校4年生の時、担任の先生が「日本は、国際連合に81番目に立憲君主国日本として加盟しました」と喜びをこめて教へて下さった。今だに忘れられない。昭和31年のことであった。
40年近く前のことになるが、昭和55年3月1日の卒業式を前に、私が勤務してゐた直方高校で、式次第の「国歌斉唱」をめぐって、連日、職員会議が開かれた。今の学校現場では想像できない激しい論争だった。
私は「日本国憲法の第一章は天皇である。日本は国連には立憲共和国としてではなく、立憲君主国として加盟してゐる。だから国際的にも国歌は君が代を斉唱するのが正しいことなのだ」と主張した。当時は現在とは違って、全員の賛否が決め手であった(職員会議は校長の職務の円滑な執行に資するために校長が主宰するもので、本来的に多数決にはなじまない。しかし組合員が多数派の学校では組合の意向が校長の決定を左右してゐた)。私の発言が大勢の心を掴んだやうで斉唱することが多数決で決定された。だが、彼ら組合派教員が主張する多数決で決まったものを裏では秘かに潰す政治的な動きがあったやうだった。そこに朝日新聞の記者が絡んでゐた。
卒業式の前夜、職員室に残って式で呼びあげるクラスの生徒の名前を墨書してゐると電話が鳴った。私しかゐなかったので電話に出た。「明日の卒業式では国歌斉唱はやらないでせうね」と朝日の記者からであった。「いいえ、国歌斉唱はあることになってゐます」と答へると、「をかしいですね。筑豊地区では一校もやらないといふことになってゐる筈ですが…」とその記者が言ったのだ。学校の行事に対して何を言ふのかとむかっ腹が立ったが気を取り直して、「疑問があるのならば、学校まで来て取材して下さい。私が式の行はれる体育館に案内しませう。そこには明日の卒業式の式次第が大きく張り出してありますから、それを見て下さい」と言ふと電話はぷつんと切れた。仕事中の人間を電話口まで呼び出してゐながら一言の挨拶もなかった。彼らは「民主的に多数決で決めよ」と主張するが、否決されると暗躍する今も同じだ。
「立たんか!」の大喝一声
この時の卒業生のひとり、日比生哲也君(現在高校教員、本会会員)に後日聞いたのだが、「高教組が国歌斉唱では『立つな、歌ふな』といふビラを配布してゐたので、クラスの中で何人かが集まっては『どうしようか』と迷ってゐました」とのことだった。組合の教員は外部と一緒になって執拗に政治運動を展開してゐたのだ。一昨々年(平成27年)の合宿教室の班別研修の折、日比生君があの卒業式の思ひ出として、「国歌斉唱が始まったとき、後ろの方で『立たんか!』といふ大きな声が聞えた」といふことも話してくれた。
私はあの時、一心に国歌を歌ってゐたから、その声に気づかなかった。
思ひ出すと更に10年遡って大学4年生の夏(昭和44年)、合宿教室が終了した後、リーダー学生は残って事後合宿が行はれた。片付けが終り夜の反省会でのことであった。
当時多くの大学は、全共闘(全学共闘会議)を名乗る極左の三派全学連系によってバリケードを築かれ封鎖される異常事態だった。中でも全共闘によって支配された日本大学では、彼らの本部(アジト)に上がる階段にはびっしりと昭和天皇の御写真が貼り付けられてゐたといふのだ。
小田村寅二郎先生が実に耐へ難く悲しいお顔で「昭和天皇様を踏み絵のごとく使ってゐる。許し難い事がなされてゐる。学問の府で、本当に情けないことだ。心をこめて国歌が斉唱される時代は来るのだらうか」と憂ひ深く申されたあの夜のことがずっと心に焼き付いてゐたのである。国歌斉唱の際、先生のお言葉が思ひ出されてきて私は、「君が代は千代に八千代に…」と歌ひ出すと胸がじーんと熱くなり、思いっきり大きな声で歌ってゐたのだ。だから「立たんか!」の声は耳に入らなかった。
公教育に於いて儀式に臨む態度を養ふことは肝要なことである。国歌を歌はない自由があるなどといふ主張がまかり通れば、太古からの歴史が絶たれて彼らの狙ふ「立憲共和国」となって仕舞ふではないか。
一昨年(平成28年)も、皇居の勤労奉仕に上がらせて戴いた。かつて直方高校で一緒に勤めてゐた須堯(すぎょう)勇人先生夫婦と一緒であった。草取り作業を楽しく共に行ったが、小休止になった時、直方高校での国歌斉唱に話が及んだ。「日比生君は『立たんか!』の大喝一声があったから迷ってゐた何人かの生徒が電気に打たれたやうにパッと立ち上がったと言ってゐましたが、あれは誰の声だったのですか」と聞くと「実は私だったのです」と返事が返って来た。体育の先生の声なのかなと想像してゐたが意外にも生物の須堯先生だったとは…。皇居の勤労奉仕の際に分かったことで嬉しさ二倍だった。
「国民に寄り添はれる」伝統
一昨年(平成28年)8月8日御放送の「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」には多くをお教へ頂いたが、その中の「私が天皇の位についてから、ほぼ28年、この間(かん)私は、我が国における多くの喜びの時、また悲しみの時を、人々と共に過ごして来ました。私はこれまで天皇の務めとして、何よりもまず国民の安寧と幸せを祈ることを大切に考えて来ましたが、同時に事にあたっては、時として人々の傍らに立ち、その声に耳を傾け、思いに寄り添うことも大切なことと考えて来ました」(宮内庁ホームページから)との一節には、改めて心震へるものを感じた。
国民文化研究会の「聖徳太子研究會」(桑原曉一、高木尚一、葛西順夫、小田村寅二郞、夜久正雄、戸田義雄、梶村昇の諸先生ほか)による『聖徳太子佛典講説 勝鬘経義疏の現代語訳と研究(下巻)』(大明堂刊、平成元年)の中に、聖徳太子が政治の衝にお立ちになられるご姿勢について触れた箇所がある。梶村昇先生がお書きになってゐる。
「『乗の体』に対する太子のかうしたご理解は、誠に独創的であり『敦煌本』等にも見られないところであります。それと言ふのも、太子は、現実に政治の衝にお立ちになられ、日夜すべての人々の幸福に思ひを致してをられたわけでありますから、仏道を求めるに際しても、観念的理解ではなく、具体的事実として、それがすべての人々の救ひにつながるものでありたいと願つてをられた結果、万人の行ずることのできる善をもつて『乗の体』となされたものと思ひます」(正説 第5・1乗章20頁)註・「乗の体」…「乗」とは迷ひの衆生を悟りのかなたに運ぶ乗物のことで、「乗の体」とは「乗」の本質・本体のこと。
右の太子についての文書は、そのまま今上陛下について述べられたものとして読み直すとどうのやうになるであらうか。
今上陛下は、「現実に政治の衝にお立ちになられ、日夜すべての人々の幸福に思ひを致してをられ」る「わけでありますから」日本国憲法の第一章 天皇「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴である」を「観念的理解ではなく、具体的事実として、それがすべての人々の救ひにつながるものでありたいと願つてをられた結果…」といふやうに拝読できると思ふのである。これこそが悠久なる皇統の伝統と言ふべきであらう。
陛下のお言葉から、総理大臣や大臣らのどこかしら見てくれのものに感じられる言動とは遙かに次元を異にしたものを、政治家とは違って、一層深く切実なるご境地に立たれて政(まつりごと)をなされてゐることを我々は感じとってゐるのではあるまいか。被災して苦しみ悲しみの底に沈む人たちこそ、そのことを直感してゐるのではあるまいか。
よみがへる「夢のやうな感激」
さて、これまで5回、ありがたいことに皇居での勤労奉仕を体験することが出来た。平成27年の秋には国文研有志奉仕団の団長としてご会釈を賜る折に、両陛下から御下問を受ける光栄にも浴した。私は昭和47年に高校の教員になって以来、毎朝の御製拝誦と教育勅語奉読を欠かすことなく行って来た。平成に入ると神棚に両陛下のご真影を掲げさせて戴き、二拝二拍手一拝をする。私にとっては両陛下はこの上なく有難い神様なのである。
ご会釈の折のことを思ひ起すと、あの日の夢のごとき感激が現(うつつ)によみがへる。両陛下が歩一歩と私に近づいて来られる。四尺ぐらゐの距離だらうか、極めて近いところにお立ちになられた。私は心臓は強い方だと自負してゐたが、まったく違ってゐた。陛下の数歩後ろから皇后さまが、慎ましげに立たれた。
これまでに体験したことのない胸の高鳴りで、ものが言へる状態ではなくなってゐた。だが、団長として奉仕団の紹介をする責任があった。コチコチの固い姿勢で、「東京都、公益社団法人国民文化研究会20名、ご奉仕させて戴いてをります」と何とか申し上げることができた。先づ天皇陛下から「有り難う」とのひと言を頂戴した。ますます固くなってしまった。それまでは団員として後列でご会釈を賜ったが、この日は全く違った。皇后陛下からも「有り難う」とのおやさしいお声を戴いた。
私のこれまでの人生で最高の幸(さち)に浴した一瞬だった。ご多忙にあらせられる陛下は、勲章の授与を終へられた後に式服を召されたままで我々の奉仕団のところへお運びになられたのだった。思へば、さしたる奉仕が出来たわけでもない作業服のままの私たちにも等しく隔てなく労(ねぎら)ひ給ふたのである。最高の誉(ほま)れであった。
この譬へやうのない喜びの中で一国民として私は、報恩感謝の国民文化の精髄があると感得した次第であった。
(元福岡県立高等学校教諭)
生ひ立ち
明治37年2月、日露戦争が開戦した。当時、我が国は戦費を外債に頼るほかなく、「米国を味方にせよ」との命を受けて貴族院議員金子堅太郎が渡米した。親露的な米国世論を逆転させ、目標以上の資金調達を果した金子の背景には、各地で金子を支へ続けた高峰譲吉の存在があった。高峰譲吉とは、一体どんな人物だったのだらうか。
安政元年(1854)、ペリーが再び来航して、日米和親条約が結ばれたこの年、高峰譲吉は、加賀藩典医・高峰精一の長男として高岡(富山県高岡市)に生を享けた。両親は代々続く医家を継がせるべく、幼い頃から譲吉に教育を施し、9歳で藩校明倫堂へ入学後、12歳になると加賀藩選抜生として長崎へ留学した(選抜生は普通は14~15歳といふから、その秀才ぶりが伺はれる)。
父・精一は、医者として漢方医学や蘭学に限界を感じてをり、「これからは西洋医術と英語だ」と息子に繰り返し語り、譲吉少年も応へようと努力した。
化学への目覚め
明治に入り、父祖の医業を継ぐべく大阪の適塾を経て医学校に進学。しかし医学校の予備科目『舎密(せいみ)』(オランダ語の化学「Chemie」の音写)に興味を覚え、大阪舎密学校にも通ふやうになった。譲吉は「医学が救ふのは一人一人の患者だが、化学は万人を救ふ」との信念を抱き、工部大学校(東京大学工学部の前身)に進学。この六年制の学校で同期生と寄宿舎で寝食を共にしながら学んだ。
工部大学校では、平生の言動や習癖からお互ひに渾名(あだな)で呼び合ってゐたが、譲吉は学力と人徳がぬきんでてゐたらしく、「高峰君」と敬意を込めて名前で呼ばれたといふ。
工部大学校を首席で卒業した譲吉は、明治政府の目指す「お雇ひ外国人に頼らない、日本人教師の育成・確保」のため、3年間の英国留学生11人の一人に選抜された。この頃、内務卿大久保利通を暗殺した者が加賀藩関係者だった(紀尾井坂の変)ため、政府内からは「(加賀藩出身の)高峰を留学候補生から外せ」との指示も出たやうだが、工部大輔山尾庸三や、工部大学校長大鳥圭介の強い推薦を得て英国留学が実現した。
米国との機縁
3年の留学を経て帰国した28歳の譲吉は、農商務省御用係となり、農業や商工業を興すために必要と思はれることなら何でも自由に研究していいといふポストを得た。「願はくば習得した技術を日本固有の工業に応用したい…」と考へた譲吉が力を入れたのは、国産人造肥料の開発であった。当時の肥料は糞尿や堆肥が中心で、人造肥料の干(ほし)鰯(か)や鰊粕(にしんかす)は原料の高騰で農家を圧迫してゐた。明治初期の政財界には農村出身者も多く、「国の根幹は農業」といふ意識が強かったため、譲吉の「価格の安定した肥料が出来れば収穫高も上がり、農民が潤ふ」との説得に賛同する者も多かった。特に、渋沢栄一は、譲吉を「科学者」としての側面のみならず、「事業を処理する才にも通ずるなり」と評してゐる。
明治17年に、事務官として米国ニューオリンズ万博に派遣された際は、休暇を利用して南部に向ひ、肥料の原料となる燐鉱石を自費で10トン購入して日本へ送った。これを元にして、渋沢など政財界の重鎮から出資を受け、明治19年、東京人造肥料会社を立ち上げた。この会社は6年後には配当を出せる企業にまで成長した。
譲吉はニューオリンズ万博に派遣された際、南部のヒッチ家令嬢・キャロラインと婚約をしてゐる。日本館を訪ねた母・メアリーに、「茶の湯」の歴史と心について講じたことからヒッチ家の晩餐会に招待されたのが縁である。3年後、再び渡米した譲吉は正式に結婚をした。ヒッチ氏は、南北戦争で南軍の大尉を務めた名士である。米国南部では、白人と黒人の混血も珍しくなかったため、東洋の青年との結婚も大いに祝福されたといふ。
結婚後、夫婦は東京本所の肥料工場脇の小さな家に住み、ここで二人の男の子に恵まれてゐる。
「日本の米麹で洋酒を造らう」
将来を約束された農商務省の役人をあっさりと辞めた譲吉は、人造肥料会社の経営を進める傍ら、アルコール発酵についての研究を続けた。やがて、日本酒の製造方法を応用して米国でウイスキーを造らうと考へて、船便でも腐らせずに運搬可能な元麹を開発し、「高峰式元麹改良法」の特許を得た。この方法なら、それまで廃棄物同然だった麦皮(フスマ)からでも短期間でウイスキーを造れる。さう勇み立ったが、販路を得るのは容易ではなかった。譲吉も後に、「異境の米国においてもとより知己は少なく資力もまた乏しく…日本人の発明などに対してだれが耳を傾けようか…」と当時を回想してゐる。このとき、全米の9割以上のウイスキーを生産してゐるウイスキートラスト社と渡りをつけたのが、義母のメアリーだった。かうして明治23年、譲吉一家は米国に渡ることになった。
しかし、先に立ち上げた人造肥料会社の処遇が問題となる。出資者の一人渋沢栄一は、「高峰なくして会社は成り立たず」と、再三渡米撤回を要請したが、「日本人の発明を米国の会社が実用化しようといふ話はこれまで耳にしたことが無い。ここは高峰に花を持たせよう」とする他の出資者の意見に押されたといふ。 現在では様々な日本の技術が世界で応用されてゐるが、譲吉はその先駆的存在だったと言へる。
原料の栽培から数ふれば約半年の行程を要してゐたウイスキー造りが、わづか24時間で、しかも麦皮から出来るといふことで、利益は莫大なものとなった。しかし、高峰式が広まると、モルト職人や他の工場主は生活を脅かされた。つひには工場が放火され、一夜で全てが灰になった。その後、別工場も建てられたが、今度はウイスキートラスト社が解散した。トラスト社に独占的な特許使用を認めてゐた高峰は途方に暮れ、事業は行き詰まった。またこの頃、譲吉は肝臓を病み、死の淵をさまよったが、シカゴに移って手術を受け、奇跡的に回復した。妻カロラインは、内職までして生計を支へたといふ。
この頃から、麹の分解作用を消化薬に応用出来ないかと考へるやうになり、明治27年、それまで存在していたジアスターゼをより強力にした「タカジアスターゼ」を発見、特許を得た。「タカ」とは、ギリシャ語で「最高・優秀」を意味すると同時に、高峰譲吉の「タカ」をも掛けてゐる。タカジアスターゼは、デトロイトの製薬会社パークデイビス社から全世界に売り出され、爆発的にヒットをした。この業績により、譲吉は後に日本政府から工学博士号を授与されてゐる。まさに、どん底からの大逆転と言へる。
アドレナリンの結晶化成功
パークデイビス社とコンサルティング契約を結んだ譲吉は、拠点をシカゴからニューヨークの小さな研究室に移した。
当時(19世紀後半)は、世界各地で戦争が勃発し、戦傷による出血性ショックで多くの若者が命を落してゐた。世界の製薬業界は、血圧上昇・強心・止血の作用を持つといふ副腎エキスを純粋な結晶として生成すべくしのぎを削ってをり、パークデイビス社も、譲吉に研究を依頼した。譲吉は、日本から上中敬三(うえなかけいぞう)を助手として招いて研究を進めた結果、明治33年7月21日、高峰研究室で、アドレナリンの結晶化に初めて成功し、世界に「タカミネ」の名が知れ渡った。
譲吉は、後年かう述べてゐる。
「同じ発明をするにも、それはひいて日本の国益になることを忘れてはいけない。日本を名実ともに一等国にするためには、国産品をより優秀にせねばならぬ」
この言葉が示すやうに、パークデイビス社とのタカジアスターゼやアドレナリンの日本国内での生産・販売は、日本の企業(後の三共製薬)が携はることを認めさせてゐる。米国に居ても、常に「日本の国益」を考へるその姿勢は、後に譲吉が日米親善の「無官大使」と呼ばれた働きからも理解できる。
いま、再び日露戦争の前夜!?
我が国が近代化と独立自尊のために苦闘していた明治時代、譲吉は単身米国に乗り込んで成功を収めた。しかしそれは、自己の「栄誉」にとどまらず、常に意識は国家と共にあったと考へられる。冒頭記した金子堅太郎との関り以外にも、私費を投じて有名新聞社の一面を買ひ取って、当時既に世界的な学者だった北里柴三郎博士を紹介しながら「日本は模倣だけの国では無い」と自ら筆を執って訴へた。また、自ら主催するパーティーには必ず紋付き袴で登場し、妻・キャロラインも着物姿で接待させたといふ。
「余の社交の目的は、私利私欲を謀るに非ずして、日米の国交を親かつ密ならしめんとするにあり。これ余の使命である」
ともすれば誤解が誤解を呼ぶやうな国際社会、当時まだまだ東洋の未開国と見なされてゐた時代にあって、正しい日本の姿を積極的かつ正確にアピールし、米国国内に親日家を増やした。譲吉が中心となって結成した「日本クラブ」(親日アメリカ人との交流)や、「日本協会」(在米日本人の会)は現在も活動し、日米友好を促進してゐる。
現在、わが国は中韓両国が世界に広げた「悪逆非道なる日本」といふ悪意に満ちた反日プロパガンダの逆風を受けてゐる。中韓を非難しても始まらない。何よりも大事なことは日本人自身が自国の正しい姿を世界に発信しようとする強い意欲を持つことだ。挫折にもめげず、常に「日本人科学者・高峰譲吉」として生きたその気概こそ、私たちは学ぶべきであらう。(『寺子屋だより』17号所載の旧稿を改編し加筆した)
(荘島慈恩塾)
をとめの胸鉏(むなすき)取らして大魚(おほうを)のきだ衝き別けて、はたすすきほふりわけて、三身(みつみ)の綱うちかけて、霜つゞらくるやくるやに、河船のもそろもそろに、国来々々(くにこ)と引き来縫へる国は、去豆(こつ)の打絶えより、やほに杵築(きづき)の御(み)埼(さき)なり。
(出雲国風土記)
あまりにも国が小さく作られてゐるのをなげいてゐた出雲国の祖神、八束(やつか)水臣津野命(みづおみつののみこと)は、はるか海原のかなた、新羅の国を見さけて、余れる国なきやと望みたまひしところ、果して「国の余り」があった。そこで命はすぐさまに童女(をとめ)の胸の如く広く平らかなる鋤をとって、丁度魚を取る時に鰓(えら)に鉾(ほこ)をつきさすやうに、がっしりと鋤を突きさして土地を切り離し、それに三本の綱を縒り合せた逞しい綱をかけて出雲の国の方へとたぐりよせるのである。だがその手応へはあまりにも重く、あたかも河船の進まむとして進まざるがごとくである。
太古の空間はまことにのびやかに、神々の世界は底ぬけに明るい。その蒼々(あをあを)と澄み切った海原の彼方から「国の余り」は河船のもそろもそろに近づいてくるのだ。かくて引いてきた国を神々は出雲の国土に縫ひつけた。それが去(こ)豆浜(づがはま)から現在の日御埼(ひのみさき)(出雲大社西北)に至る一帯だといふのである。
発想はまことに奇抜であり表現もユーモラスだが、そのユーモアを支へる汪洋(おう よう)たる精神の拡がりはすばらしい。古代の神々の「国来々々(くにこ)」といふかけごゑの中にはまさに宇宙に遍満する大らかな呼吸がある。ぼくはこの国引きの神話を読むたびに、いはば日本民族の呼吸といふやうなものを思はずにはゐられないのである。ぼくらが日本の民族として生きることは、この古代の呼吸を自らのものとして生きることではないか。
われわれ日本人は外来の文化をめまぐるしいテンポで摂取しつくすといふ異常な才能をめぐまれてゐると言はれてきた、だが文化といふものは本質的に一つの「持続」である以上、かゝるテンポの早さといふものには、実はそれほどの意味はないのだ。ぼくらにとってかけがへもなく大切なものは、かかる一時の華やかな才能ではない。それはもっと根深い、この風土記の言葉が示すやうな、悠揚として迫らぬゆるやかなテンポでなければならない。即ち日本人はその未来を「霜つゞらくるやくるやに、河船のもそろもそろに、国来々々」とたぐりよせる以外にはないのだ。そこに日本民族の本質的な姿がある。この呼吸を失ったときに、われわれは近代といふ激流の中に苦しい喘(あへ)ぎをつゞけながら、つひに日本といふ国の姿を見失ふに至るのである。
(初出『国民同胞』昭和38年8月号)
編集後記
本号7頁の“小柳陽太郎先生の「古典の窓」”は半世紀以上前のものだが、この間のわが国の歩みを正に予見してをられた。最後の段落の「われわれ日本人は外来の文化をめまぐるしいテンポで摂取しつくすといふ異常な才能をめぐまれてゐると言はれてきた、だが文化といふものは本質的に一つの『持続』である以上、かゝるテンポの早さといふものには、実はそれほどの意味はないのだ。ぼくらにとってかけがへもなく大切なものは、かかる一時の華やかな才能ではない」との一節には慄然とさせられる。そして「つひに日本といふ国の姿を見失ふに至るのである」との警句にも。今後も、折々に「古典の窓」を再掲したい。ご精読を。
御譲位のこと、憲法改正のこと、国家の重大事を前に、先づは太古からの変らぬ国柄に思ひを致したい。それにしても、朝日を先頭とする大メディアの内通的亡国的な世界的にも稀な堕落は何時まで続くのか。今年もお力添へを下さい。
平成30年元旦 山内健生