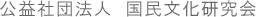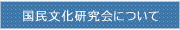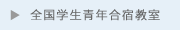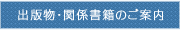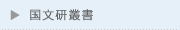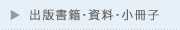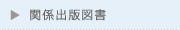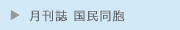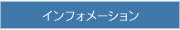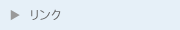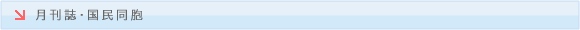
第666号
| 執筆者 | 題名 |
| 池松 伸典 | 「歌を味はふ」といふこと - それは、まごころを感じ取る力を養ふ - |
| 庭本 秀一郎 | 故・プミポン国王陛下とタイ国民の絆(上) - 弔意を示しながらも、仕事は普段通りに - |
| 中村 正和 | 武士道と禅 - 「武士道」を生成して来たわが国の歩み - |
| 古川 修 | 西元寺紘毅先輩を偲びて |
| 学生代表・九大・法4 西元寺紘毅 |
国民文化研究会10周年の集ひ 祖国を護る心情をよび起さう |
| 新刊紹介 |
合宿教室は今夏で62回を数へるが、その際の参加必携書『短歌のすすめ』に、脇山良雄先生がお詠みになった連作11首が載ってゐる。昭和38年4月、長崎県大村湾の近くで行はれた「長崎大学信和会」の合宿にオブザーバーとして参加された時に詠まれたものである。当時、脇山先生は55歳であった。先生は長崎県立長崎中学校から五高、京大と進まれ、長崎市内で書店を経営されてゐた。
私は大村湾に近い諫早市の出身で、昭和38年と言へばまだ小学校の二年生だった。ずっと後、大学を卒業して長崎に戻った折、お亡くなりになる前の一年半ほどの間、勉強会でご一緒させて頂いた。
この度、先生の連作を改めて拝読して心が洗はれる感じがした。次はその中の三首である
底ひまで澄める潮(うしほ)にかこまれて秋(あき)津島根(つしまね)の清らなるかな
さざ波の打ちよするごと春風の吹きよするごと若き魂(たま)よる
騒がしき世をはなれ来て春の海澄める底ひの石(いは)を見つむる
大村湾は佐世保湾と一部が繋がってゐてその他は陸が取り囲んでゐる波穏やかな海である。繰り返すさざ波の心地よい音と海底の石が見て取れる澄んだ海を見つめながら、その情景とこの合宿に参加してゐる学生達の心の清らかさとが重なり合って詠まれてゐて、心が洗はれ清められていくやうな感じがするのである。
この合宿に同じく参加されてゐた小田村寅二郎先生(国文研初代理事長)が、この連作短歌について次のやうに学生宛の書簡に書かれてゐる。
「脇山さんは、こんな歌がいつでもおできになる方かどうかは私は存じません。…(素晴らしい歌を詠むために)もし経験の差(がある)というならば、〝私のことは忘れて、国を思うこと、世を思うこと、人のことを思うこと〟について〝ちぢに─大変こまやかに─心をくだいてきた経験〟とこそいうべきでしょう」(カッコ内は補記)
小田村先生と脇山先生のご交流がどのやうなものであったかは私には分らない。ここでは経歴などの知識は無用で、小田村先生はこの短歌の三十一文字を通して一瞬の裡に人のまごころを感じ取ってをられることに深く教へられたのである。ともすると我々は歌の内容を味はふ前に、その人についての種々の情報を得ようとし、その情報量が多いほどその人に近づけると思ひがちである。
確かに情報は必要かもしれないが、あくまで言葉を通じて相手の心に触れていかうとする姿勢があって、初めてその情報は生きてくるものだと思ふ。情報過多の現代においては様々な知識を容易に得ることができるが、その代償として、言葉に触れて人の心を直に感じとる能力が衰へてきてゐるやうに思はれてならない。
小田村先生はさらに「脇山氏のうたのすばらしさに同感されても、それは経験がある方だから、といって自己との比較は遠ざけてしまわれ勝ちと思います。私は、それはいけないことだ、とここで注意しておきたいのです」とも書かれてゐる。
今の私は脇山先生のご年齢を過ぎたが、とても上記のやうな歌は詠めない。「ちぢに心を砕くこと」を疎(おろそ)かにしてきたからであらうし、日々の仕事にかまけて自分を見つめ直し人のことを思ひやることから遠ざかってゐたためでもあらう。先生は常日頃から手帳に和歌を認(したた)め、「技巧を凝らしたりせず、ただ自分の日記代わりの心の記録として歌を詠んだのである」と親族の方が先生の遺歌集『楠若葉』に書いてをられる。
最近、短歌はテレビなどでもよく取り上げられるが、奇を衒(てら)ふ感じのものが多い。さういふ歌もあるだらうが、万葉の時代から詠まれてきた短歌といふ表現方法は単なる文学的なものといふよりは、本質的には「ちぢに心を働かせる」ことで人のまごころを確かめつつ生きていくためのものだったやうに思ふのである。
防人から天皇の御歌まで貧富性別に関係なくあらゆる階層の人達が歌を詠んできた。さうした歌を味はふだけで万葉人の心根を蘇らせることができる。「感動」は時間とともに薄れて単なる記憶になりやすいものだが、この感動を正確に詠む努力を続けることで、人のまごころを感じ取る力も身につくのではないかと思ふのである。
(若築建設(株)東京支店)
国王陛下崩御 ―その前後のこと―
昨平成28年(仏暦2559年)10月13日、タイのプミポン・アドゥンヤデート国王陛下が崩御された―注・仏暦…タイでは釈迦入滅の翌年を元年とする。キリスト暦〈西暦〉に543を加へる― 。
プミポン国王は御在位70年、立憲君主制の下、国民の絶大な敬愛を集め、数々の政治的混乱をも収拾され、タイ国の政治的安定の要でもあられた。
陛下の御容態がいよいよお悪いとの情報が入ったのは前日の12日だった。王族方がご入院先の病院に入られ、ご快癒を願ふことを示すピンク色のシャツを着た多くの国民が病院の前で祈ってゐる姿が報道された。
13日の夕方、残業をしてゐた7~8名の社員の間からすすり泣く声が聞え始めた。帰宅途上の総務課長からは、18時50分に〝Thailand,s King Bhumibol Adulyadej passed away today.〟との短いLINEメッセージが入り、19時から政府の公式発表のテレビ放送があった。
「いつかは訪れるであらうその日」についてタイ人社員には聞くことは憚られた(プミポン前国王陛下にとっては不本意なことであったさうだが、タイには不敬罪がある)。他方、日本人社会の中では、まことに不謹慎ながら、密かに「その日」に何が起るか、その備へはどうすべきかといった会話が続けられてきてゐた。社会インフラが止まるのではないか、クーデターがまた起るのではないかなど、色々なことが議論されてゐた。全てのタイ人社員が帰宅した後、駐在員で協議した。タイ人社員が出社しない、公共交通機関が止まるといった可能性を想定し、翌朝の動き方を確認した。
「弔問のための休暇は申請不要」
混乱もなく一夜が明けた。政府機関は一日だけ休みとなったが、公共交通機関は止まることなく、金融市場は開き、13日に一旦下げた株価は反発、為替の混乱もなかった。社員も皆出社して来た。プラユット首相から、服喪が経済活動に与へる影響を極力回避するやうにとの指示が出たことも背景にあったと思ふ。
上司であるタイ現地法人の社長が日本帰国中であったため、本事態への対応については私に一任された。
14日の朝一番に管理職会議を招集したところ、タイ人管理職の面々は泣きはらしたやうな赤い目をしてゐた。その状況を見て、日泰管理職全員の同意のもと、「今後(弔問、服喪など)国王陛下のために時間を使ひたい人は自由に休暇を取っても良い(有給休暇の申請不要)」といふことにして、その旨を全社員を会議室に集めて伝達した。
いつも笑顔を絶やさないタイ人社員の顔からは普段の微笑みが消え、泣いてゐる社員が多くゐた。会議室には私の想像をはるかに超えた悲しみの気が満ち満ちてをり、圧倒されさうだった。
私は今の自分の思ひを彼らに伝へなければと思った。私は社員の前で、(本当はタイ語で話したかったが、その力はなく)拙い英語で次のやうなことを話した。
タイ人社員を前に私は語った
「今皆さんの感じてゐる悲しみの深さが如何ばかりのものかと、私は思ひを巡らせてゐます。私は、今、昭和天皇が崩御された時の少年のころのことを思ひ出してゐます。正直なところ、その時はただならぬ方が亡くなられるといふただならぬ事が起ったのだといふことは分りましたが、その意味はあまりよく分りませんでした。
その後、年を重ね自分なりに皇室のことや歴史を学び、皇室が日本にとってとても大切な存在であることを遅ればせながら知りました。また、私なりに及ばずながらもタイの歴史やプミポン国王陛下のご事績も学びました。だから同じロイヤルファミリーを戴く国の民として、皆さんの今の思ひを少しなりとも理解できると思ってゐます。
私は忘れません、私の故郷が地震で被災した時、タイの人たちが熊本に義捐金を送ってくれたことを。私の故郷が熊本であることを知ってゐて温かい声をかけてくれた人もこの中にゐます。東日本大震災の時もタイの人たちは日本を助けてくれたと聞きます。私自身も皆さんと仕事をする中で多くの方々の優しさに触れ、助けられてきました。さういった皆さんの優しさは、陛下のお人柄を尊敬しそれに倣はうとする中で皆さんの中に育まれてきたものでもあると信じます」
彼らの表情を見てゐて、私の言ったことは伝はったのかどうかよく分らなかった。「外国人のあなたに、今の気持ちが分るか?」といったやうな空気も感じた。言語力の問題もあったと思ふ。社員の気持ちを少しでも分って寄り添ひたいといふ思ひだったが、彼らの悲しみはずっと遠く深いところにあるやうな感じがして、一人取り残されたやうに思った。
そんな私にも、「ありがたうございます」と感謝の言葉をかけてくれる部下もゐて、逆に救はれる思ひだった。思ひ返せば、それは、彼らの悲しみに近づかうとして近づけないでゐる私への気遣ひだったかもしれないと思ふ。
果して、全タイ人社員48名中7名から、午後に休みを取りたいとの申し出があった。14日には国王陛下のご遺体が病院から王宮に移され、病院から王宮に至る道沿ひには多くの人々がそれを見送るために詰めかけてをり、そこに連なりたいといふ社員達が休みを申し出たのだった。午後になると、インターネットテレビでその模様が中継され、社員が見始めたので会議室にプロジェクターを設置して全員が見られるやうにした。彼らは時々仕事の手を休めてはその模様を見に、三々五々会議室に出たり入ったりしてゐた。
前述の「陛下のための休みは自由」といふわが社の対応を、近い関係にあった取引先にも参考情報として伝へた。「そんなことで労務管理ができるのか?休みを取ってずっと出勤しない者が出てくるのではないか、その時はどうするのか」と驚かれたが、「うちの社員は、そんなことはしませんから大丈夫です」と答へた。私には寸分の迷ひもなかった。
結局その日以降は、社員から「国王陛下のための休暇申し出」は一切なかった。弔問は土日に行けるから問題ないとのことだった。
バンコクの街は黒一色に
バンコクの街は黒一色に染まった。国民は思ひ思ひに黒あるいは白黒の服を装ひ、祭壇や記帳所はオフィスビル、デパート、ホテルなど到る所に設けられた。洋品店には黒い服が一斉に陳列され、テレビの画像、ウェブサイト、銀行ATMの画面、雑誌の表紙などがモノクロまたはダークトーンに変った。黒い服が買へない貧しい人のために喪章を作成するボランティア活動も生まれた。タイの国民は、このやうに静かに陛下を思ひ、弔意を示しながらも、仕事や日常生活は極力普段通りにしようとしてゐるやうだった。タイの国民は、前国王陛下ご自身が、自身のための服喪により国の経済活動が停滞することを好まれないであらうとの思ひのもとに行動してゐるやうに見受けられて、情や調和、合理性を重んじるタイの国民らしい成熟した姿だと感じた。
心ある日本人駐在員の仲間が、「その日」のための備へを議論してゐた自分たちのことを恥かしく思ふと話してくれて、同じ思ひだった。
プミポン前国王陛下の御事績 ―ロイヤルプロジェクト―
プミポン前国王陛下は、国民に父と呼ばれ慕はれてきた。その理由には、お人柄も然ることながら、ロイヤルプロジェクトと呼ばれる開発プロジェクトがある。
陛下ご自身が行はれたものの他に、ご発案のものも含めると、その数は、非営利、半営利含めて4,449件にもなる。
水資源および灌漑開発事業(農業用水や生活用水の不足に直面する地域があれば、洪水被害を受ける地域もあり、苦しむ国民のために水資源の確保や灌漑などのためのプロジェクト)、土地改良と開発に関する事業(痩せ細った土地を肥沃な土壌に改良し、共同組合を組織して、土地を農民に分配するためのプロジェクト)、医療及び衛生に関する事業(陛下の派遣された巡回医師、陛下の立案による特別医療プロジェクト、陛下による巡回歯科診療機関設立)、教育に関する事業(学校建設をはじめ、教育費が不足して学業に就けない優秀な児童を支援するための奨学金制度、海外留学のための基金創設)、農業事業(北部開発事業、人工雨事業、米銀行事業、水牛銀行事業、農業休閑期の農民のための特別職業支援事業、協同組合事業など)と多岐にわたってゐる。
昭和27年から昭和52年までの最初の100件の国王陛下発案プロジェクトのうち、北部の貧しい地域を対象にしたものが85件を超えてゐる。
当時はまともな道路もなく、熟練運転手による四輪駆動でも進めないやうな山道を陛下専用のジープで赴かれ、途中で車を降りて暑い中を汗だくになりながら何時間も歩かれこともあった。普通の人であれば、くたくたになるところだらうが、国民と共においでになときの陛下は、常に楽しさうにされてゐたといふ。「助ける活動をするには、助けられる側の人間をよく知っておかなければならない」とお考へになっての御行動であった。
(次号に続く)
(東洋紡タイランド(株))
1、武士道とは
戦後、武士道は占領政策もあって軍国主義と同一視された面があったが、武士道は軍国主義でもなければ、殺人剣でもない。むしろまったく逆に、わが国の武士道は、己を殺して人を生かす活人剣であり、抜かずして天下を治める不抜の剣であった。
また、武士道は、武士階級特有の道徳として限定的に捉へがちであるが、しかし、武士道は、神代の昔から現代に至るまで脈々と受け継がれてきた和平実現への道である。武士道は、世界に誇り得る日本人の精神性を示すものであり、今日においても尚、大いなる価値を有するものである。
わが国は、尚武の国である。そもそものはじめに、「天沼矛(あめのぬぼこ)」によってわが国はつくられた。「武」とは、本来、「戈(ほこ)(戦ひ)を止(とど)める」ことであり、神々はこの聖なる戈(ほこ)によって地上に和平を実現することをめざされた。また、天照大御神が皇孫に「八尺(やさか)の勾璁(まがたま)」「鏡」とともに託された「草薙剣(くさなぎつるぎ)」こそ、わが国に平安をもたらすための神器であった。
そして、わが皇祖皇宗の悲願は、三種の神器の「鏡」に象徴される「しろしめす」にあった。それは覇権による支配を意味する古語「うしはく」とは明確に区別された。「しろしめす(しらす)」とは天皇(すめらみこと)が鏡の如き無私なる心で国民の苦しみと喜びを知り、「国安かれ、民安かれ」と祈る有り難き祭祀(まつりごと)であった。
天孫降臨に際して、邇邇芸命(ににぎのみこと)に仕へた武人たち、あるいは神武天皇を守護し先導した「もののふ」たちは、天照大御神の「託宣」と「わが国の道」を深く遵奉(じゆんぽう)して臣従した。かうして、わが国は、聖なる剣の威力によって生まれ、剣の武徳によって鎮められたのである。それが皇祖神(みおやのかみ)の始め給ひたる「随神(かんながら)の道」であった。
天孫降臨に臣従した天児屋根命(あめのこやねのみこと)の子孫大伴家持が
大君の辺(へ)にこそ死なめかへり見はせじ(万葉集)
と歌ったのも、わが国上古(じようこ)の武士道が和平実現への皇室の悲願を奉じて、身を捨てて、誠を尽すことにあったことを物語ってゐる。これがわが国の道としての武士道である。以後、わが国の武士道は神・儒・仏三道の影響を受けながら、やがて日本人の道となって行った。
戦場で刃を交へる武士は敵を殺さなければならない。しかし、武士に限らず、誰もが他の動植物の命を頂かなければ(奪はなければ)、一日として生きのびることなどできないのである。わが国の武士道は、この生の冷厳なる事実と人間の宿業の深さを知るが故に、「いのち」をいつくしみ、正しく生きることを教へて来た。己の心身を正し、命を賭けて愛する者とわが祖国を守り、この世に平安を実現することを使命としてきたのである。これがわが国の武士道である。
そして、やがてわが先人たちは「禅」と出遭って、さらに気づいたのである。殺し合ふ阿修羅の世界を克服するためには、相手を殺すのではなく、自己自身の在り方を見つめ直し、己を殺して仁をなす以外に方法はない、と。ここでわが国の武士道は、殺伐たる殺人剣を活人剣へと転換したのである。それは、己を捨てることによってはじめて獲得できる人間本来の「いのち」への絶対的肯定、他者との敵対を超える安心立命の境涯であった。
2、死と自我の超克
武士道は死を前提とした哲学である。自我を超克するための思想と言ってもよい。「武士道といふは、死ぬ事と見付けたり」、この一節で有名な『葉隠』には生死を克服する道が説かれてゐる。そして、その思想には、ただただ勇猛の一気で死に身なって「此糞袋(このくそふくろ)(身体)を何とも思はず打ち捨てる」鈴木正三(しようさん)の仁王(におう)禅(ぜん)(煩悩に打ち克つ禅の修行には、悪魔を調伏(ちょうぶく)するべく憤怒の形相で寺院の門前に立つ仁王の気迫が不可欠だとする)の影響が指摘されてゐる。
しかし、生死への不安は、何も武士に限ったことではない。実は、死は誰にでも必ず訪れる。その不条理をパスカルは「人間は生まれながらにして死刑囚である」と表現した。「死」は、「自我」につきまとふ最も根源的な不安と恐れなのである。むしろ、問題は、死を恐れて不安に苛(さいな)まれる「自我」の意識の方にある。
西洋は、近代以後、この死と自我の問題で行き詰まり、出口を見失った。この西洋に学んで「近代的自我の確立」を唱へた明治以降、特に「自我の尊重」を何より優先した戦後の日本人も、この肥大化する自我の問題で病んでゐる。だが禅は、端的に「己を殺せ」と教へる。
禅で己を鍛へた西郷隆盛も「おのれを愛するは、善からぬことの第一なり」と、自我を増長させる現代教育とは真逆のことを教へてゐる。おのれを愛する我執ほど根深く断ち切り 難い欲望はない。何事においても「自分が」「自分が」と我を主張し、寝ても覚めても自己中心的にはたらき続ける浅ましい心の動きが自我意識である。
本を読んでも、勉強をしても、どんな立派な修行をしても、禅定力を養っても、それが自分のためでしかなかったならば、それは増上慢に堕し畜生道に落るしかない。どんなに剣術を磨いても自分のための練磨であれば、それは殺人剣に他ならない。
従って、至道(しどう)無難(ぶなん)禅師(江戸時代初期の臨済僧)は、『即心記』の中で「身をなくするなり。身に八万四千の悪あり、身なければ大安楽なり。直に神なり、直に天なり」と、徹底して自我を殺し、「身をなくす」ことを説き、次のやうに歌ってゐる。
ころせころせわが身をころせころしはてて何もなき時人の師となれ
いきながら死人となりてなりはてておもひのままにするわざぞよき
人間は、一度死に切り、己を殺さなければならない。宮本武蔵は、身をなくし、覚悟が定まったその心の在り方を「岩尾の身」と呼んだ。
ある時、熊本二代藩主細川光尚が「岩尾の身とは何か」と武蔵に問うた。さればと武蔵は弟子の寺尾求(もと)馬助(めの すけ)をその場に召し出し、「その方、只今切腹の沙汰が下されたゆゑに、速やかにお受けせよ」と命じた。
求馬助は即座にただ「はっ」と平伏し、顔色一つ変へずに切腹の準備に取り掛かった。その求馬助の後姿(うしろすがた)を見て、武蔵は「これが岩尾の身でござります」と藩主に答へたといふ。それは、常に死を覚悟し、いつでも「捨て身」で物事に処すが故に、何事にも動じない絶対主体となった巌の如き心である。
3、己事(こじ)の究明
自我の問題、すなはち「己事の究明」に真正面から取り組んだ禅僧がゐた。鎌倉末期に生まれ、南北朝時代の乱世に生きた抜隊(ばつすい)得勝(とくしよう)禅師(1327~87)である。彼は「聞く主、これ何ぞ」「見る主、これ何ぞ」といふ大疑団を一貫し、ついに生死の一大事を明らめた。
抜隊禅師は大疑の末にこの問題が「自心を悟る」ことであると喝破した。抜隊禅師は「自心と云ふは、父母もいまだ生まれず、我が身もいまだなかりしさきよりして、今に至るまで移りかはることなくして、一切衆生の本性なるゆゑに、是を本来の面目と云へり」といふ。
これは一体どういうことか。私は最近、生徒たちからつくづく気づかされたことがある。生徒も教師もおなじ「いのち」を生きてゐるが、教師よりはるかに優れた「魂」をもった生徒たちがゐる。大変な恵まれない境遇の中で生きてゐる生徒たちから、教師である私が教へられる毎日である。
沢庵和尚の『不動智神妙録』に「ずつと高きは、ずつと低きと同じものに成り申し候」とある。低き迷ひの中にある自我とずっと高きにある本来的自己は、実は別物ではなく、不二である。本当は、どんな人も同じく尊き「いのち」なのである。「一切衆生悉有仏性」で、そもそも父母未生以前の「真実の自己」は、生ずることも滅することもなく最初からあり続けてゐる。
人はまた、どんなに辛く苦しくても、この己の命を「いま」「ここ」で生きるしかない。即今目前の「いま」「ここ」こそ、本当は浄土である。八万四千の悪あるこの身がそのまま真実の自己だからである。これが西田幾多郎の「絶対矛盾的自己同一」である。だから、白隠禅師は「當處即ち蓮華国 此の身即ち佛なり」と謳った。それが「自心を悟る」ことである。
そして、我が国の武士道は、そこからさらに、敵と自分も不二であるといふ無敵の境地に到る。己を捨て、自己の仏性に気づき、他者の仏性へと思ひ至る時、自と他の対立は消え、あらゆる敵対は慈愛によって融和する。それこそが、柳生宗矩(むねのり)の西江(せい ごう)水(すい)、針谷夕雲の無住心、山岡鐵舟の無刀流、直心影流の丸橋(まろはし)など、もはや敵のゐない天地自然と一体になった自由無碍(む げ)の境地である。
4、「西江水」と「放つ位」
己の「いのち」を如何に掴み取り、人生の中でその「本来の自己」をどうすれば実現できるのか。禅はその鍛錬法についても教へてゐる。
剣禅一如の極意に柳生宗矩の「西江水」がある。それは、唐の馬祖(ばそ)道一(どういつ)禅師が「汝が西江の水を一口に吸尽し来る時、汝に向って道(い)はん」と言った時、道を求める修行者が言下に悟った故事に由来する。
大森曹玄老師(臨済宗の禅僧。直心影流剣術の使ひ手で、花園大学学長も務め平成六年歿)の『剣と禅』によれば、この西江水は丹田呼吸法の極意である。西の海の限りなき水(西江水)を一口に飲み尽し、「腹」を「たんぶ」(気張りを抜いてゆったり)と水に入った心持で、「背中」、特に腹の裏と背中の中筋、そして全身に活気を充実させ、心・身・刀を一つにする柳生新陰流の「無形の位」が「西江水」である。
柳生宗矩は「何事も去つたる所、是西江水也」と言ふ。宗矩の父石舟斎宗(むね)厳(よし)は「当流に構(かま)へる太刀を皆、殺人刀と云ふ。(略)又構へる太刀を残らず裁断して除(の)け、無き所を用ゆるに付き、其の生ずるにより活人剣と云ふ」と述べてゐる。すなはち、構へを残らず裁断し、習ひをすべて打ち捨てた「独脱無依の妙用」が「無形の位」である。この何ものにも依存せず、「何事も去つたる所」から本源的な命のはたらきである活人剣が生ずるといふのである。
大森老師は、この西江水が「りきみもなく、ぬけた所もない」全身心の充実であるからこそ、次の「放つ位」に到り得るのだと説く。老師は、この「放つ位」を尾州第二代徳川光友の左記の歌、
張れや張れただゆるみなきあづさ弓放つ矢さきは知らぬなりけり
を取りあげて、精進・充実・超絶の三段階の最後の悟りの境地として解説してゐる。それは坐禅の呼吸法にも通じるものがある。
第一が「張れや張れ」で張り切った勤勉・努力・精進の段階。第二が「ただゆるみなきあづさ弓」で誠心によって充ち満ちた充実の段階。そして、最後が「張り切った矢が、気充ち機熟しておのづから弦を放れて飛びゆく」放行(ほうぎよう)・超絶の段階。
それは『十牛図』にある、牛(真理)を外に求めてゐた牧童がやがて「一切は自己である」と気づき、さらに悟後の修行を経て、やがては現実の世界に立ち還る「入廛(につてん)垂手(すいしゆ)」の最後の段階でもあらうか。
わが国の武士道が禅と出遭って最後に辿り着いたのは、愚の如く魯の如く、衆生済度する利他行の境位であった。それは位すら捨てて痴愚にも等しい向下的遊戯の境地、晩年の山岡鐵舟が剣道の極意として示した「施無畏(せむい)」(無畏(むい)を施(ほどこ)す)で、誰をも慈しみ、誰の命をも活かす菩薩道の境涯であった。
5、筆禅道と武士道
私が加はってゐる「筆禅会」(禅・武道・書道を一体的に学ぶことを本旨とする研究会)では、剣禅一如の境涯を筆で表現し、鑑賞眼を高めてその「墨気」を徹見し、鍛錬の糧としてゐる。「書は人なり」で、書にはその人の境涯が墨気となって凛然とあらはれるからである。また、名品鑑賞は、書から境涯を学ぶ公案の如きものである。会を始められた先師横山天啓翁は、この道を、筆管を以てする禅であるとして「筆禅道」と名づけられた。
筆禅道では、鹿島神傳(かしましんでん)直心影(じきしんかげ)流(りゆう)の「法定(ほうじよう)」といふ剣の型を稽古する。その教への根幹は、「後来習態(こうらいしゆうたい)の容形を除き、本来清明の恒体に復する」こと、すなはち「育って来た環境の中で身に付いた癖を取り除き、型の稽古に依って本来の癖の無い心身に戻す」ことにある。特に、仕太刀(したち)が打太刀(うちたち)の影に成り切り、死に切るときに、本来清明の恒体である父母未生以前の「直心」がおのづと姿を現して来ると説くのである。
また、この法定は呼吸法に重点を置く。まず初心者は運(うん)歩(ぽ)といふ阿吽(あうん)の呼吸で歩く稽古に徹する。柳生宗矩の「西江水」の如く、大河を飲み込んだ心持で、丹田にこれを降ろして腹圧をかけ、相手を全力で押して行くのである。このやうに筆禅道には、武士道が行き着いた境涯とそこに到る鍛錬法がそのままこの現代にまで受け継がれてゐる。
至道無難禅師は「心本(もと)一物もなし。心の動き、第一慈悲なり。和(やわらか)なり。直(すなほ)也」と述べてゐる。人間は、本来、無一物である。誰もが自我を去ることによって、人間本来の慈しみの心、やはらかで素直な心に戻ることができる。直心影流五世の神谷伝心斎は、「一身を防ぐ道具は直心のみだ」との名言を残した。最終的には、「直心是道場」なのである。
わが国は、古来、道ある国である。日本文化の根底には「道」といふ見えない原理があった筈で、それ故に、人殺しに繋がる剣術が、わが国においては武士道となった。そして、それは禅と出遭ふことによって、「何事も去つたる所」を体得体現して、殺人剣を活人剣へ転じ、つひに神武不殺(じんぶふさつ)の和の道に至り着いた。かうして武士道は、「いのち」そのものに連なる「随神(かんながら)の道」に帰着したのである。
武士道は、「いのち」を活かす道である。私は、この武士道が個人の境涯にとどまらず、天下国家、世界人類の道とならねばならないと思ってゐる。わが国の武士道は、世界人類の道標(みちしるべ)であり、人々を導く希望の燈火(とも しび)である。それゆゑに、武士道と武士道を生成して来たわが国の歩みを子どもたちに伝へる責任が、われわれにはあると思ふのである。
(神奈川県立小田原高校定時制教諭)
今年の正月
西元寺紘毅先輩はパーキンソンと長年にわたり闘はれたが2月3日つひに他界された。先輩は三井石油化学(株)に長く御勤務で、退職後は関連会社の社長を務められた。
先輩のことが数年来ずっと気にかかってゐたが、今年の正月に頂いた賀状を見て、思ひ切ってご自宅に電話をした。奥様の代筆であると分ってはゐたが、やはりご容態は良くないことを奥様から知らされた。奥様の「主人も電話の傍にゐるので是非話して下さい」とのお言葉に従って、「西元寺さん、明けましておめでたうございます」と呼びかけたら、一呼吸をおいて、「ふるかはー、ふるかはー」と絞り出すやうなお声が受話器を通して聞えて来た。そのお声が私にとって最期となった。
我が先輩(とも)の絞り出す如きみ声聞き悲しかりけりこの正月は
桜島合宿
昭和39年、私が大学一年の夏、桜島で行はれた第九回全国学生青年合宿教室に参加したのは、まさに西元寺先輩の「全国から、志を持った者が大勢集ひ、男泣きするやうな感動がある。一緒に参加しようではないか」といふ〝ひと言〟であった。
当時の九州大学教養部のキャンパスは、三派全学連、民青、社青同による主導権争ひと連日のシュプレヒコールで騒然とした雰囲気であり、真っ赤な文字でスローガンが大書された立看板が並ぶ異様な光景を呈してゐた。ひと月ぐらゐ経て私も些(いささ)かげんなりしてゐた頃、大学での西元寺先輩との出逢ひがあったのである。
先輩は修猷館高校の二年先輩であった。「二年先輩」は高校生にとっては「大先輩」であり先輩の同期生には今も御指導頂いてゐる今村宏明さん、山本博資さん、木田浩隆さんがをられる。
九大信和会
桜島合宿における諸先輩、諸先生方の真剣な生き方に圧倒されつつ、更に小林秀雄先生の「常識について」といふご講義を間近に聞く機会を得たのである。今にして思へば実に得難いご講義であった。
先輩に誘はれ行きし彼の夏の桜島合宿我は忘れじ
この合宿を機に九州大学で、稲津利比古さん、島津正數さんらと共に「九大信和会」が発足したのであるが、その機縁を与へて下さったのは西元寺先輩であった。
百道浜(ももちはま)での小合宿で先輩方と共に学んだ日々は今でも懐かしく思ひ出される。先輩の豪快なお声と笑顔は、今もわが胸に深く刻まれてゐる
潮風の冷たき浜辺に集ひ来て朝まで語りし百道の合宿
〇
辻堂の明るき海辺を先輩と歩む願ひもつひに叶ず
獅子吼せし野太き声の聞えきて笑顔偲ばれ涙こぼるる
(元日産自動車(株))
昭和40年10月20日
「学問とは、単なる知識の積み重ねではない。古人が残していった文献に取り組む場合にも、私たちは心から古人を尊敬し、古人を忝う気持ちをもち、全身全霊を傾けて古人の心に触れようといふ謙虚な態度が必要なのだ。古人が一生を托して残していった言葉を、私たちはいのちがけで学ぼうではないか!さういふ基本姿勢が学問の本義であることを知らされました。友だちに対する場合でも、自分の心を閉ざして相手に接するのでは、相手の心の中に飛び込むことはできない。自分の真心を打ちつけぶっつけ、しかも友がどう思ひ、どう生きてゐるかといふことに心を労していく、これが友情の根本であると感得しました。
かういふ身近な、しかも人生にとって基本的な態度を教へて下さったのが、合宿教室であります。」
「私たちははじめて学問をする喜びを実感できたのです。私たちは学問の喜び、友情の喜びを求めて行って、おのづから日本といふ国のすばらしさを、人間性があふれるばかりに躍動してゐる祖国日本の真の姿を求めて行ったのです。さういふ学問をしてまゐりますと、現在の学園に流れてゐる誤った思想に対して断固戦って行かなければならないと痛感した次第であります。」
「現在の学園にはマルクス主義の風潮が嵐のごとく吹きまくってゐます。私たちは身近にそれを感じ、どうしたらいいのかと日夜心を砕いてをります。そこで私たちは学友の一人、日本人の一人々々をつかまへて〝この美しい祖国を護って行かなければならないじゃないか〟といふ心情をよび起していく以外に道はないと思ってをります。」
(「学生代表あいさつ」から抄出、東京・国立教育会館にて)
―昭和40年11月号所載―
廣木寧著 慧文社刊
天下なんぞ狂える 夏目漱石の『こころ』をめぐって (上)(下)
各税別2,000円
本会会員、廣木寧氏の近著である。著者が学生時代から愛読してきた夏目漱石に関する論考であり、序章のほか、全七章からなるハードカバー上下二巻の大作である。
『こころ』は漱石の代表作の一つとして知られるが、主人公である「先生」は長い遺書の終りに、明治天皇の崩御の際、「私は明治の精神が天皇に始まって天皇に終ったやうな気がしました」と記し、「もし自分が殉死するならば、明治の精神に殉死する積(つもり)だ」と妻に語ってゐる。
『こころ』の有名な一節だが、では、この「明治の精神」とは、「先生」にとって、漱石にとって、どのやうな精神であったのかは『こころ』を読むだけでは必ずしも明らかではない。本書はこの漱石にとっての「明治の精神」を明かすものになってゐる。
本書では、明治を生きた漱石の、青春時代の正岡子規との交友、半生をかけた英文学研究と英国への留学、小説家としての生活と門下生とのやりとりなど様々な側面に光を当ててゐる。著者は「人生の純粋性や理想を求めようとする哲学性なり思想性なりというものは私たちの心の中奥深くあるのだが、その、哲学性も思想性も日常性に食い殺されて行く生活の真っ只中で、漱石は戦いながら書き続けたのだ」と漱石の著作活動を評してゐるが、本書では漱石の不幸な生ひ立ちや恋愛や家庭の経済生活なども含めてその日常をも見据ゑつつ、漱石の内心の戦ひに迫る。漱石の小説、論文、講演録、書簡、漢詩などその言葉を丹念に読みとくとともに、様々な周辺のエピソードを交へて漱石像を描き出す手際はいつもながら見事で、興味深い。そして、その全体が漱石に生きてゐた「天皇に始まって天皇に終った」「明治の精神」に収斂する構成となってゐる。
私は、特に子規と漱石の友情と二人の志の高さに打たれた。著者は漱石が大学を卒業する前に発表した「英国詩人の天地山川に対する観念」といふ研究を紹介するに際して、子規の「俳諧大要」と並べて、二十代の両者の「研究の深さと烈しさ」、「(英文学と俳句文学と)耕す畑こそ違え同じ精神の高さと足腰の強さ」を指摘して、学問の豪傑たらんと「鍛錬」を競ひあった二人の仕事を評してゐる。二人の友情はこの学問の志と一つであった。漱石は留学中にもらった子規の最後の手紙を、後年『吾輩は猫である』の自序にその全文を引用した、といふことも本書で知った。『猫』は親友子規に捧げられたのだった。
本書では乃木大将について二章を割いてゐる。普通には旅順の名将と小説家では如何にも対照的に思へるが、本書で明らかにされる倫理的人格としての漱石の姿を示す言葉や漢詩を読むとき、両者の距離は意外に近いことを思はしめられる。二人とも明治新時代の国家的な使命感の中に生きた人である。本書で引用される漱石の書簡(鈴木三重吉宛)にも「死ぬか生きるか、命のやりとりをする様な維新の志士の如き烈しい精神で文学をやって見たい」とある。
著者が表題に選んだ「天下なんぞ狂える」とは大正五年の漱石最晩年の漢詩から取ったものである。七言律詩の一節に
天下何(な)んぞ狂える筆を投じて起(た)ち人間(にんげん)道(みち)有り身を挺(ぬき)んでて之(ゆ)く
吾(わ)れ当(まさ)に死すべき処(ところ)吾れ当に死すべし…
とあって、あたかも憂憤する志士のやうな気迫に満ちてゐる。それを題に選んだ本書の著者もまたその気持ちを等しくしてゐるのであらう。
本書の序によれば、漱石は百年後の日本人に向けてその作品を書いた。「百年後に第二の漱石が出て第一の漱石を評してくれればよい」と漱石の書簡中にあるといふ。昨年は漱石歿後百年であった。本書の著者は百年後の評家として本書を刊行した。第二の漱石としてかどうかは知らないが、漱石の志をよく見届けた人の書だと思ふ。著者の思ひは深く、読み応へのある本である。諸兄姉にもお手にとっていただきたい。
(IBJL東芝リース勤務小柳志乃夫)
編集後記
「拉致被害者の家族会」結成から20年、猶も悲痛な叫びが続くのか。これほど戦後政治の無力を示すものが他にあらうか。産経以外のメディアの「北」偏向が政治の無策を許した。金正日が拉致を白状してから「拉致」の大文字が一面に躍った。
(山内)