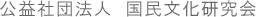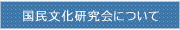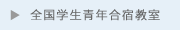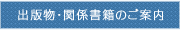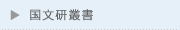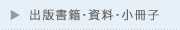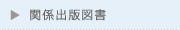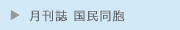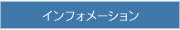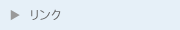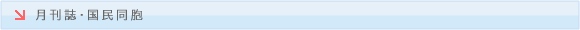
第665号
| 執筆者 | 題名 |
| 山内 健生 | さらなる時間と精力の「浪費」にならないか - 「小学校英語」が三年生から始まる! - |
| 柴田 悌輔 | 「ナショナリズム」を考へる - 先づは「日本人としての価値観」の共有を! - |
| 廣木 寧 | 道統と学恩と - 「東西文化融合の世界的使命を負ふもの」 - |
| 山田輝彦先生のご講義「実朝の歌」 - 昭和39年3月の春季大村合宿(昭和39年4月号所載) - |
|
| 新刊紹介 吉田好克著 高木書房 言問ふ葦―私はなぜ反「左翼」なのか―」 |
これまで小学校への英語教育導入について、「国語の力こそ、外国語学習の基礎ではないのか」などと本紙(平成26年7月号)でも疑念を呈して来たが、旧臘22日付産経新聞(二面)の「小学英語 30年度から先行実施―中教審が指導要領改定案」との記事を読んで改めて考へざるを得なかった。
前倒しで2、4年生から実施へ
現在(平成23年度からだが)、小学校では5、6年生を対象に「聞く・話す」を中心に週一コマの外国語活動(ほとんどが「英語学習」と見ていい)が行はれてゐる。それを次期学習指導要領の改訂(平成32年度)に2年先立て、各校の判断で3、4年生に前倒しすることが平成30年度から可能となるといふのだ。そして5、6年生は「読む・書く」の要素も学ぶ週2コマとなり教科書を使ふ教科となるといふ。
歌って・踊って・ゲームして
現在の小学校英語は、英語を話すALT〈外国語指導助手Assistant Language Teacher〉が、教員免許がないので担任教師の立ち会ひの下で行ってゐる。語彙の少ない小学生には文法の話は無理だし、そもそもALTの日本語が覚束ない。「聞く・話す」と言へば体裁がいいが、実際は多く「歌って・踊って・ゲームして」の授業となってゐるやうだ。
それでも〝生の英語〟に触れる良い機会だとの声もあるとも聞く。早くから英語に接することは「話す英語」への近道だとの考へがあるからだが、語学の専門家に言はせると、同じ英語と言ってもALTの出身国てよって発音に幅があるらしい。あれこれ考へると、たとへ児童が嬉々として参加してゐるとしても、小学校英語への不審は消えない。
もし国語に振り向けたとしたら…
週当り授業時数28コマの内の1コマが毎週(年間35週)英語学習に充てらてゐる。それが今度は5、6年生では週2コマ(年間70コマ)になる(次期学習指導要領では週当りの授業時数は1コマ増えるが―ちなみに授業時数は昭和五十年頃は週33コマだった―)。もし、英語学習に割かれる時間を「漢字の書き取り」「作文」「古典名句の朗読や諳誦」など国語教育の充実の方に振り向けたとしたら、その前と後とでは国語力にかなりの差違が生じるだらう。
何よりも、小学校英語に注がれる「精力」が、その準備に費やされる「時間」が、国語や算数に向けられないものかと思ふばかりである。担任教師としてはALTとの事前の打ち合せにも結構時間を取られるらしい。ただ、他教科の授業よりも教へる側に力が入ってゐるからだらうか、内容はともかく児童は授業には「嬉々として」乗って来るといふことだ。教師の熱意には応へようとするものだからである。しかし、それで身に付くものは何だらうか。
小学生時代は、家庭環境にも引けをとらない「人間の根っこをつくる」大事な時期ではないのか。たっぷりと国語の世界に浸り、国語を正しく身につけて自己の内面を形成する大切な成長期である(「漢字の書き順」や「かなの字形」を正しく学ぶことは、無意識ながら先人の生き方を仰ぐ国民教育に他ならないし、それは自国の文化を大切にすることでもある)。
底の浅い人間を生み出しかねない
外国語の習得は知的活動だから、国語の基礎の上に立って、従前のやうに中学校から始めた方が、生徒にも教員にも無理がないのではないか。外国語として学ぶ英語であり、国語(日本語)の環境の中での外国語学習だから、「読む・書く」から始めるのが自然のはずだ。 言ひたいことは、手順(時期)に問題がありはしないかといふことである(〔〇歳&ママクラス〕を用意する幼児英語教室まであるといふから恐ろしい)。
グローバル化の時代だ!、多くの非英語国でも小学校から教へてゐる!、「話せる英語」を早く!との声は多く聞くが、さうした国々が、その一方で次世代国民の教育(「国防」教育、「愛国心」教育など)にどれほど力を入れてゐるかは目に入らないらしい。「英語の時代」に遅れてはならないと言はんばかりに、足許を見ようとしない現行の小学校英語では、自国文化(国語)を軽侮する底の浅い人間を生み出しかねない。それこそ「グローバル化の時代」に軽んぜられるのではなからうか。
(拓殖大学日本文化研究所客員教授)
はじめに
「国家」とか「民族」とかいふ言葉を、迂闊に口にすると、とかく周りから白眼視される時代に、私は学生時代を過した。昭和30年代の日本では、「普遍性」が最も貴ばれた。グロ―バリズムといふ主義は普遍性を最も貴ぶ。それに反してナショナリズムとは、国家の個性を尊ぶと言へる。だが当時の日本は未だ、国家としての「個性」に自信が持てなかった。その為日本では永い間、グロ―バリズムを持て囃す思潮が、主流を占めてゐた。更に最近の国際情勢の変化を契機に、「ナショナリズム」を非常に危険視する論調が、又強まってきた。「ナショナリズム」とは、そんなに危険な「主義」なのだらうか。
アメリカ合衆国の大統領にトランプ氏が選ばれ、先日就任式が行はれた。日本のマス・メディアは、かうした結果を全く予測出來てゐなかったし、今でも臍を噛む思ひで、報道してゐる様子がほの見える。トランプ氏を「ナショナリスト」と、決め付けたメディアは、これ以上の「ナショナリズム」の横行を、何とか喰ひ止めたいとの思ひで躍起になってゐる感じである。
普遍主義への「疲労感」
第二次大戦後の世界における思想の主流は「グローバリズム」であった。米ソ冷戦(東西冷戦)の戦後世界にあって、東側陣営の「社会主義」に対して、西側陣営は「自由主義」を掲げた訳だが、どちらもある種の普遍主義であり「グローバリズム」であったと言へる。ところが「社会主義」の破綻(ソ連東欧陣営の自壊)によって冷戦構造が崩れて四半世紀が経過した現在、このところ幾つかの国に、「ナショナリズム」を標榜する勢力が現れてゐる。ひとつの「主義」の流行は、サイクルが短いのが普通である。それにも拘らず、戦後世界では社会主義、或いは自由主義といふ名の「グローバリズム」の賞味期間は五十年近く続いて永かった。その為それの反語である「ナショナリズム」への否定的評価も永続きしてゐた。メディアの多くはトランプ政権の短命を予測、又は期待してゐる。だがトランプ氏の登場は、永かったグロ―バリズムの終焉と私は考へてゐる。世界の指導的国家であったアメリカが、自ら自分の力を放棄し始めたのである。
これから世界の主要国家は、それぞれの生存を賭けて、闊達な競争を繰り広げるのだらう。シリアから大量の難民が発生したのを機に、欧州では大きな地殻変動が起きてゐる。 その一例がイギリスのEU離脱といふ事件だらう。先づEUといふ政治的統合体は、近代の「国民国家」を否定する思想に基いてゐる。欧州各国の国境の枠を撤去し、ユートピアじみた理想郷を欧州に造る。さうした理念が、EU本来のものであった。その理念に對してNOを突きつけたのが、イギリスのEU離脱の本質である。欧州各国の国民は、EUの理念でもある「グローバリズム」に、「疲れて」きたのではないだらうか。
グローバリズムへの疲弊感を否定的に捉へ、「ナショナリズムの擡頭」、或は「ポピュリズム(大衆迎合主義)の擡頭」、「極右勢力の擡頭」と、決め付ける傾向が、日本のマス・メディアには多い。この決め付けは戦後の日本だけに現れる独特な思考法とも言へなくもない。日本人は容易に戦前の「国家主義者」に立ち還り易いから要注意だと説きたがる反日イデオロギーは、日本のメディアには未だに根強い。
大量のシリア難民の流入が一つの契機だったのだらう。ネイション、つまりは自分たちだけの国家と国民を、今一度再構築したいといふ欧州各国の国民の希みが、表面に噴き出した。その感情を正しくないと、誰が咎め立てられるだらうか。独立主権国家を基本単位として構成される、いはゆる「近代世界」の枠組みを創ったのは、さうした「ナショナリズム」だった筈である。それの否定はそのまま、「近代」の否定に他ならない。
福澤の言葉「立国は『私』なり」
「国家」といふ言葉は福澤諭吉の著書『痩せ我慢の説』の冒頭の一節を思ひ出させる。
「立国は『私』なり、『公』に非ざるなり」
国家を構成するものとは、「政府」である「公」ではなく、「私」である民族であると、福澤は強調したかったのだらう。この一節には、又次のやうな思想も含まれる。
「私人としての資質が、卑小なものであつてはならない」
私人の集団である民族が保有する「知性」或は「文化」とは、絶えず磨き続けておかなければ、劣化するばかりである。そんな福澤の思ひを、彼のもう一つの著書『學問のすすめ』からも、私たちは汲み取る事が出来る。福澤の生涯は国を構成する私人を、如何にして啓蒙するかに、費やされてゐた。当時でも現在でも、国の指導者層(エリート)と、一般庶民との知識レベルの格差は甚だしい。この格差の是正こそ福澤の思想であったらう。この福澤の思想を正しく実践してこそ、「ナショナリズム」は、卑小ではなくなり得る。
人工国家アメリカの実態
国家の二大要素とは、領土と民族である。近代国家の成立以来、その領土を巡って、国家同士の争ひが永く続いた。さうした時代の記憶が、「国家」を卑小なものとし、「グローバリズム」をより良いものとする思想が力を持った由縁なのだらう。だがグローバルな世界とは、数多くのナショナル、つまりは民族国家の総和である筈だ。そして、さうした世界の構成単位である国家も又、国家を構成する私人、つまりは私人の集団としての民族で成り立ってゐる。
さて民族の定義だが、これが以外に難しい。それでも国家を構成するものは、ひとつの「文化」と「歴史」を共有する「民族」である事は確かだらう。それなら民族とは、同じ歴史と文化を、共有するものと定義出来る。それだけに異なる民族又は部族が、協同して同一の国家を構成するには無理がある。これはアメリカ合衆国といふ、人工国家を見てみれば解り易い。アメリカは移民で成り立つ国である。それだけに種々雑多な民族が、アメリカ国民として共存せざるを得ない。WASP(ホワイト・アングロサクソン・プロテスタント)を始めとして、アイルランド系、イタリア系、アフリカ系、アジア系などと、移り住んだ時期毎に別れて生活してゐる。この「別れて生活する」点に注目したい。
彼らは決して「渾然一体」として、アメリカに居住してはゐなかった。人は同一の民族同士で「暮らし住む」事が、心地よいのである。この現実は何人といへども非難すべきではない。それは人間の根源的な欲求に基く。だがオバマ氏が大統領に就任して以来、彼はかうした雑多な民族に、アメリカ国民としての同一性を求めた。この政策の理念は高貴ではあっても、余りにも人間性を無視し過ぎてゐる。リベラリストはとかく、人間性を無視してでも理想を追ひたがる。多くのアメリカ国民もそれに気づき、そして疲れたのだらう。
アメリカはグローバリズムを、国家存立の基本的価値観としてきた。私はその人間性無視の理念に、無理があったと思ふ。今回の大統領選でのトランプ氏の勝利とは、さうした無理の積重ねを、国民が拒否したからでもある。その意味では、アメリカと欧州における、グローバリゼーションの終焉とは、アメリカの価値観が終りを告げた事を示してゐる。
日本人の価値観を想起せよ
日本人は敗戦後アメリカ人の価値観を、そのまま受け容れてきた。もうそれもお仕舞にして良いのではないか。では日本人の価値観とは、如何なるものでありたいのだらうか。一例として、私は日本人の持つ「誇り高さ」といふ資質に注目したい。私はそれを日本人の価値観にしたいと考へてゐる。日本人は歴史的にも宿命的にも、外からの刺激によって、民族の思想を鍛えてきた。
戦後の70年間、日本は精神的にはアメリカの属国であった。これから世界の主要国家は、それぞれの国民国家の樹立にいそしむ事だらう。その中で日本は今までみたいに、アメリカとの同盟だけを賴りにする訳にはいかない。これからは否応なく、国家としての「自立」が求められる。それには防衛と外交の自主性の確立は当然の事として、それ以上に日本人としての価値観の共有が必要である。
唐突だが、江戸時代中期以降の「武士」といふ階級を考へると、面白い事に氣がつく。彼らはその時代、既に武闘集団ではなかった。つまり彼らには「存在理由」が失はれてゐた。だが日本人はその「無用の民」を、幾百年にも渉って温存してきた。武士たちは貧しくはあっても、指導層である事と、敎養を持つ事に誇りを持ち、「貧しさを恥ぢない」といふ文化伝統を保つたまま、明治といふ新しい時代を迎へた。
明治期に士族と呼ばれた彼らこそが、「明治新時代」といふ日本近代の成功を荷ったのである。今一度、私たちはこの日本民族の文化、「誇り高さ」といふものを、「民族の資質」として、呼び戻せはしないだらうか。世界の主要国家が自国のエゴを主張する中で、「貧しさを恥ぢない」といふ武士の生き方を想起したいものだ。日本と日本国民は民族の「誇り」と「節度」を失はない態度を維持し続けたい。
「誇り高さ」といふ価値観こそが、日本人の「ナショナリズム」であると、私は声を大にして言ひたいのである。
((株)柴田代表取締役)
黒上正一郎先生の「御本」との出会ひ
大学に入学すると、機縁があって国民文化研究会の指導を受けてゐた九大信和会といふ学内サークルに入った。信和会では前期は小林秀雄の文章を読んだが、夏休み明けの後期の例会は黒上正一郎先生の『聖徳太子の信仰思想と日本文化創業』(以下、御本(ごほん))の輪読となった。
御本の原本は昭和10年に刊行されたものであるが、以後は上梓の機会に恵まれず、やうやく昭和41年に復刊された。その際、理事長の小田村寅二郎先生は「復刊のことば」の中で、「この本に窺はれる著者の聖徳太子研究の姿勢は、日本の高等教育で教へる知識偏重の学道とは、本質的な相違を示してゐた」云々と若き日に御本を読まれた感想を述べられてゐるが、大学一年生の僕が御本に覚えた困難は、こちらの浅学も一因であることは当然として、「知識偏重の学道」で育てられたことに由来することが、今ははっきりと解る。
小田村先生は、また「青年・学生たちは、当時でも、この本はまことに難解な書物と考へ、『何回読んでも中々よく判らない』と話し合ひ」云々と述べられてゐる。戦前の思潮の中にゐた学生たちでも「よく判らない」と感じたのであるから、戦前の思潮が否定されてしまった戦後に育てられた僕に、御本が「よく判らない」のも当然なのであらう。僕が輪読の時間以外に自ら御本をひもとくのに丸3年を要した。
「大陸思想批判綜合の内的事業」
御本の第四編に、
| 《(聖徳太子は)固有民族文化と大陸文化との交流接触の時代に出現せさせ給ひ、わが日本の国礎を確立せられたる一代の政治は、また三(さん)経(ぎよう)義疏(ぎしよ)にあらはれし如き大陸思想批判綜合の内的事業にその根柢(こんてい)を置かれたのである。》 |
とある。いったい、いつの時代の、いづこの政治家が、その政治の根柢を、思想学術の「批判綜合の内的事業」に置くのであらうか。『憲法十七条』の第二条に「何を以てか枉(まが)れるを直(ただ)さむ」とあるやうに、人の心の「枉れる」のを「直」す難しさに直面されてゐた太子は、政治の混乱はひとへに思想の、ひいては信仰の混乱にあると痛感されてゐた。だからこそ、太子は、思想文献の表現に対しては細心であった。
黒上先生は太子の、経典への「内的批判」の例をいくつか示されてゐるので、引いてみる(御本第三編)。
まづ、『法華経』の「常好坐禅。在於閑処。修摂其心」(常に坐禅を好む。閑処に在り。その心を修摂す)の文に見られる心のありやうは、太子より50年ほど前の、黒上先生の言葉をかりれば「支那大陸の法華講讃史上に重大の地位を占(し)むる」光宅寺法雲も、「初(しょ)親近処(しんごんしよ)」に入ると釈してゐる。「親近処」とは菩薩(ぼさつ)たるものが親しみ近づくところ、といふ意味である。当時の碩学法雲は「常に坐禅を好む」者を褒めてゐるのである。ところが太子はさうではない。今の経典の文句は「不親近処(ふしんごんしよ)」に入ると釈される。その言はれるところは、「此(ここ)を捨て彼(か)の山間に就(ゆ)きて常に坐禅を好む」(『法華義疏』)、つまり俗事を避けて山の中に籠もって常に坐禅を好むのは、現実の困難から逃げてゐることになる。だから、さうであるならば「何の暇(いとま)ありてか此の経を世間に弘通(ぐつう)せむ」(『同上』)――山に籠もってゐて、苦しみ迷ってゐる世の中の人々の心を安めるためにある仏(ほとけ)の教へを、いったいいつ、弘めるのか、と疑はれるのである。黒上先生は、太子を憶念して次のやうに述べられてゐる。
| 《(太子は)「常に」なる言葉に大御心を留めさせ給うたのである。常に坐禅を好むといへば、個人的解脱の修養のみに終始する日常生活を表現するが故に、この生死超脱の理想を一我の天地に局分する偏倚的人生観に陥ることを教誡(きようかい)し給ふのである。》 |
「一我の天地に局分する偏倚的人生観」とは私たち凡人の人生から生れた人生観そのものである。
今一つ、これも法華経についてである。「有人至親友家酔酒而臥」(人有り。親友の家に至りて、酒に酔ひて臥す)といふ経典の文に対して、太子は、これでは親友が酒を与へて酔はせたことになると指摘されてゐる。これもまた僕ら凡人の日常であるのだが、太子は「此の文は少しく倒せり」と断じられて、「有人酔酒至親友家而臥」(人有り。酒に酔ひて親友の家に至りて臥す)と経典の文を訂正された。黒上先生は
| 《共にその心意を護り合はすべき 友情の誠を思はせ給ひ、又之に例同して自ら行ひ他を教化すべき聖人は衆生のため煩悩の縁とならざるべきを明かし、此に人生帰趨(きすう)の大道を具現し給ふ大御心は経典の表現法に厳粛精到の内的批判を示させ給ふのである。》 |
と述べられてゐる。経典は拝読し、熟読玩味すべきものであるが、大事なのは人生であって、経典が煩悩を促進させてはならないのである。
黒上先生の歴史的視野「我が国民生活の二大転機 ―推古朝と明治時代―」
黒上先生の国史の大観は重要であり、示唆に富む。
| 《我が国民生活は外来文化との接触によつて前後二回の重大転機に遭遇したのである。先に東洋文化を受容せし推古朝と、後に西洋文化を輸入せる明治時代とは正に此の二大転機に外ならぬのである。》(「序説」) |
明治時代に西洋といふ異文明に全身をさらした人に夏目漱石がゐる。漱石は西洋文学思想研究の第一世代の代表者である。明治四十年に漱石が行なった講演(「文芸の哲学的基礎」)の中で19世紀フランスの作家エミール・ゾラを採りあげてゐる(次のゾラの作品は『漱石全集』によれば『シャブル氏の貝』である)。
| 《御爺(おじい)さんが年の違つた若い御嫁(およめ)さんを貰ひます。結婚は致しましたが、どう云ふものか夫婦の間に子が出来ません。夫(それ)を苦に病んで御爺さんが医者に相談をかけますと、医者は何でも答弁する義務がありますから、左様(さよう)、海岸へ御出でになつて何とかいふ貝を召し上がつたら子が出来ませうよと妙な返事をしました。爺さんは大喜びで、早速細君(さいくん)携帯で仏蘭西(フランス)の大磯(おおいそ)辺(あたり)に出掛けます。すると其処に細君と年齢から其他(そのた)の点に至るまで夫婦として、如何にも釣り合ひのいゝ男が逗留(とうりゆう)して居まして細君とすぐ懇意になります。両人は毎日海の中へ飛び込んで一所に泳ぎ回ります。爺さんは浜辺の砂の上から、毎日遠く之を拝見して、中々若いものは活潑(かつぱつ)だと、心中ひそかに嘆賞して居りました。ある日の事三人で海岸を散歩する事になります。時に、お爺さんは老体の事ですから、石の多い浜辺を嫌つて土堤(どて)の上を行きます。若い人々は波打際を遠慮なくさつさとあるいて参ります。所が約(およそ)五六丁(ちょう)も来ると、磯際に大きな洞穴(ほらあな)があつて、両人がそれに這入ると、うまい具合と申すか、折悪(おりあし)くと申すか、潮が上げて来て出る事が六(む)づかしくなりました。老人は洞穴の上へ坐つた儘(まま)、沖の白帆を眺めて、潮が引いて両人の出て来るのを待つて居ります。そこであまり退屈だものだから、不図(ふと)思出して、例の医者から勧められた貝を出して、此貝を食つては待ち、食つては待つて、とうとう潮が引いて、両人が出て来る迄には余程多量の貝を平(たいら)げました。其場(そのば)は夫(そ)れで済みまして、愈(いよいよ)細君を連れて宅へ帰つて見ますと、貝の利目(ききめ)は忽(たちま)ちあらはれて、細君は其月から懐妊して、玉の様な男子か女子か知りませんが生み落して老人は大満足を表すると云ふのが大団円(だいだんえん)であります。》 |
漱石によれば、文芸の理想は四つある。真、善、美、荘厳である。文芸作品が一つの理想を表さうとして他の理想を欠くことは止むを得ないが、他の理想を打ち崩してはいけないと漱石は考へる。今のゾラの話は「真(実)」を表さうとして、「善」も、取りやうによっては「美」も打ち崩してゐる。漱石は思ふ、一般の世の中が腐敗して道義の観念が薄くなればなる程「真」以外の理想は低くなる。「善」などはどうでもいい、「荘厳」はさらに興味がない、「真」さへ表せればいいといふことになる。漱石は続ける。
| 《日本の現代がさう云ふ社会なら致し方もないが、西洋の社会がかく腐敗して文芸の理想が真の一方に傾いたものとすれば、前後の考へもなく、すぐ夫(それ)を担いで、神戸や横浜から輸入するのは随分気の早い話であります。外国からペストの種を輸入して喜ぶ国民は古来多くはあるまいと考へる。》(『文芸の哲学的基礎』) |
太子が憂へたのも、「内的批判」なしに、日本国民の人生観に「煩悩の縁」となる「ペストの種」が輸入されることなのである。
夏目漱石の眼力「日本人は輸入品にすぐ食ひ付きたがる」
あるアンケートに応へた文(応問「世界の大変局と戦後の日本」、大正四年)の中で、漱石は「日本人は新ら((ママ))しいものを見るとすぐ食ひ付きたがります」と語り、続けて
| 《或る友人が来て日本人は新しくさへあれば何でも飛びつきたがる国民だと云ひました。その通りです。然(しか)し彼等の飛び付きたがるのは輸入品に限るやうです。》 |
と述べてゐる。ここにあるやうに日本人の性情が「何でも飛びつきたがる」性情だからこそ、「内的批判」が必要となるのであるが、この性情が日本文化の豊かさを造り続けて来たのも否定し得ない。黒上先生は御本の中で次のやうに述べてゐる。
| 《東洋文化の伝統及び理想を正しく現実に把持(はじ)するものは我が日本である。大乗仏教及び儒教の如き東亜大陸の代表的文化は、すでにその本国に於いて衰頽(すいたい)せるに拘(かか)らず、共に我が国土に朝宗(ちようそう)して国民生活の体験に融化せられ、その生命を持続開展せしめられて居る。日本文化とは実に東洋文化の綜合としてのそれであつて、それは西洋文化と対照補足せらるべき世界文化の重大要素であり、この文化を把持する我が国民は更に東西文化融合の世界的使命を負ふものである。》(「序説」) |
外来文化がわが「国民生活の体験に融化」されるとは、我が国民の美質を残したまま、「枉」れるは正し、あるいはその美質を伸ばすやうに摂取されるといふことである。さういふ摂取の上に東洋文化を把持してゐるからこそ、新しく受容した「善」といふ言葉を活かされた太子の言葉をかりれば、「諸(もろもろの)善(ぜん)を行ふ」国民だからこそ、西洋文化の摂取が期待されるのである。黒上先生は、わが国民はさらに「東西文化融合の世界的使命を負ふ」と断じられたのである。
漱石から小林秀雄、江藤淳へ
漱石の一世代(30年)後の文学者にフランスの哲学文芸に学んだ小林秀雄がゐる。小林の文業について、さらに一世代あとの文学者の江藤淳は、「フランス象徴主義の果汁を万葉以来の日本文学の持続のなかに注入し」(「サルディスの壺」)云々と述べてゐる。これは小林が、外来の文化が国民にとって「煩悩の縁」とならぬやうに、言ひ換へると、人生観に翳(かげ)りをもたらさぬやうに、善は摂(と)り悪(あ)しきは棄てることを外来文化輸入の留意眼目とすることを第一義とする、正統の日本文学者であることを述べたものである。
当の小林が『本居宣長』を完成させたときに、江藤と対談(「『本居宣長』をめぐって」)し、西洋思想の受容について自らの体験を語ってゐる。
| ― 私(小林)は若いころから、ベルグソンの影響を大変受けて来た。ベルグソンのいふところは、常識人は存在と現象とを分離する以前の事物を見てゐる。常識にとっては、対象は対象自体で存在し、而(しか)も私達に見えるがままの生き生きとした姿を自身備へてゐる。これはフランス語でいふ、「image(イマージュ)」である。このimageを「映像」と現代語に訳しても、どうもしっくりしない。宣長も使ってゐる「かたち」といふ古い言葉の方が、余程(よ ほど)しっくりするのだ。「古事記伝」になると、訳ももっと正確になる。性質情状と書いて、「アルカタチ」とかなを振ってある。「物」に「性質情状(アルカタチ)」である。これが「イマージュ」の正訳だ。「古事記伝」には、ベルグソンが行った哲学の革新を思はせるものがあるのだ。― |
「古事記伝」といふ創造的考証は、小林によれば、日本語に、つまり日本人の思惟における、哲学的展開に「革新」をもたらしてゐる。小林はそれをベルグソンの哲学を援用して明らかにした。
私たちの「使命」
黒上先生のいふ日本が負ってゐる「東西文化融合の世界的使命」とは、小林が達成したやうな大業績ばかりをいふのではない。
私たちに何ほどの事が出来るかわからない。しかし、私たちは、黒上先生がご自身に向かって言はれたやうに「幼き研究の歩み」を続けるしかない。それが道統につながる私たちの「使命」であり、学恩に報いる正道だと信ずるのである。
((株)寺子屋モデル世話役)
1、実朝の生涯
鎌倉幕府の三代目の将軍であり、日本の文芸史、思想史の上に不滅の光芒を放つ実朝は建久(けんきゅう)3年(1192年)父頼朝母政子の子として生れた。頼朝が征夷大将軍に任ぜられてから間もない8月9日のことであった。そして、承久(じょうきゅう)元年(1219年)正月27日、鶴岡八幡宮に前夜からの積雪をついて拝賀の行列が続いたが、境内の銀杏のかげに身をひそめてゐた甥の公暁(くぎょう)の手によって暗殺された。年28、まさに痛恨すべき夭折であった。
保元、平治の乱から実朝の死まで、源氏の血統は流血の悲劇にいろどられてゐる。保元の乱で敗れた為義は、子の義朝によって殺された。その義朝は平治の乱で敗れて清盛のために殺された。義朝の子の頼朝は、武家政権を確立して行く過程で肉親の弟である範頼、義経をつぎつぎに殺して行った。頼朝を継いだ頼家が正式の将軍職にゐたのは、わづかに一年余りで北条時政のために弑せられた。公暁は頼家の子であり、叔父実朝に対する根深いにくしみを秘めつつ生きてゐたと思はれる。かうして、為義から公暁までの五代の系譜をたどるとき、その命を全うしたのは頼朝一人だったと言っても過言ではない。このすざましい人間崩壊の修羅を凝視しつつ、実朝の多感な青春が形成されて行ったのである。実朝の十九才の時、聖徳太子の御影を供養したといふ記事が東鑑(あづまかがみ)に見られるが、高貴な血統に生れて肉親相剋のの悲劇のただ中に生きたといふ点で、この二つの天才は驚くほど相似を示すのである。
実朝が将軍職についたのは12才、13才の時、坊門(ぼうもん)宰相信清(のぶきよ)の女(むすめ)を夫人に迎へた。ここに東国の武士の文化と、王朝文化の接触の機が開かれたと思はれる。14才の時、初めて和歌12首を詠んだが、その年、京都では新古今集の撰進があり侍臣の内藤朝親の手によって実朝に伝へられた。17才の時に古今集を入手し18才で定家から最初の歌の指導を受けてゐる。実朝が定家から万葉集の写本を贈呈され「重宝何物か之に過ぎむや」と言ったと東鑑に記されてゐる。これはかれが22才の時であったから、従来実朝の万葉調はそれ以後の作であらうと推定されてゐたが、佐々木信綱博士の発見によって、実朝の歌を定家が記録したものの日付が「建暦(けんりゃく)3年(1213年)12月18日」であることから、金槐集の歌は、実朝22才以前の作といふことになった。その根拠にたてば実朝の七百首余りの歌は18才から22才までの間に作られたことになる。驚くべきことである。
2、無常感と罪業感
多感な青春の眼前で展開される悲劇をみつめて、彼の心は痛切な悲しみにみたされたと思はれる。ふとよみ捨てた歌の中に惻々と胸をうつものがあるのも、かりそめのことではあるまい。
我心いかにせよとか山吹のうつらふ花のあらしたつみむ
「山吹に風の吹くをみて」といふ詞書をもった一首だが、疾風にもまれて散らむとする山吹の無常をやるせない思ひに耐へて凝視する姿が目に見えるやうである。
萩の花くれぐれまでもありつるが月出て見るになきがはかなさ
「庭の萩わづかに残れるを月さしいでて後見るに散りわたりたるにや花の見えざりしかばよめる」といふ長い詞書を持った歌である。夕暮にはたしかに、わづかだが残ってゐた花、それが月が出るまでのほんの短い時間にすっかり散ってしまってゐた。その一瞬の間の自然の変化を「はかなさ」とうたふのである。この「はかなさ」は、王朝文学の「もののあはれ」の範疇ではとらへられぬ、もっと悲痛な体験に裏づけられてゐる。同じことは「思罪業歌」といふ詞書を持った次の歌にもなまなましくうたひ上げられる。
ほのほのみ虚空にみてる阿鼻(あび)地獄行くへもなしといふもはかなし
所詮は無間(む げん)地獄へ落つるより外行くへもない人間の罪業、その地獄のほむらを見つつ「はかなし」とうたふのである。この「はかなし」は鎌倉新仏教をうみ出す発条でもあった。
3、自然と人生
強い無常感は、一転すると切実な永遠への思慕となる。それは古今集以来の花鳥諷詠のマンネリズムを脱出せざるを得なかった。「万葉調」といふやうな言葉では概括出来ぬ生命の力学の表現であった。
大海の磯もとどろによする波われてくだけてさけて散るかも
「われ」「くだけ」「さけ」と次第に強まって行く語調が、寄せて来る怒濤の動きに呼応する。この歌に「壮快」ではなく「憂悶」をよみとった小林秀雄氏の炯眼(けいがん)はさすがといふ外はない。山の端(は)に入る落日を見てよんだ次のやうな歌もある。
紅のちしほのまふり山のはに日の入るときの空にぞありける
「ちしほ」は「千入」すなはちいくども染めるといふ意、「まふり」は「真振」で、これも布を染料に入れて幾度もふる意である。落日の空一面が、幾度も染料に入れて染め上げたやうに真紅だといふ意味の歌で、彼の短命を予感させるやうな凄絶な歌である。かういふ緊張し、凝縮された生命は、道の辺に泣く孤児に涙し、ものいはぬ四方のけだものにも親子の情を思ひ、洪水に泣く民を思って、八大竜王を叱咤する。
山はさけ海はあせなむ世なりとも君にふた心わがあらめやも
彼が22才の時、後鳥羽院にさし上げたといはれるこの歌が、かりそめのものである筈がない。
(編註・筆者は当時、福岡県立若松高校教諭。のち福岡教育大学教授。長らく本会の常務理事を務め、平成21年逝去)
吉田好克著 高木書房
言問ふ葦―私はなぜ反「左翼」なのか―」 税抜2,400円
宮崎大学准教授の著者は、本会の第51回合宿教室(平成18年、於・霧島)で「『日本待望論』について」と題して登壇されてゐる。その折の講演記録を含め、著者がこれまで新聞や雑誌に発表された論考が、「私の文章に御関心をお寄せ下さる方々のためにも、手に取りやすいやうな形にしておきたい」と願って、一本に纏められたものである。表題からもお分りのやうに、歴史的仮名遣ひでの表記となってゐる。
読みすすめてゆくうちにだんだんと分ってくるのは、リズミカルで小気味よい、歯に衣(きぬ)着せぬ著者の語り口の魅力である。これはそのまま、著者の生一本な性格を示してゐると思はれる。そして、時事問題が果敢に論じられるが、それらはすべて単なる政策論といふものでなく、著者の人間に対する深い洞察に裏付けられてゐる。中でも平成10年5月30日に「北朝鮮に拉致された日本人を救出する宮崎の集ひ」を「実行委員長」として開催された後、同年6月25日付の「月曜評論」紙に掲載された「日本及び日本人の責任と威信が問はれる―日本人拉致事件が突きつけるもの」の次のくだりは、強く印象に残った。
《拉致問題は、国家の責任と威信といふ問題を提起してゐる。といふことは、我々日本人の責任と威信が問はれてゐるといふことである。今更『朝日』なんぞに言はれずとも、「日本の態度がきわめて大きな意味をもつ」(6月7日社説)のは余りに当然のことである。被害者を奪還したレバノンの例もある。政府が「あらゆる手段を講じる」といふ断固たる態度を取れるやうに、我々国民が強力に後押しをするべきではなからうか。
政治家の程度は国民の程度の反映なのだから、政府が弱腰なのは、実は我々が弱腰だからである。だとすれば、責任の一端は我々にもあるといふことになる。「同情」といふやうな素朴な感情を別にすれば、私どもの運動はさういふ自覚を動機としてゐる(略)。
歴史教科書刷新運動の推進者に対して「学者なのか運動家なのか」と揚げ足を取る保守派の言論人が出て来る御時世だが、この運動に参加するには、囚はれの同胞と御家族の苦悩に思ひを致しつつ、国家の責任といふことについてしばし沈思黙考すれば良いのであつて、身分の規定なんぞ一切不要である。読者諸賢もできることから始めて戴きたいと切に願ふものである。》
「拉致問題は、国家の責任と威信といふ問題を提起してゐる。といふことは、我々日本人の責任と威信が問はれてゐるといふことである」。このご指摘によって問題は、私達一人一人の「責任と威信」といふ生き方に関ってくる。具体的には、「囚はれの同胞と御家族の苦悩に思ひを致しつつ、国家の責任といふことについてしばし沈思黙考す」る中で、私達めいめいの生き方として「できることから始め」るものであるといふ。このご提言にはハッとさせられ、わが身を正さざるを得なかった。
著者は「フランス17世紀が生んだ天才思想家ブレーズ・パスカル」の研究者である。その代表作『パンセ』に関する「『パンセ』を読む」といふ論考も収録されてをり、著者の「パスカルとの対話」は興味が尽きない。また、著者が筑波大学に助手として赴任されてから薫陶を受けられた筑波大学名誉教授竹本忠雄先生の御著『われ、日本をかく語れり―ヨーロッパ講演・対話集』の「校訂者解説」は、著者の先生への敬愛の情に貫かれてをり、一読して該書を読みたくなるものであった。
その他、本書収録の論考から教へられ考へさせられることが多々あった。多くの方にご一読をお勧めしたい。
(元アルパック(株)北濱 道)
今年の皇居勤労奉仕について
平成29年の勤労奉仕は10月下旬を考へてをります。月曜日から木曜日までか、火曜日から金曜日までの4日間で、体調不良を除き全日程参加が原則です。10月の第4週か、第3週かで宮内庁に申請する予定です。
ご希望の方は、氏名、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号)を3月末日迄にお知らせ下さい。
平成28年団長 島津正數
Eメールアドレス maruni10ji@gmail.com
携帯電話 080・5499・0847
ファックス(国文研事務局 澤部壽孫) 03・5468・1470
近刊予定 第61回合宿教室の記録
日本への回帰 第52集
編集後記
2/23夜のNHKニュースは〝慰安婦問題を象徴する少女像〟云々と報じてゐた。正確には「慰安婦問題の誤解を象徴する少女像」だ。「少女→慰安婦」といふ誤情報を世界中に拡散した震源地の朝日新聞は〝慰安婦を象徴する「少女像」〟(2/24朝刊)と、もっと直接的で、二年余り前、慰安婦報道の虚報で社長が辞任したはずなのに、虚報を続けてゐることになるし、国外でも訂正されてゐない。歴史教科書検定誤報事件(昭和57年)でも後始末をきちんとしてゐない。古いことと言ふなかれ!
(山内)