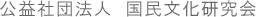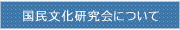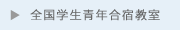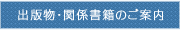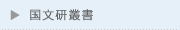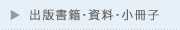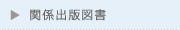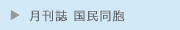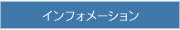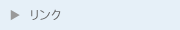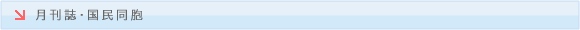
第634号
| 執筆者 | 題名 |
| 小柳 志乃夫 | 〝やまとのことばに、やまとのいのちを〟 - 淡路での合宿教室を前に - |
| 布瀬 雅義 | 日本語が作る脳 - 「虫の音」を左脳で聞く日本人、右脳で聞く西洋人!? - |
| 廣木 寧 | 〝今の学問は君たちから生きた知恵を奪ってゐます。君たちはさう感じないか〟 - 小林秀雄は問ひ質した - |
| 國武 忠彦 | 国民文化研究会・新潮社編 〝小林秀雄「学生との対話」〟刊行の経緯(3) |
| 書籍紹介 井上 義和著 『日本主義と東京大学━昭和期学生思想運動の系譜━』 柏書房、税別3,800円 |
今年も8月がやってきた。私にとっては、そして当会の会員の多くの方々にとってもさうであらうが、8月は合宿教室の季節である。学生のときから参加してきた、毎年の夏の合宿教室は、全国の師友との年に1回の再会の場であり、新たな友との出会ひの場であった。そこにはいつも家族的な暖かな雰囲気がたたへられてゐて、阿蘇を始めとする合宿地の風景とともに今は亡き師友の姿が懐かしく思ひ起される。
合宿教室は単なる知識吸収の場ではなく、先人や講師の生きた言葉に出会ひ、互ひに思ひを述べ合はうといふ場である。明治から昭和にかけての詩人、三井甲之の長詩『祖国礼拝』の一節に
やまとのことばに
やまとのいのちを
ともにうたひて
こゝにあつまる
友よ、はらからよ、
ともに喜び、悲み、泣き、憤り、
行かなむ、友よ、もろともに…
とある。学生時代に小合宿で学んで印象に残る強い言葉だが、今思へば、その言葉は合宿教室の求める姿を指し示してゐるやうにも思はれる。「やまとのことばに、やまとのいのちを」―合宿教室は国語の豊かな伝統を共に学び、生きた言葉を求め、そこに友情をつちかふ場といへよう。
国語の伝統の中核に位置するのが和歌である。過日、英語学者で評論家の渡部昇一氏の旧著『日本語のこころ』を久しぶりに再読したが、和歌の伝統とその意義についての論述が興味深かった。その一つは、日本では「和歌の前の平等」といふ固有の平等原理があったといふ指摘である。それは万葉集といふ国民歌集の姿に端的に示されて、そこでは天皇から庶民に至るまで一つの歌集にまとめられてゐる。これが漢詩などの外来語の詩歌集であれば教養の有無や身分格差が反映されて国民的連帯感は生れなかったであらうが、和歌は古事記以来の魂のふるさとともいふべき大和言葉をもとに作られるから、まごころをうたひあげた歌は、その作者が天皇であれ、庶民であれ、等しく読む人の心を打つのである。
日本人は法の前の平等といふ外的平等の前に和歌といふ内的、精神的な平等の世界を有してゐた。
さらに渡部氏の興味深い指摘の一つは「日本人は日本語の中に生れる」といふものである。日本人は桜を愛し、幕末の志士も特攻隊員も散りゆく桜の花びらに自らの姿を重ねてきた。さういふ桜に対する日本人の特別な感情は、桜の自然の美だけでは説明できない。海外でも桜は同じく咲いてもそれを歌った詩歌は少ないのである。氏は日本の詩歌の伝統が桜の花とその散る様に対する感慨を呼び起すのであって、この伝統の外に生れた人には散りゆく桜の花に特別の美は見えないのだといふ。山桜はプルヌス・セルラタ・スポンタネアといふ学名で呼んでも客観的世界の自然物としての植物に過ぎないが、これを「やまざくら」と呼んだ瞬間に「我々の魂の内側とかかわりあいを持つのである」と氏は述べる。
この著書の書かれたのは40年前だが、同じ感覚が今の日本人の中に生きてゐるだらうか、本来、僕らはさういふ国語の伝統の中に生れてきたのである。僕らの祖先はその情意を言葉にとどめてきた。国語を学ぶとはこの日本人の精神を学ぶのであり、僕らの魂の内側を構成するものを見つけることであらう。さういふ言葉を一つあげてみよう。
万葉集の防人の歌に
忘らむと野行き山行き我(われ)来(く)れどわが父母は忘れせぬかも
の一首がある。東国の若者は九州の防備のために兵士として徴用された。父母に対する愛惜の思ひを断ち切らうと、野を越え山を越えて来たけれどもわが父母の姿は忘れようにも忘れられない、と嘆くのである。「わが父母は忘れせぬかも」、その言葉を口に唱へるとき現代の我々にも郷里に残し、或いは死別した親の姿がまざまざと甦ってはこないか。そのとき防人の歌は明らかに我々の魂の内側に声を響かせたのである。
「やまとのことばに、やまとのいのちを」―今年の合宿は初めて9月に淡路島で行はれる。今回も、先人の、友人の生きた言葉に出会ひたいものだ。同じ詩人はかうも詠んだ。
「友よ! と呼べば 友は来たりぬ」
(興銀リース㈱)
「虫の音」に気がつかない!?
東京医科歯科大学の角田忠信教授が、1987年1月にキューバのハバナで開かれた第1回国際学会「中枢神経系の病態生理学 とその代償」に参加した時の事である。キューバではいまだ戦時体制が続いてをり、西側諸国からの参加者は角田教授一人だった。
開会式の前夜に歓迎会が開かれ、東欧圏から大勢の科学者が参加してゐた。キューバ人の男性が力強いスペイン語で熱弁をふるふ。しかし、教授は会場を覆ふ激しい「虫の音」に気をとられてゐた。なるほど暑い国だな、と感心して、周囲の人に何といふ虫かと尋ねてみたが、だれも何も聞えないといふ。教授には「蝉しぐれ」のやうに聞えるのに!
午前2時頃、やうやくパーティが終って、キューバ人の若い男女二人と帰途についたが、静かな夜道には、先ほどよりももっと激しく虫の音が聞える。教授が何度も虫の鳴く草むらを指して示しても、二人は立ち止まって真剣に聴き入るのだが、何も聞えないやうだ。不思議さうに顔を見合はせては、お疲れでせうからゆっくりお休みください、といふばかりであった。
教授は毎日、この二人と行動をともにしたが、3日目になってやうやく男性は虫の音に気づくやうになった。しかし、それ以上の感心は示さなかった。女性の方は、つひに一週間たっても分らないままで終った。どうも日本人の耳と、外国人の耳 は違ひがあるやうだ。
左脳と右脳
かうした聴覚の違ひを切り口に、角田教授は日本人の脳が他の民族の脳と違ふ点を生理学的に追求してきた。その結果が驚くべき発見につながった。人間の脳は右脳と左脳とに分れ、それぞれ得意分野がある。右脳は音楽脳とも呼ばれ、音楽や機械音、雑音を処理する。左脳は言語脳と呼ばれ、人間の話す声の理解など、論理的知的な処理を受け持つ。ここまでは日本人も西洋人も一緒である。
ところが、虫の音をどちらの脳で聞くかといふ点で違ひが見つかった。西洋人は虫の音を機械音や雑音と同様に音楽脳で処理するのに対し、日本人は言語脳で受けとめる、といふことが、角田教授の実験であきらかになった。日本人は虫の音を「虫の声」として聞いてゐるといふことになる。
キューバ人にとっては、会場を覆ふ激しい虫の音も、いつもの騒々しい雑音だと慣れてしまへば、意識にのぼらなくなってしまふ。我々でも線路沿ひに長年住んでゐれば、騒音に慣れて、電車が通っても意識しなくなってしまふのと同じ現象なのだらう。しかし、虫の音を日本人は「人の声」と同様に言語脳で聞いてゐるので、雑音として聞き流すことはできない。スペイン語の熱弁と激しい虫の音は、教授の左脳でぶつかってゐたのだ。
このやうな特徴は、世界でも日本人とポリネシア人だけに見られ、中国人や韓国人も西洋型を示すといふ。さらに興味深いことは、日本人でも外国語を母語として育てられると西洋型となり、外国人でも日本語を母語として育つと日本人型になってしまふ、といふのである。脳の物理的構造といふハードウェアの問題ではなく、幼児期にまづ母語としてどの言語を教はったのか、といふソフトウェアの問題らしい。
左脳か、右脳かの実験
この違ひを考察する前に、かうした結果がどのやうな実験で 得られたのか、簡単に見ておかう。
人間の耳から脳への神経系の構造は、左耳から入った音の情報は右脳に行き、右耳から入ると左脳に行く、という交叉状態になってゐる。そこで、左右の耳に同時に違ったメロディーを流して、その後で、どちらのメロディーを聴きとれたかを調べると、常に左耳から聴いた方がよく認識されてゐる事が分る。これで音楽は、左耳、すなはち右脳の方が得意だと分る。同様に、違ふ言葉を左右から同時に聴かせると、右耳、すなわち左脳の方がよく認識する。我々がほとんどの場合、右耳に受話器をあてるのは、このためださうだ。これが最も基本的な実験方法である。
かういう実験で、いろいろな音で、左脳と右脳の違ひを調べると、音楽、機械音、雑音は右脳、言語音は左脳といふのは、日本人も西洋人も共通であるが、違ひが出るのは、母音、泣き・笑ひ・嘆き、虫や動物の鳴き声、波、風、雨の音、小川のせせらぎ、邦楽器音などは、日本人は言語と同様の左脳で聴き、西洋人は楽器や雑音と同じく右脳で聴いてゐることが分った。
アメリカでの「虫の音」?
虫の音と言へば、私にもこんな体験がある。ボストンから内陸部に車で二時間ほど入った人里離れた山中で、見晴らしの良い所があったので、車を止めて一休みしてゐると、昼間なのに虫がしきりに鳴いてゐる。
それを聞いてゐるうちに、ふと、さう言へばカリフォルニアに四年も住んでゐたが、虫の音に聴き入った覚えがないな、と気がついた。乾燥したカリフォルニアでも沿岸部にはかなり緑も多い。しかし私の記憶の中の光景では、なぜか常に豊かな緑がシーンと静まりかえってゐるのだ。やかましい蝉しぐれだとか、秋の夜長の虫の音だとかは、どうしても思ひ出せない。
アメリカ人が虫といふ場合にまづ思ひ浮べるのは、モスキート(蚊)、フライ(蠅)、ビー(蜂)など、害虫の類だ。しかし蜂はまだしも、蚊や蠅はほとんどお目にかからない。だからたまに蠅を見かけると、とんでもない不衛生な所だといふ感じがする。文明生活の敵だとして、とことん退治してしまったのだらうか?
また昆虫を示す単語には、悪い語感が付随してゐる場合が多い。"insect"には「虫けらのような人、卑しむべき人」といふ使ひ方があり、"bug"は、「悩ましい、てこずらせる」から、転じてソフトウェアの「バグ」などと使はれる。日本語なら「虫けら」とか、蚤、シラミのイメージだ。
虫はすべて害虫であり、その鳴く音も雑音と同様に聞くとなれば、蚊や蠅を退治する殺虫剤で、見境なく一緒に全滅させてしまったとしても無理はない。
虫の音に聴き入る文化
日本では対照的に、虫の音に聴き入る文化がある。現代でもコオロギ類の画像と鳴き声を納めたインターネットサイトから、飼育法を解説した書籍まで無数にある。「虫の声」といふ童謡は、虫の音に聴き入る文化が子供の頃から親しまれてゐる一例である。
あれ 松虫が鳴いている
チンチロ チンチロ チンチロリン あれ 鈴虫も鳴き出した
リン リン リン リン リーン リン
秋の夜長を鳴きとおす ああ おもしろい 虫の声
この伝統は古代にまで遡る。
夕月夜心もしのに白露の置くこの庭にこほろぎ鳴くも(万葉集、しのに=しみじみした気分で)
近世では、明治天皇の御製が心に残る(「虫」、明治41年)。
ひとりしてしづかにきけば聞くままにしげくなりゆくむしのこゑかな
一人静かに耳を傾けると、虫の声がより一層繁く聞えてくるといふ、いかにも精密な心理描写である。また虫の「声」といふ表現が、すでに虫の音も言語脳で聞くといふ角田教授の発見と符合してゐる。もう一つ明治天皇のお歌を掲げる。
虫声(明治44年)
さまざまの虫のこゑにもしられけり生きとし生けるものの思ひは
松虫や鈴虫など、さまざまな虫がさまざまな声で鳴いてゐる。それらの声に「生きとし生けるもの」のさまざまな思ひが知られる、といふのである。人も虫もともに「生きとし生けるもの」として、等しく「声」や「思ひ」を持つといふ日本人の自然観がうかがはれる。日本人は虫の音も人の声と同様に言語脳で聞いてゐる。
犬は「ワンワン」 猫は「ニャーニャー」
角田教授の発見では、虫の音だけでなく、そのほかの動物の 鳴き声、波、風、雨の音、小川のせせらぎまで、日本人は言語脳で聞いてゐるといふ。これまた山や川や海まで、ありとあらゆる自然物に神が宿り、人間はその一員に過ぎないといふ日本古来からの自然観に合致してゐる。
| 「幼稚園から小学校の4、5年ぐらいの日本の子供に、犬はなんといって鳴くかというと、ワンワンというにきまっているのです。マツムシはチンチロリンという。外国人に聞きますと、ひじょうに困るのです。なんというていいか一生懸命考えて記憶を呼び出して、ウォーウォーといったり、ワーワーと言ったり」(角田教授との対談者、園原太郎京都大学名誉教授(心理学)の発言、後掲書(1)122頁) |
日本の子供が「ワンワン」と答へるのは当然である。親が犬を指して「ワンワン」と教へるのであるから。同様に猫は「ニャーニャー」、牛は「モーモー」、豚は「ブウブウ」、小川は「サラサラ」、波は「ザブーン」、雨は「シトシト」、風は「ビュウビュウ」。まるで自然物はすべて「声」をもつかのやうである。
このやうな擬声語、擬音語が高度に発達してゐるといふ点が、日本語の特徴である。幼児がこれらを最初から学んでくれば、虫や動物の鳴き声も自然音もすべて言語の一部として、言語脳で処理するといふのも当然かもしれない。あるいは、逆に、言語脳で処理するから、言語の一部として擬声語、擬音語が豊かに発達したのか?
いづれにしろ、自然音を言語脳で受けとめるといふ日本人の生理的特徴と、擬声語・擬音語が高度に発達したといふ日本語の言語学的特徴と、さらに自然物にはすべて神が宿ってゐるといふ日本的自然観との三点が見事に我々の中に揃ってゐるのである。
人種ではなく、母語の違ひ
角田教授の発見で興味深いのは、自然音を言語脳で受けめるといふ日本型の特徴が、日本人や日系人といふ「血筋」の問題ではなく、日本語を母語として最初に覚えたかどうか、といふ点で決まるとしてゐることである。
その端的な例として、南米での日系人十人を調査したデータがある。これらの日系人は一名を除いて、ポルトガル語やスペイン語を母語として育った人々で、その脳はすべて西洋型であった。唯一日本型を示した例外は、お父さんが徹底的な日本語教育を施して十歳になるまでポルトガル語をまったく知らずに過した女性であった。その後、ブラジルの小学校に入り、大学まで出たのだが、この女性だけはいまだに自然音を言語脳でとらへるといふ完全な日本型だった。
逆に朝鮮人・韓国人はもともと西洋型なのだが、日本で日本語を母語として育った在日の人々は、完全な日本型になってゐる。
かう考へると、西洋型か日本型かは人種の違ひではなく、育った母語の相違である可能性が高い。「日本人の脳」といふより、「日本語の脳」と言ふべきだらう。角田教授の今までの調査では、日本語と同じパターンは世界でもポリネシア語でしか見つかってゐない。
違ふがゆゑに独創的なものが生れる
日本語による脳の違ひとは、我々にとってどのやうな意味を持つのだらうか?
理論物理学者の湯川秀樹博士は、角田教授との対談でかう語る(後掲書(1)114頁)。
|
「つまり日本人はいままでなんとなく情緒的であるというていた。(西欧人が)論理的であるのに対して、より情緒的であるといっていたのが、構造的、機能的、あるいは文化といってもいいけれども、そういうところに対応する違いがあったということが、角田さんのご研究ではっきりしたわけです。 そうするとそこで私が考えますことは、その違うということを生かすという方向です。違うということは上とか下とかいうことではなくて、その違いということを生かす。 (中略)違うがゆえに独創的なものが生まれるのである。 西洋に比べてあかん、劣っているという考え方が根深くあったけれども、そういう受け取り方をしたら劣等感を深める一方です」 |
「違うがゆえに独創的なものが生まれる」とは、独創的な中間子理論でノーベル賞を受賞した湯川博士の言葉だけに重みがある。日本語の脳の違ひは人類の多様性増大に貢献してゐるわけで、「虫の音に耳を傾ける文化」などは人類全体の文化をより豊かにする独創的なものと言へる。
かうした「生きとし生けるもの」の「声」に耳を傾けるといふ日本語とともに歴史的に培はれてきた日本人の自然に対する敬虔な姿勢は、大局的に「宇宙船地球号」の中ですべての生命と共生していくために貴重な示唆を与へ得るものである。
受け継いできたこの「日本語の脳」の特性を、われわれが意識的に自覚把握して、その独創性をよりよく発揮していくことは、日本人の全世界に対する責務とも言へるだらう。
(1)角田忠信著『右脳と左脳』小学館 ライブラリー、平成4年
国際派日本人養成講座240号 - 一部改稿 -
12世紀のはじめ頃に成立した『今昔(こんじやく)物語集』に次のやうな話がある。大学寮において律令を講じる明法(みようぼう)博士に清原義澄(よしすみ)といふ者がゐた。その道において並ぶ者がなかった。年は70ほどで、世に用ひられてゐた。ある夜、この義澄の家に強盗が入った。義澄は板敷きの下に逃げ込んだから強盗は気が付かなかった。盗人たちは、家を思ふ存分に打ち壊し、わめき散らして去った。
義澄は板敷きを出て門まで走り、声をあげて、「おーい、お前ら、顔はしかと見たぞ。夜が明けたら警察に行って、お前たちを捕まへてもらふぞ」と叫んだ。これを聞いた強盗たちは引き返して、義澄をうち殺して逃げ去った。『今昔』の作者は、「義澄才(ざい)ハ微妙(めでた)カリケレドモ、露(つゆ)、和魂(やまとだましい)無カリケル者ニテ、此(かか)ル心幼キ事ヲ云(いひ)テ死ヌル也」と評した。
これから100年ほど遡(さかのぼ)る。『源氏物語』の話である。光源氏は息子夕霧の元服にあたって大学寮に入れて学問をさせたいと考へてゐた。祖母も夕霧も不満である。今風に云へば中学生になった夕霧は自分が学生のうちに、自分より年下の者が自分を追ひ越して昇進して行くのがたまらないのである。夕霧は、父はずゐ分つらいことをなさいます。このやうに学問せずとも高い位に昇り世に用ひられる人もありますものを、と恨み言を心の中で繰り返した。
夕霧は早く卒業をして、人とも交はり、立身もしたいと猛勉強をして四、五ヶ月のうちに史記などは読み終へてしまった。源氏は、試験に向けて、夕霧の師に予め試問をさせた。夕霧の答へは見事でいたらぬところはなく、さすがは源氏の君の血筋をひく方であると誰もが讃嘆した。
天皇の血筋をひく夕霧がわざわざ大学寮に行く必要は、夕霧も解ってゐるやうに、ないのである。では、なぜ源氏は息子を大学に入れたのか。―高き位の家のうまれた者として、栄達も思ひのままで、学問修行をするのはずい分遠回りのやうに思はれやう。が、権勢に媚びへつらふ者は、心服はせぬが追従しおべんちゃらを言ったりするから、機嫌をとられた当人はわが身を誤解して偉い者と思ひまちがひをしてしまふ。そして時移り、親に死なれて力が衰へてしまふと、人から軽くあつかはれることになる。だから、源氏はわが子を大学に入れようと思ったのである。―「才(ざえ)を本(もと)としてこそ、大和(やまと)魂(だましい)の世に用ひらるる方も、強(つよ)う侍(はべ)らめ」
ここに「才」とは漢才のことで大陸の文物制度に学んだ学問的知識に関するものをいふ。義澄が講じた律令もその一つであるし、夕霧が学んだ史記もその一つである。これに対して、「大和魂」(或は「和魂」)は生きた常識、生活の知恵で、日本人であれば当然のやうに身につけてゐるものなのである。源氏が「才を本としてこそ云々」といふのは、「大和魂」を夕霧は身につけてゐると考へてゐた。さう取れる。しかし博学で「才ハ微妙(めでた)」いといはれた老齢の義澄は世間の知恵も当然身につけてゐていいはずであるのに、「和魂」がないばかりに「心幼キ事」を言ふて殺されてしまった。
小林秀雄の『本居宣長』によれば、「やまと魂」とか「やまと心」とかいふ言葉は、文学史においては、平安期の王朝文学の中にしか登場しない。幕末に、例へば吉田松陰の『留魂録』にある「留め置かまし大和魂」のやうな武士道とともに用ひられた「やまと魂」或は「やまと心」とは意味合ひの違ふものなのである。
小林は、『今昔』と『源氏』の他にもう一つ平安中期の女流歌人赤染(あかぞめ)衛門(えもん)が「大和心」を詠んだ歌をも合はせて「人間は、学問などをすると、どうして、かうも馬鹿になるものか」と式部や赤染衛門とともに烈しい語調で慨嘆するのであるが、わが国民文化研究会主催の昭和四十五年の雲仙での全国学生青年合宿教室において、「男は学問にかまけて、大和心をなくしてしまってゐたのです。大和心をなくしてしまふやうに、日本人は学問せざるを得なかった。これは日本の一つの宿命なのです」(「文学の雑感」)と語ってゐる。
源氏がわが心を理解せぬ夕霧を思って、「学問などしてすこし物の心も得侍(はべ)らば、その恨みは、おのづから、解け侍りなん」と祖母に語ったが、作者式部にはその無理が解ってゐたであらう。源氏はかう考へるべきであった。―「大和魂を本としてこそ、才の世に用ひらるる方も、強う侍らめ」
「大和魂」を本とした全国学生青年合宿教室が今年は兵庫の淡路で開かれる。学生青年の参加をお待ちするものである。
(寺子屋モデル役員)
「並々ならぬ経緯」
小林秀雄先生の第5回目のご講義は、「感想―本居宣長をめぐって―」(昭和53年)である。合宿報告記『日本への回帰 第14集』には、ご講義内容と質疑応答が記載されてゐるが、質疑応答は要点のみである。「あとがき」に、編集委員の山田輝彦、小柳陽太郎両先生は、次のやうに記してゐる。
「特に今度の阿蘇合宿には、小林秀雄先生が大著『本居宣長』を完成されたあとの御多忙の中を割いて、遠い九州の地まで5回目の御出講をいたゞいたことは何ものにもかへがたい感激であった。さらに本書の編集にあたっては、当日の御講義の速記原稿をもとに、編集委員で作成した400字詰45枚の原稿の殆んどすべての頁にわたって、御心こもる御加筆をいたゞき、さらに先生御自ら校正の筆までおとりいたゞいたことは言葉に尽せないよろこびであった。このたゞならぬ先生の御厚志に御応へすべき道を求めて日々精進を重ねることが、私達に与へられた重大な課題であることをいましみじみと思はざるを得ない。」
以上、御出講の1回から5回までを通観すると、講義内容は、編集委員が速記録から要旨をまとめ、小林先生からご加筆・訂正をいただいてゐるのがわかる。質疑応答は、要旨だけを記してゐるもの、記載がないのもある。一部には、ご加筆・訂正の不明なものもあるが、総じて、先生のお目通しはいただいてゐたものと推測できる。
私が、ここで全5回の合宿報告記を見直したのも、「國武先生もご存じでせう」といふ池田雅延(まさのぶ)さん(新潮社の元編集者)の一言に注意を促されたからである。池田さんが書かれた文章がある。
「小林先生は、講演であれ対談・座談の類であれ、自分の話を録音することを固く禁じられていた。…講演も対談・座談の類も、速記原稿が届くや徹底的に手を入れ、自分が目を通していない速記の公表は決して許されなかった。録音じたいの拒否は、ひとつにはその録音が勝手に使われ、小林秀雄論など書かれたりしては困るからである」(『新潮45』小林秀雄とテープレコーダー・平成25年)
これは、一編集者の言葉ではない。小林秀雄先生の文章に毎日目を通して「弟子」となった人の言葉である。一字一句の表現に苦しみ、精魂を傾ける先生の姿を毎日見てゐた「弟子」の叫びともとれる。池田さんには、ご遺族と一緒になって抗議したい苦い思ひ出がおありのやうだ。勝手に録音テープから文字化して、小林秀雄はかく言った式の文章の独り歩きを懸念されたのである。
「だが、何人かの講演会主催者や編集者が、先生の逆鱗にふれるかもしれない恐怖と戦いながら、密かにテープを回していた。先生が亡くなられた後、こんどは話の中身はもちろんだが、先生の声と語り口は後世に伝えなければならないと思いきめた編集者の熱意と、それを諒とされたご遺族の英断によって、講演テープが世に送られた。それらは今日、「新潮CD小林秀雄講演」(全8巻)で聴くことができる。が、ここに至るまでの背後には、そういう並々ならぬ 経緯があったのである」(前掲の『新潮45』)
この池田さんの前後の文章をよく読むと、絶対に許されないものと、許されないことは承知の上で何とかお許しをいただきたいといふ強い願望、この二つの苦しい対立がある。しかし、この対立を乗り越えたのには、「並々ならぬ経緯」があったことがわかる。
『感想』刊行の事情と同じ決断
今回の『学生との対話』が企画された目的も、成功するかどうかの命運も、まさに「新潮CD」のときと同じである。とするならば、あのときはどうだったのか。「失敗」と先生自ら呼ばれ、刊行する意思のなかったベルグソン論『感想』はなぜ刊行されたのか、といふ疑問である。池田さんは、「今回と同じです」と応へられた。
「著者の没後十數年を經る間に、かつての『新潮』連載稿に據つて、著者を、あるいはベルグソンを論じる傾向が次第に顕著となり、もし現状で先々までも推移すれば、著者の遺志は世に知られぬまま、著者の遺志に反する形で「感想」が繙讀される事態は今後ともあり得るとの危惧が浮上した。よつて今般、著作権繼承者容認のもと、第五次全集に別巻を立ててその全文を収録し、巻頭に収録意圖を明記して著者の遺志の告知を圖ることとした。著者には諒恕を、讀者には著者の遺志に對する格別の配慮を懇願してやまない。」(第五次 「小林秀雄全集」別巻Ⅰ・巻頭の「緒言」から)
これは、未完のベルグソン論「感想」を特別に収録するに至った新潮社の「緒言」の言葉だ。これは、池田さんの言葉ではないのか。当時、私はこれを何度も読み返した。小林秀雄の愛読者は皆さうであったに違ひない。編集部の苦渋の決断を理解しようと何度も読み直した。その結果、愛読者はこの決断に拍手を送り、かつ改めて表現とは何かと考へ、襟を正された思ひがした。CD発売のときも、『感想』刊行のときも、そして今回の『学生との対話』の発刊企画も、すべて同じ苦渋の決断にある。
さあ、それだけにこれからが大変だ。池田さんは、「諒恕」と「配慮」を念頭に置き、万全の準備をしたうへで、著作権継承者の白洲明子さまのご承諾をいただくために全力を注ぐことになる。
「質問教育」の実態を伝へたい
その後、5冊の合宿報告記や小林先生のお顔のお写真などをお送りしたあと、7月、池田さんと楠瀬啓之(くすのせひろゆき)さんに国文研の事務所にまでご来訪いただき、打ち合せをした。楠瀬さんには、このとき初めてお目にかかった。40代の若い方だ。小林秀雄の文章には学生のころから強く魅かれ愛読してきたとおっしゃる。楠瀬さんが、これから始まる原本(テープ)のCD化も文字に起して活字化するのも、すべて担ふことになる。
磯貝保博さん(元講談社)は、ダンボールから骨董品を取り出すやうに、懐かしい古ぼけたオープンリール(テープ)を次々と取り出した。「小林先生以外にも、竹山道雄、岡潔、福田恆存、江藤淳先生のものなど沢山ありますよ」と言った。池田さんは、「〝常識について〟のテープは、まだ見つかりませんか」と訊く。磯貝さんは、「探しましたが見つかりませんでした」と残念さうに応へる。このテープだけが、いまだに行方不明なのだ。
池田さんは、今日お借りする四つの講義・質疑テープを、まずCD化し、活字化します、講義も何編かは載せたい、そして、すべての原稿を整へた上で、明子(はるこ)さまに読んでいただきご判断を仰ぐことになります、とおっしゃった。御帰りのとき、合宿教室参加者の「感想文集」や会員の「走り書き感想文」のいくつかをお渡しした。これからのお二人の仕事は、多忙を極めることになる。
私は、ただひたすら明子さまのご許可が下りることを祈ってゐた。そして、依頼されてゐた講義中の学生の姿を撮った写真を探してゐた。仲間は、そんな写真は持ってゐないといふ。困ってゐたら、小柳志乃夫さん(興銀リース)が、「親父(おやぢ)のところにあるかも知れない」と言った。福岡に帰省した折に探したら「ありました」といふ朗報。沢山のネガが見つかった。この中の一枚が採用され、『学生との対話』の本扉に載った(昭和53年阿蘇合宿。畳の大広間に全員が椅子に座って聴いている。前列に黒岩真一君、二列目に酒村聡一郎君の顔が見える)。
12月、待ちに待った池田さんからの電話がはいる。「明子さまから出版の同意をいただきました」といふ嬉しいお知らせ。年が改まり1月に池田・楠瀬さんにお会ひした。明子さまの同意が得られたといふのも、ひとへに池田さんへの信頼による。『感想』の第五次全集別巻収録以来、明子さまと一体となって事に処してきた池田さんであったからこそ、許されたのだ。『学生との対話』の「はじめに」に、その趣旨を次のやうに記されてゐる。
「今回ここに収録した学生たちの質問と小林氏の応答は、他に類を見ない小林氏の「会話教育」と「質問教育」の実態を、現代に、ひいては後世に伝えるべく、国民文化研究会と新潮社が、同会に残された音声を新たに文字化し、小林氏の著作権継承者である白洲明子氏のご検分とご容認を得て刊行するものです」。
「質問教育」とは何か。池田さんは、「若い人に質問せよといふ教育をしたのは、おそらく小林先生しかゐない。その成果がここにありありと残ってゐる。これが誰にも知られずに闇に去るのは、日本の精神文化のすぐれた礎(いしづゑ)が消え去るのと同じです」とおっしゃった。
池田さんは、きっとこの言葉で明子さまにご許可をお願ひ申し上げたのだと思ふ。ともあれ、今回の『学生との対話』が刊行されたことを喜び、その功績は、すべて池田雅延、楠瀬啓之さんにあったことを記し、感謝申し上げたい。
最後に、小林先生のご講義を聴いて詠んだ学生の歌をいくつか紹介したい。
先生の心つくして話さるるそのみ姿に胸のふるへたり(小林 至)
しばし目をつむり給ひて師の君ははるかに人を偲び給ふか(青山直幸)
かねてより師の御言葉にふれたしと思ひし願ひ今成れるかな(伊藤哲朗)
幾年も小林秀雄氏の書を読みて想ひし如くその顔はきびし(小幡道男)
先生の深き心を握りしめ身体にこめて持ち帰りたし(古川 修)
(了)
(昭和音楽大学名誉教授)
戦後の思想的昏迷の萌芽は戦前にあり!
昭和12年4月、東大法学部政治学科に入学した小田村寅二郎は、講義内容のあまりの欧米思想追随に強い違和感を覚える。もとより欧米思想を排せよといふのではない。聖徳太子の仏典研究に見られるやうに主体的に外来の思想文化を摂取して、自らの文化を豊かにして来た日本人の伝統的な態度に比して、東大の学風は欧米思想を無批判的に受け入れるだけではないか、「現実を直視せぬ思惟でいいのか」といふ根本的疑問である。その疑問から生ずる所信を年度末の「政治学」の答案に書いて提出する。担当は矢部貞治助教授。
これを機に師弟の間で往復書簡といふ形で論争が始まる(40余日間に6たび)。政治学は一生涯を通じて関心を持つべき重要な学問と先生は仰るが研究対象から「日本」が除外され国体との関係が不明徴である、人間は努めれば努めるほど自らの至らなさ不完全性を痛感するものだが「理想的な人格的完成」を政治原理の基礎に据ゑてゐる…。初めは困惑気味だった矢部助教授は、テキストの標題を『政治学講義要旨』から『欧州政治原理講義案』と改め内容も改訂する(第2章、第3章)。
本書は、東大を初めとする高等教育機関における欧米思想追随の学風を改革せんとした昭和十年代の「学生思想運動」の本質とその可能性を検証した画期的な研究書である。「昭和10年代は不自由極まりない『政治的に正しくない』言語空間だった」といふやうな戦後的な先入観では到底把握しきれない「時代の真相」に迫らうとしてゐる。著者は教育社会学・学生文化論の専攻で昭和48年生れ、京大大学院助手を経て関西国際大学准教授(一昨年4月から、帝京大学総合教育センター准教授)。
昭和10年代の「学生運動」といへば、当局に迎合的なものしか存在しなかった筈だといふのが、今日の一般的な認識であらう。丸山真男が昭和11年の「二・二六事件を契機としていわば下からの急進ファシズムの運動に終止符が打たれ」「これ以後の進展はいろいろジッグザッグはあつても結局は既存の政治体制の内部における編成がえであり、もつぱら上からの国家統制の一方的強化の過程である」云々と述べたことは本書でも触れられてゐる。勿論ここで取り上げてゐる学生思想運動はファシズムとは無縁だが、本書を読めば二・二六事件を契機に「下から」の民間の運動が終焉を迎へて以後は「上から」の一方的統制下におかれたなどといふ記述がいかに皮相なものかが明確となる。
「この学生思想運動は、欧米思想追随の高等教育や学術研究の実態を憂へる東京帝国大学の学生たちが、昭和13年6月に東大精神科学研究会を結成するところから始まる。
…中核メンバーのひとりが無期停学処分となった…事件をきっかけに、運動は全国に広がり、日本学生協会(昭和15年5月)および精神科学研究所(昭和16年2月)へと発展していく。…その過程で大学・学校当局と衝突し、文部省の文教政策を攻撃し、戦時体制の指導理念を批判するようになる。そして昭和18年2月のメンバー一斉検挙を経て、同年10月解散に至った」(はじめに)。
検挙の引き金となった「戦時体制の指導理念」批判、即ち、すべからく戦争は「終局を明示」して短期であるべし、「人間の能力には限度があり、長期間全力投入し続けることはできない」とする時局批判は、この学風改革の思想運動が人間の不完全性への深い洞察から発してゐることを物語ってゐる(第八章)。昭和10年代の東大(ことに法学部・経済学部)の学風が欧米思想追随であったといふことや、それを指摘した論文を学外誌に発表した学生が「学問の自由」「言論の自由」を口にする教授会によって無期停学処分を受けた事実(東大小田村事件)などは戦後的価値観では驚きではなからうか。
当時、指摘された「祖国憶念の情意の欠如」といふ東大の学問に見られた知的弊風は少しは改まってゐるのだらうか。むしろ占領統治による影響とも相俟って、改まるどころか官界・政界・経済界・教育界・報道界等々にまで広く蔓延してゐるのではなからうか。戦後の思想的昏迷の芽は、既に戦前に萌してゐることを本書は示唆してゐる。
(山内健生)
- 初出・『新日本学』第11号(拓殖大学日本文化研究所) -
第59回全国学生青年合宿教室
先人の〝詩と哲学〟に 生きるあかしを見出そう! - 言葉に学ぶ -
招聘講師
京都大学名誉教授 中西輝政先生
9月5日(金)~8日(日)国立淡路青少年交流の家
参加費 学生 22,000円 社会人 37,000円 申し込み締切迫る!
編集後記
「歯止めが必要だ」「限定的には許される」。自らをどう縛るかで妙な議論が続く。領土と国民を守るために、己の力と知恵を最大限に発揮する、万全を期して時に他国とも協力する。世界の常識ではないか。
(山内)