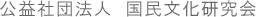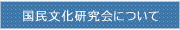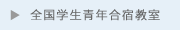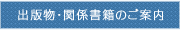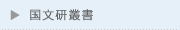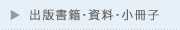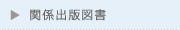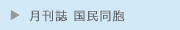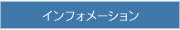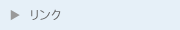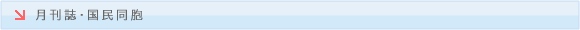
第632号
| 執筆者 | 題名 |
| 理事長 今林 賢郁 |
「青年の心」に火を点け、祖国再生の道を共に歩まう! |
| 山口 秀範 | 「慕はしき小田村寅二郎先生」 - 今こそ〝MAN TO MAN運動〟を - |
| 小柳 陽太郎 | (本紙昭和37年7月10日号所載) 古事記について - わが神々のいのちの奔流 - |
| 國武 忠彦 | 国民文化研究会・新潮社編 〝小林秀雄「学生との対話」〟刊行の経緯について |
上村和男前理事長の後任を拝命して2ヶ月余が経過した。今更ながら任の重さを思ひ、身の引締るのを覚える。昭和31年に設立された当会は来年60年を迎へる。長期間に亘り当会の事業に対し格別のご理解とご支援を頂いた皆様に先づ深甚の謝意を申し上げる。併せて小田村寅二郎先生の遺託を受けて、15年の間、当会の発展に尽力された上村和男前理事長に敬意と感謝の念を申しあげたい。
小田村先生は44年の長きに亘ってその任を担はれ、まことに鋭い批判精神と果敢な行動力で常にわれわれを導いて下さったが、先生は又、巧みなユーモアの心をお持ちの方で、在る事象を表現される時のことば遣ひは絶妙だった。
先生が60歳の頃、当時30歳から40歳代の、上村さん以下の世代
(私もその一人であったが)について、「上村君以下のヤング・オールド」と名付けられたのもその一つであらう。「上村君以下の諸君は、現役の学生ではないから『オールド』ではあるが、自分たちの世代からすれば20年以上も若い『ヤング』である。その『ヤング・オールド』の諸君たちが、社会に出てからも研鑽を重ねながら、ひとりひとりが思想活動を展開してゐる。このやうな諸君たちが今後とも輩出してくれれば必ずや『相続者層』となって自分たちの志をつないでくれるに違ひない」―このやうな先生のお心持が、この「上村君以下のヤング・オールド」には込められてゐたのではあるまいか。
先生がお亡くなりになって15年、われわれは先生をはじめ諸先輩方のご期待に応へることはできたのだらうか。来し方を振り返れば心底忸怩たる思ひが抜けないのであるが、一つだけ言へることがある。祖国再建に生涯を捧げられた先輩方の「志」を断じて絶やしてはならぬ―この一点だけは片時も忘れることはなかった。その思ひをこもごも胸に抱きながら歩んできた。嘗ての「ヤング・オールド」たちも今や高齢の域に近づいた。道統の継続が急がれなければならない。30代、40代の会員諸兄の奮起を期待して已まない所以である。
本会が営む「全国学生青年合宿教室」は、今年の「淡路島合宿」で59回を迎へる。この59年といふ長い歳月、われわれ国文研に連なる同志たちが全国の学生、青年たちに訴へ続けてきたのは、未だに国民の心を呪縛し続けてゐる敗戦後遺症を克服し、真正の独立主権国家としての矜持を取り戻して貰ひたい、そして、青年ひとりひとりの胸の内に、祖国日本を活き活きと蘇らせながら堂々と生きて行って欲しい、といふことだった。
われわれの思想活動は、一人が一人に立ち向ひ、語りかけ、問ひかけ、心を通ひ合はせる中に同信の友を獲得すること―小田村先生が言はれた「マン・ツー・マン運動」―にある。一人の青年の心を動かすことが出来れば、その動き出した心は、必ずやまた一人の青年の心を動かすに違ひない。このことをお互ひの胸に刻みながら、更なる研鑽を重ねよう!、聖徳太子のご思想を学ばう!、心を鍛へるためにしきしまの道に取り組まう!、そのやうな思ひがあらためて胸をよぎるのである。
若き日に先生方に導かれながら、「学問・人生・祖国」をおのが身に受け止め、それを総合的に把握して、揺るがぬ生き方を求めた、あの立志の日々に今一度思ひを巡らし又一歩を踏み出さう。ひとりひとりの更なる一歩が、国を支へる礎のひとつになることを信じ、大らかに、朗らかに歩み続けやうではないか。
祖国再建の道はなほ厳しいが、われらは心ひとつに大御心を仰ぎ、「み民われら もろともに まめやかに わが大君に 仕へまつらむと 誓ひまつらむ」(戦時中、先輩方が神前に奏上してゐた「のりと言(ごと)」。三井甲之先生作)と心に反芻しながら、ご皇室のご安泰と祖国再生の道を同信諸友と共に進みたいと思ふ。
皆様の全面的なご支援を心からお願ひする次第である。
ご縁を頂く
毎年この季節になると、ありし日の事どもが思ひ出され慕はしさで一杯になる。6月4日は、本会初代理事長・小田村寅二郎先生のご命日、師逝きて15年が過ぎようとしてゐる。学生時代から計り知れない学恩を受けた不肖の弟子の一人として、また本会の事務局長を務めたご縁により最晩年の先生のお傍近くで文字通り謦咳に接した後輩として、改めて小田村先生が遺して下さったもの、次代に託された願ひなどの一端をたどってみたい。
御母堂に明治の日本を仰ぐ
大正3年東京にお生れの先生が、吉田松陰のお血筋を引くことは広く知られてゐる。学生時代に2年間住まはせて頂いた港区芝白金の「正大寮」は先生の御母堂治子様の持家だった由で、毎月格安の家賃をお届けしたが、その折に美味しいお茶をご馳走になるひと時は「ああ、この方が松陰先生の妹さんのお孫さんなのだ」と、幕末に思ひを馳せる貴重な機会でもあった。「台湾近代教育の父」と今も讃へられる六士先生のリーダー格・楫取道明は先生の祖父に当るわけで、道半ばで非業の最期を遂げた道明の遺児が私の眼前の矍鑠たる老婦人だといふ事実は、明治の日本をたちまち身近なものにしてくれたのである。
お母様は先生を「寅さん」と呼ばれて頼りにしてをられた。日ごろ私たちには何事も的確に、厳しく指図される先生が、懇(ねんごろ)に孝養を尽され「はい、はい」と母の教へに従っていらっしゃるお姿を、松陰先生とその母・滝さんに重ね合はせて拝見するのは楽しみであった。
親思ふこころにまさる親ごごろけふの音づれ何ときくらむ
といふ人口に膾炙した松陰先生の歌は、私にとって小田村先生母子を追慕するよすがともなってゐるのである。
学園紛争のさ中で
半世紀近く前の昭和43年、私が大学生として上京する時に高校時代以来の恩師・小柳陽太郎先生から「小田村先生にご挨拶に行くやうに」と促され、銀座7丁目松坂屋デパートの裏手にあった小さなビルの一室を緊張しつつお訪ねした。『追悼 小田村寅二郎先生』の追憶の記にも書いたが、先生の机の前に墨痕鮮やかに自筆された次のお歌があったことが今も記憶に新しい。
義宮様のお歌
テレニュース見つめ給へる父君の御顔(みかほ)はくもるストの叫びに
当時全国の大学では熾烈な反体制運動が展開されつつあった。私が銀座の事務所を訪ねたのは入学式から二ヶ月ほど経った頃かと記憶するが、その時点で早稲田大学の正門には学生たちによるバリケードが築かれて全学封鎖状態に陥ってゐた。革命成就のためには手段を選ばずと尖鋭化して行く学生紛争の根本課題は、実は戦前に端を発する大学の思想的混乱にあると先生はお考へであった。
昭和12年に先生が入学された東京帝国大学の憲法学講座で、一年間天皇統治に全く触れられぬままであったといふご自身の体験は、所謂「小田村事件」となって先生のその後の人生を決定づけることとなるが、爾来日本の国の歴史と伝統に則った学問が大学に確立しない限りは、次代を担ふ学生青年に真の生き甲斐を与へることは出来ないとの信念を貫かれて、本会の「合宿教室」発展継続に心血を注がれたのである。
混迷を深める大学の様子が天皇陛下のお心をお悩ませしてゐるといふ義宮様(現在の常陸宮殿下)のお歌を、小田村先生は昭和の民として心から申し訳なく受け止められ、大学学風の改革に一層の尽力をお誓ひなさったものと拝察するのである。当時大学に入りたての私に充分理解出来たわけではないが、他に掲示物もないどちらかと言へば殺風景な事務所の壁に、かなりの期間掲げられ毎日拝してをられた先生のご心中を改めて偲ぶのである。
同級生丸山真男の学問
戦後の進歩的文化人や左翼学生たちにとって理論武装の指導者と目されて来たのが、東大教授の丸山真男であった。小田村先生はこの丸山と東京府立一中の同級生で、自宅を行き来する親しい友人同士だったらしい。しかし大学時代久しぶりに訪ねた丸山は、既に東大法学部に奉職してゐたが、小田村学生を思想的対立者として冷徹に遇したとのこと。
昭和44年の夏に「第1回全国学協リーダーズゼミ」と銘打って開催された合宿に講師として招かれた先生は、右のやうなエピソードを枕としつつ丸山論説批判を縦横に開陳された。参加学生の一人だった私は、その日の会場の緊迫感を今も忘れてゐない。大多数の学生にとって、今を時めく丸山真男批判を初めて耳にした衝撃は相当大きかったに違ひない。講義録を読み返して今も目を開かれる点が多く、丸山流の勉強方法を指摘した次の箇所は殊に印象深い。
| 「丸山氏の生き方といふのは、自分のポケットに入れた物差しの目盛りが、歴史の必然性とか、ヘーゲルの弁証法とか、唯物史観とかいふ目盛りになってゐる物差しで、その物差しを取出して徳川時代の思想、社会、政治を測り廻ります。しかし、なかなかその物差しの目盛りに合ふものが見つからない。しかし、見つからなくとも決して後退はしない。その目盛りに合ふものがないなどといふ筈はないんだ、といふ心情的励みに支へられながら、いよいよ熱を上げて捜し廻る。鵜の目、鷹の目で〝微視的探索〟に没頭する」 |
つまり学問の対象物に、心を空しくして自分の方から飛び込んでいくのではなく、予め持ってゐる目盛り付きの物差しで対象物を測ることに夢中になる。例へば西洋流の理論で日本の歴史や思想を理解したつもりになることは、長く我が国の学問の通弊だったが、その代表格として丸山真男を俎上に載せたご講義はとても新鮮だった。更にこの〝微視的探索〟を敷衍してかう続けられる。
| 「しかし、これは科学における作業や、顕微鏡で物を見る〝精密さ〟とは違って、作業に従事してゐるご本人の中にそれを見つける熱情が溢れんばかりに横溢してゐますから、心情的作用が常に優先することになります。そのために、その〝微視的探索〟自体もついつい対象全体において、あるがままに把握することが乱れがちになり、つい〝虚視的探索〟になってしまったり、〝針小棒大な敷衍〟が始まったり、更には〝真実に対しては目をつぶってゐながら、つひにその不覚に気づかずに大切な対象の所を素通りしてしまふ〟といふやうな間違ひをも犯しがちになってしまふのです」 |
人の心や民族の歴史を扱ふ学問を人文・社会科学と呼ぶが、科学してゐるつもりの研究者は自分の物差しに合ふ現象だけを選び出す作業に没頭してあるがままの事実から目を逸らす(〝虚視的探索〟)といふ、学問へ取り組む姿勢の誤りに先生は警鐘を鳴らし続けられたのである。
〝心〟を鍛へる教育
合宿教室での先生のご講義演題は時として大変長いものだった。曰く
●「われわれ人間は自分ひとりで生 きてゐるのではない」
●「学問と教育をそれぞれの正しい軌道にのせるために」
●「〝畏敬の心〟を身につけずんば日本国民にあらず」等々。
これらを通じて先生は学生たちに、古今の人々との触れ合ひの中で〝心〟を鍛へて欲しいと願はれた。「〝心〟を鍛へる教育を」と題された次の一文はそれを端的に伝へてゐる。
| 「徳育とは、一人びとりの少国民の〝心〟を鍛へていく教育にほかならない。〝心〟を鍛へるとは、少国民たちが、やがて成人して大人になったとき、その対人関係における〝心のくばり方〟をはじめ、社会の一員としての自覚自制力、国家を構成する一員としての祖国存続への使命感などを体得させることであり、それらが幼いうちに養はれていってこそ、『教育を受けた人』にふさはしくなるのである」 |
家族、組織、社会そして国民の一員として如何に身を処するかといふ心の鍛へ方が出来てゐるかと、まづ自らに問ひつつ、同時に一人でも多くの「次代の少国民」を育成することが、小田村先生の学恩に報ひる道であらう。
今林賢郁新理事長の下で会員相互に励まし合ひながら、先生の提唱された〝MAN TO MAN運動〟に立ち返ることが今こそ求められてゐる。小田村先生に直接指導を受ける機縁のなかった30代会員の間で、先生方の戦前からの運動を綴った『昭和史に刻むわれらが道統』(小田村先生の御著書)の勉強会(「興風会」)が始まってをり、その成果に大いに期待したい。我々が「道統」を継がずして誰が次代に繋ぐのかといふ自覚を確かめ合ふためにも、59回続いてゐる「合宿教室」に一人でも多くの会員諸氏が、心新たに足を運んでもらひたいと願はずにはをられない。
毎朝神棚の前で唱へる「み民われら もろともに まめやかに わが大君に 仕へまつらむと 誓ひまつらむ」(三井甲之先生作)も小田村先生から伝授頂いたものである。記紀万葉の昔から一筋に連なる日本の国柄の中に生きる喜びを共有できる世界、それを先生は「国民同胞感」と教へて下さった。
(本会常務理事・(株)寺子屋モデル代表)
(編註)標記の小柳陽太郎先生の御論考は52年前のものであるが、国文研の学問的思想的道統の深さを示すもので、今日なほ瑞々しく読む者の胸に迫ってくる。
一昨年は古事記成立1,300年であったが、あらためて先生の御論考を通して、「古事記の説き示す世界」を仰ぎたい。
若き日に一度は必ずふれておかねばならない書物、それを一冊あげてくれと問はれた時には、私は躊躇することなく〝古事記〟をあげたいと思ふ。何故か、勿論古事記は日本の民族が生んだ最古の古典である。そのやうな意味で、古事記は僕らの心のふるさとであるといへよう。だが私が古事記を必読の書物に数へる所以は、単に甘美な、牧歌的な夢を古事記に懐(いだ)くためではない。古事記といふ書物は郷愁といふやうなニュアンスを越えた、人間の根源に僕らの生命を導いてくれるものだ。
また一方古事記を、天皇制の成立を合理化する古代氏族の政治意識の所産とみる考へがある。このやうな見地からすれば古事記は一つの政治的立場を主張するものにすぎないし、日本の民族の伝統的なイデオロギーを代表する書物であるといふことになるだらう。たしかにこのやうな考へは、戦後の思想界を風靡したし、そのために、古事記は教科書の中からはすべて抹殺され、ただ僅かに古事記の中の断片をとりあげて、その文学的な価値を問題にされるにすぎないといふ憂き目を見るに至ったのである。
だが古事記とは単なる政治思想の表現ではないし、まして天皇制擁護のための戦術の書物ではない。むしろそれは政治的な一つの立場などといふ限定された世界から僕らを解き放って、自然の鼓動の中に人間の生命を、投げ入れ、溶しこんで、人間そのもののありのままの姿を僕らの前に示す、いはば啓示の書物、予言の書物としての価値を示すものに他ならない。天皇を中心とした国柄といふものも、かかる波瀾動揺の人生の中から自らに生れ出たものであることに注目しなければならない。
以下古事記の本質について、私なりに思ひついた感想を述べてみたい。
精一杯に生きるいのち
第一に古事記といふ書物は、僕らの祖先が最高度に力を傾けて生きて来た、他に類を見ない魂の記録であるといふことに注目したい。スサノヲノミコトが母イザナミノミコトを慕って、「青山は枯山なす泣き枯らし、河海は悉(ことごと)に泣き乾(ほ)」したといふことはあまりにも有名だが、古事記の神々の行動には、歎きも、喜びも、怒りも、恋も、戦も、更に嫉妬も、復讐も、いはばすべての人間的感情が、何のわだかまりもなく、奔騰してとどまるところを知らない。人々はこれを無邪気と呼び、これを古代人独特の素朴さのせゐにするやうだが、単に、素朴とか無邪気とかといふやうな言葉では到底表せないものがある。子供の無邪気さは、たしかに大人の心をうつ。しかしそれは僕らのいのちを根柢からゆさぶり、僕らに生きて行く本源的な力を与へてはくれない。
これに反して古事記の神々の感情の奔流は僕らをして人間本来の姿に立ちかへらせ、そこに無限に沸き出る力を与へてくれるのである。その一つの現れとして、古事記の世界は、如何に感情が交錯し、はげしい動乱の人生を展開しても、その行きつくところはまことに爽やかであるといふ事に注意したいと思ふ。
スサノヲノミコトはあまりに母を慕ひ泣き叫んだために、父親イザナギノミコトの怒りにふれて追放された後、然らば自分の心情をアマテラスオホミカミに訴へようとして、高天原に上って来る。その時の様子を古事記は「山川悉に動(とよ)み、国土皆震(ゆ)りき」と形容してゐる。その暴風雨のごとく荒れ狂ふ神は再び高天原から地上に放たれ、ここで有名な八岐(やまた)の大蛇(をろち)を退治されたあと、クシナダヒメを妻として、須賀の地に到って、「あれここにきて、あが御心すがすがし」とのたまひ、須賀の宮を造って例の「八雲立つ出雲八重垣、妻ごみに八重垣つくる、その八重垣を」といふ歌をよむのである。善も悪も、そのすべてをつき動かして進んでゆく、生命のはげしさ、そのゆきつくところに生れる「スガスガシ」といふ言葉のもつ無限の感触、これこそが古事記ならではふれることのできない世界である。
戦争中よく叫ばれた「撃ちてしやまむ」といふ言葉も、あの時代はその言葉だけをとり出して、何か金属的なひびきをもって国民の感情をかきたてたけれども、
みつみつし久米の子らが、垣下に
植ゑし椒(はじかみ)口ひひく吾は忘れじ撃ちてしやまむ
といふ古事記の歌謡の全体に接した時には、人間の全存在をゆるがす激情に、まことに大胆にこの身を委ねた古代の勇士たちが、それこそ一分の隙もなく、僕らの前にそそり立ってゐるのを見ることが出来る。ここだけではない―反省も許さぬ、分析も許さぬ、さういふ完璧な人間の姿を、僕らは古事記のいたるところに、無数にばらまかれた神々の中に見ることが出来るのである。精一杯に生きてゆく、そこにすべてがある。「神」とは精一杯に生きるいのちのあり方に名附けたものだ―何だかさういった方がふさはしいやうである。
古事記の世界はこの生命の拡りが、稀有のスケールで空間を埋めつくしたところに他に比類のない価値がある。日本民族に与へられた生命の行動半径の可能性を示した書物―それが古事記であると私は思ふ。
ヤマトタケルノミコト
次にこれと表裏の関係にあるが、古事記の世界にわづらはしい道徳的な反省や分析が、姿を現さないといふことは重要である。ヤマトタケルノミコトが熊襲を征伐したとき、逃げてゆくクマソタケルの背中をつかんで、剣を尻より刺し通し、熟瓜(ほぞち)の如く振り断って殺したといふ場面があるが、その豪快な行動の中には、じめじめした反省の影は全く見られない。かうして大和に凱旋したミコトは再び東国遠征の旅に上られるのであるが、その時ミコトはこのやうに帰ってきてどれ程の日数もたたないのに、東国にむけて追ひうつやうに出発せしめられるのを思へば、きっと天皇は私が早く死んだ方がよいと考へてをられるにちがひない―なほあれ早く死ねと思ほしめすなりけり―と叔母にあたるヤマトヒメミコトのもとで泣くのである。この場面を日本書紀では「臣(やっこ)労(いた)はしけれども、ひたぶるにその乱れを乎(ことむ)けなむ」と雄(をた けび)誥(をた けび)して出陣したとなってをり、ここでもやはり「労はしけれども」といふ言葉が注意されるが、天皇の命に対し、胸中にわだかまるかなしみをそのままに、表現して憚らない古事記の描写は、日本書紀に比しても遙かに率直であり、外的な道徳的な反省にしばられることなく、波打つミコトの激情が人間的な温みを伴って、僕らの胸に迫るのである。ミコトはその戦ひの果に、剣を尾張にある妃ミヤズヒメのもとに置いたまま、よろめく足をひきずって大和をさして帰る途上ノボノにおいて崩ぜられるけれどもその悲劇的な生涯を貫くものは、人生のあらゆる危機において、それを回避することなく全力を傾けて生きることの荘厳さを身をもって示されたところにあった。今自分がやってゐることは一体何か、その意味を考へる余裕などはない。或はそれは誤ったことかもしれない。しかし今のこの空虚を埋めつくし、この瞬間を、何らかの行動をもって表現しつくす以外に生きる術はない。このかけがへのない荘厳を、精一杯生きてゆく以外に一体何が可能だといふのか。―そのミコトの心情は、高天原で横暴の限りをつくしたスサノヲノミコトにも、或はまた、父親スサノヲノミコトの髪の毛を悉く梁(はり)に結びつけて、スセリヒメを奪って黄泉国(よもつくに)をのがれ去ったオホクニヌシノミコトにも、そのまま通ふところの、侵すことの出来ない威厳に満ちた生命の表現であった。ミコトの魂は、その後八尋(やひろ)白(しろ)智鳥(ちどり)となって、あてどなく天に向って飛び去ってゆくのであるが、この荘厳な魂の遍歴は、日本の民族のある限り語り伝へらるべき永遠の叙事詩でなければならない。
混沌から統一へ
ともあれ古事記の世界には、今僕らが使ふ意味での善、悪といふ道徳的基準を見出すことは出来ない。現に、古事記には無数の神々が生れてゐるが、その神々は、例へば西欧の神話におけるが如く、善神、悪神の区別はない、まして神と悪魔といふやうなはげしい対立の観念は絶無である。
では神はどこに生れるのか。それは生命が、その全き姿をもって燃焼する時、換言すれば生命が統一を得た時、又は統一せむと意志した時、その時神は生れ出るのである。
| 「国稚(わか)く浮きし脂(あぶら)の如くしてくらげなす漂へる時、葦牙(あしかび)の如く萌えあがるものによりてなりませる神の御名は、ウマシアシカビヒコヂノカミ」 |
混沌から統一へ、分裂から集中へ、
その意志のきざすところ、そこに神は生れる。「なんとすばらしい葦の芽のいのちよ」その讃美がそのままで神のみ名になり得るのである。従って僕らの民族にとって、善、悪の区別とは、強いて言へば統一と分裂、意志と怠惰に名附けられたものであった。日本には「エホバ」の神はゐなかった。絶対神は存在しない。従ってモーゼの十戒のごとき絶対の価値判断といふものもまたあり得ぬのである。そのやうな外的な、先験的な基準によって裁断され得ぬもの、それが人生のありのままの姿である。混沌から統一へと盛り上り、それがまた混沌へと崩れゆく生命の進行過程をそのままに認めるところに、僕ら日本民族の人生観、世界観の出発点があった。ウマシアシカビヒコヂノカミといふ神の名はその意味においてまことに象徴的である。
「ひと筋をふみて思へば」
僕らは何故古事記を読まなければいけないのか。最初に出した問ひについて、要約すればその答へは左の通りである。即ち人生のありのままの姿は何か、そしてそれが統一へと盛り上る刹那のはげしさとは一体どのやうなものか、それを最大限の逞(たくま)しさで語りかけてくれるもの、それが古事記なのである。だがここで注意しなければならないことは、語りかけてくるものに対する僕ら自身の用意でなければならない。即ち僕ら自身が素直に人生の波瀾に身を投げ入れ、そこに生命の統一をめざす意志がなければ所詮古事記といふ書物も僕らとは無縁であるといふこと、このことに深くおもひをひそめるべきではなからうか。
明治天皇の御歌に
ひと筋をふみて思へばちはやぶる神代の道も遠(とほ)からぬかな
といふのがあるが、この一すぢをふむ「意志」なしには、古事記は僕らの胸に永久に蘇り得ぬのである。戦ひの日において、命を捧げて国を護った人々を、僕らは神々として祭ったけれども、民族防護のために、命を捧げるといふ、その厳粛な生き方の中に、僕らはまざまざと統一への意志がそのまま神となるといふ古事記の世界を実感し得たのである。しかしながら戦ひ敗れた今、僕らにはこのやうな統一の実感から日々遠ざかりつつあるのが偽らぬ現状である。この分裂と怠惰の日に古事記を読むといふことが如何に至難なわざであるか―しかし敢へてこのやうな日々であればある程、古事記を単なる古典文学としてではなく、生命の指標として読むべき意義もまた切実な民族の要請であるといはなければなるまい。
(福岡県立修猷館高等学校教諭)
- 現在、本会参与 -
3月28日、『小林秀雄 学生との対話』(新潮社)が発売された。快調な売れ行きで、5月の初めで五刷りとなった。わづか1ヶ月余りで、こんなに売れるとは、いまだに小林秀雄先生の存在の大きいことを物語ってゐる。
表紙には、小林先生の全身像の写真が載ってゐる。鎌倉の由比が浜の海を背に、穏やかに微笑むやうな表情で、正面を向いて立ってゐる。遠くから寄せくる波は光り、コートはフラノ生地のラグラン。今にも話しかけてくる感じがする。
表紙には、「国民文化研究会」と「新潮社」の共編と書かれてゐる。驚いた人もゐるかも知れない。そこで、この本の刊行の経緯について、少し記してみたい。
50余年ぶりの小林邸
2年前、私は鎌倉での『古事記』の講演会(主催・鎌倉の教育を良くする会、山内裕子さん主宰)でお話したことが縁となり、関口靖枝さんがお世話する〝北鎌倉輪読会〟(於・円覚寺伝宗庵(でんしゅうあん))で、小林秀雄著『本居宣長』(新潮社)の輪読を始めた。伝宗庵では既に平成十九年の春から隔月で小柳陽太郎先生の『名歌でたどる日本の心』の輪読が続けられてゐたといふが、そこに新たに月1回の『本居宣長』の輪読会が加はったのである。両者のメンバーはほぼ同じで、私は主に後者に関与することになった。昨年5月、『本居宣長』輪読会が終ったとき、参加者の山内隆治さん、須郷信二さんのお二人から、「池田さんがお会ひしたいさうです」と声を掛けられた。
山内隆治さんは両方の輪読会のメンバーである浜崎祥江さん(鎌倉在住)のお嬢さんと知り合ひで、浜崎さん宅を訪ねた際、書棚にあった大部な『本居宣長』に目を留めたことから、伝宗庵での『本居宣長』輪読会をお知りになり須郷信二さんを誘って参加されてゐたのであった。
「池田さん」とは新潮社の元編集者の池田雅延(まさのぶ)さんのことで、池田さんは脳科学者の茂木健一郎さんの依頼で、3年前から鎌倉の旧小林秀雄邸(例の「山の上の家」)で塾を開き、毎月1回、小林秀雄著『本居宣長』の本を読んでをられるとのこと。山内隆治さん、須郷信二さんはその会の参加者である。
6月23日、鎌倉駅前で初めて池田さんにお会ひした。私よりもお若く、山内さん、須郷さんも来られてゐて、私も含めて4人は、タクシーに乗って、鶴岡八幡宮裏にある小高い旧邸へと向った。八幡宮を左に曲がり、坂を上りはじめると50余年前のことが思ひ出された。小田村寅二郎先生とやはりタクシーに乗ってこの道を通った日のことを。あの日は少し雨がふってゐた。私は手に〝聴講記〟(合宿教室での御講義を記録したもの)を持ってゐた。タクシーを降りて、坂を上ると右手に旧邸が見えてくる。門も玄関も昔のままだ。ひっそりと静まってゐる。
池田さんの案内で、邸内に入る。黒いタイルの玄関。すぐ右が書斎と応接室。応接室は、16畳ほどの広さだらうか。もっと広いかも知れない。柔らかい絨(じゅう)緞(たん)。客間の庭に面したところにテーブルと椅子が置いてある。「この椅子に座られて、先生のお話をお聞きしたのではないですか」と池田さんが訊く。テレフンケン製ステレオが見える。いまは、直してCDで聴くとのことだ。
改めて『新潮―小林秀雄追悼記念号―』を手にして
皆さんは、私の本(『日本の文化・歴史の心ばえ』)も読み、国文研や合宿教室にくはしかった。私が大学生のとき、小林先生に質問したことを話しはじめたら、途端に山内さんは携帯を取り出して、その時の私の音声を流し始めた。「新潮のCD・小林秀雄講演は、大変よく売れました。これを聴いて、小林秀雄がわかり始めた、本を読むようになったといふ人は多いのです」と池田さんはおっしゃる。
池田さんは、昭和45年、23歳のときに新潮社に入社。翌年の夏、小林秀雄先生の本を造る係りを命じられ、昭和52年に菊版の『本居宣長』を造り、以後「全集」の本造りにも精魂を傾けた。販売定価を抑へた第4次全集から、平成14年の堅牢・重厚な永久保存の愛蔵版といはれた第5次全集(生誕100年を記念して出版)。さらに同じ年の秋から第6次全集 (全作品を新字体・新仮名遣ひにして、脚注を付けた普及版)をスタートさせた。これら全ての本造りに挺身された。若いときに小林先生から親しく文章の手ほどきをうけられた方だ。
池田さんは、小林先生は「宣長」の執筆に12年半かけてゐるのだから、少なくともそれだけの年数をかけて読みたいとおっしゃる。そんな穏やかではあるが、信念をおもちの方であった。お話をお聞きしてゐると池田さんが、『新潮―小林秀雄追悼記念号―』(昭和58年4月5日発行)をよく読まれてゐることが判る。小林先生から厚い信頼を寄せられてゐた菅原國隆編集長の下で編集に携はれてゐたからだ。小林先生は3月1日に死去されたので、この「追悼記念号」は約1ヶ月で完成してゐる。いま手に執って見ても編集者たちの喪失感、悲しみが伝はってくる。
私は、当時この「追悼記念号」の巻頭を飾る文章を見て驚いた。サブタイトルに「未発表講演」と銘打って、「信ずることと知ること」が掲載されてゐたからである。「編集部」の筆によるその〝まえがき〟を読んでみよう。
| 「信ずることと知ること」は評論集『感想』(小社刊)の巻頭を飾る名エッセーだが、ここに掲載する同名の一文はその原型ともいうべきナマの講演である。氏は国民文化研究会主催の大学生のための夏季九州合宿に前後5回も出かけ、そのつど、何百人という学生と膝を交えて語ってこられた。極力、講演を避けられた氏としては異例であり、真剣な若者たちをいかに愛していたかというあかしでもあろう。これは昭和49年夏の講演だが、氏の朱も入って会報誌への発表を許可されたものである。こういう生きた講演が、同じ語り口ながら、本の中では、いかなるエッセーに書きなおされていくか、それを知る上でも貴重な資料となるだろう。 |
さらに驚いたのが、次に掲載されてゐる「小林秀雄と学生たちとの問答」である。同じく「編集部」の手による〝まえがき〟の一部を紹介する。
| ここに「信ずることと知ること」の講演のあとの質疑応答以下、5回にわたる小林氏と学生たちとの問答の一部を特に独立させて一挙掲載するが、けだし峻厳にして慈悲深い小林氏の「物の考え方」を学ぶ上でも格好の入門書たりうるのではないだろうか。こういう扱いを許された国民文化研究会にも謝意の意を表したい。 |
この二つの〝まえがき〟は、編集長の菅原さんがお書きなったものと思はれる。五回の合宿教室での質疑応答が抜粋ではあるが、国文研の「合宿報告記」から転載されてゐる。国文研とは何か。合宿教室とは何か。世の注目を浴びたはずだと思ふ。だから、それに答へるかのやうに小田村寅二郎先生(「20年余の御縁をいただいて」)や合宿教室に何度も出講されてゐる木内信胤先生(「野球と国語」)の追悼文が「追悼記念号」に掲載されてゐる。これらのことから、新潮社の菅原さん池田さんたちと小田村先生との間には、十分な面識があったことを窺ひ知ることができる。
「学生との問答を本にしたい」
さて、池田さんのお話に戻る。昨年、平成25年の早春、新潮社の若い編集者たちから、小林先生の没後30年を記念して先生の本を出したいとの相談を受けられたとのこと。そのいくつかのプランのなかで、楠瀬(くすのせ)啓之(ひろゆき)さんといふ若い編集者が、〝小林秀雄と学生との対話〟を本にしたいと言ってきた。まだ40歳代の方である。「追悼記念号」を、読まれて浮んでのヒントではないか。その着眼に池田さんも乗った。日ごろから、小林先生にとっての「対話」の重要性を考へられてゐた池田さんが、これを見逃すはずはない。しかし、「学生との対話」が文字化できるのか。可能なのか。そこで、まづ私に会ってみよう、といふことになったのだといふ。池田さんは私に尋ねた。
追悼記念号に載ってゐる「小林秀雄と学生たちとの問答」は、全てか、抜粋か。抜粋であれば、まだ掲載されてゐない問答の数々が、原本(テープ)には残ってゐると考へられる。残ってゐれば、その全てを収録の方向で編ませていただきたい、と。私は「全てではありません、抜粋です」と答へた。
池田さんは、もう一つ訊いてきた。小林先生は、ご自身が手を入れない話し言葉の原稿は、無断で公表することは絶対許されなかった。この方針を、お嬢さんの白洲明子(はる こ)さまは著作権継承者として、しっかりと堅持されてをられる。そこで、お尋ねしますが、国文研の「合宿報告記」記載のご講義の後の質疑応答の部分も先生のお目通しをいただいたものなのか。國武さんとの質問の部分などにも、先生が手をお入れになってゐるのでせうか、と。「さうです」と私は答へた。ただ、国文研刊行の「合宿報告記」記載の問答は全てではありません。一部です。しかし、掲載の問答は、先生のお目通しをいただいてをります、と。
「追悼記念号」記載の問答は、「合宿報告記」からの抜粋である。しかし、「合宿報告記」の問答は全てではない。原本(テープ)には、まだ先生の貴重な言葉が残されてゐる。この際、その言葉を取り出し活字化したい。これが、池田さんや楠木さんの願望である。
私は、この着眼を喜び、問答を本にしたいといふお二人の着想に大賛成はしたが、さて、乗り越えなければならぬ課題は多いのである。
(次号につづく)
(昭和音楽大学名誉教授)
編集後記
「憲法に基づいて政治を行う立憲主義にとどまるべきだ」「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」「憲法改正が筋だ」等々、憲法解釈の変更によって集団的自衛権容認を目指す首相の方針を各紙は論難する。彼ら言論人には「領土」を守護する意思も意欲もないのだ。だから尖閣危機の現実を前にして猶「集団的自衛権は憲法上許されない」などと空論を吐くが、憲法を見直せ!とは決して言はない。「志」を喪失した議論は輿論を惑はし百害あるのみだ。
今林新理事長は本会の歩みを回顧しつつ「大らかに祖国再建の道を共に歩まう」と呼びかける。ご精読下さい。
(山内)