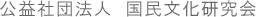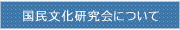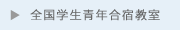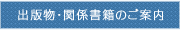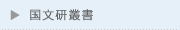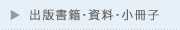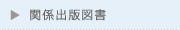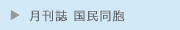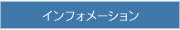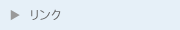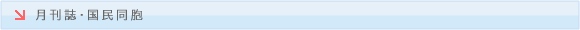
第631号
| 執筆者 | 題名 |
| 武田 有朋 | 合宿教室では「後藤新平の足跡」を語りたい! - 〝導入講義〟を担当することになって - |
| 柴田 悌輔 | 長谷川三千子著『神やぶれたまはず』を読んで - 三島由紀夫の『英靈の聲』『憂國』について - |
| 布瀬 雅義 | 日台は運命共同体である - 李元総統は「日本人よ、武士道を忘れるな」と語った - |
| 廣木 寧 | 「昭和五十二年 秋の満開」 - 小林秀雄著『本居宣長』の刊行 - |
| 新刊紹介 |
今年の合宿教室(9月5日から8日、於・淡路島)で導入講義を担当することになった。浅学の身には甚だ荷が重いと思ひつつ思案してゐたが、後藤新平を取り上げようと思った。
私が後藤新平に強く惹かれるやうになったのは、学生時代の平成15年11月、国文研から台湾へ派遣して頂いたことがきっかけであった。後藤は台湾総督府の民政長官として、欧米にも負けない近代的な都市の建設や産業の育成を行ったといふ人物である。台湾訪問で、現地の方々の「今日の台湾があるのは日本のおかげだ」といふお話を伺ひ、強い興味を抱いていった。
後藤は「大風呂敷」と渾名されてゐたさうで、都市計画のスケールの大きさが魅力的だ。一例を挙げると、後藤は明治32年度国家予算の5分の1(約4000万円)を台湾向けに確保し、近代化を進めた。台湾を去った後も満州や東京で大規模な都市計画を行ってゐる。特に関東大震災後の帝都復興を、内務大臣として担ひ、文明国の首都に相応しい都市づくりに尽力した。
このスケールの大きさもさることながら、後藤の魅力はその仕事振りにあるやうに思ふ。こんな人と共に仕事をしてみたい、といふ思ひがするのである。
後藤の仕事振りの特徴は、①徹底的な調査、②若手の積極的な登用の二点だと思はれる。
元々後藤は医師であり、行政官としての経歴は内務省衛生局から出発してゐる。明治23年に著した『衛生制度論』では、「衛生制度ヲ実施スルニハ、世態、人情、風俗、職業ノ変遷ト比照シテ考察ヲ加フコトヲ忘ルヘカラス」と述べてをり、後藤の調査を重んずる姿勢は、医師としての経歴も大きいと思ふ。
また、若手の登用といふ点においては、これはと目を付けた人物を後藤自らが口説き、登用したさうである。主に30代の若手を実力本位で登用し、自由に手腕を振はせたとのことである。後に『武士道』を著した新渡戸稲造も、後藤からの再三の勧誘によって台湾に渡り、製糖業の育成に尽力してゐる。
後藤は癇癪持ちで、部下を痛罵することもしばしばであったらしい。しかし、元来根に持たない性格なのか、一旦痛罵した相手にも直後に何事もなかったかのやうな態度で接して、相手を驚かせてゐたさうだ。この性格により、部下からは大層慕はれていたさうである。
後藤の最晩年の取り組みである「政治の倫理化」にも強い興味を抱いてゐる。これは、①当時の政界では政党同士が党利党略に陥ってゐて国民愁眉の問題を閑却してをること、②その根本原因は物質万能主義にあること(更に物質万能主義による中毒が社会主義思想であるといふこと)、の二点を指摘し、「物質万能主義の偏傾を矯めて、之れに日本文化の伝統たる精神的要素を加へて、以て、日本の安全なる途を開拓」することを目指したものであった(後藤新平講演録『政治の倫理化』より)。そして、我が国の歴史上、党派の争ひにより国難に遭遇する度に偉大なる人格者が現れてこれを救済することを指摘し、その最も顕著なる例として聖徳太子を挙げるとともに、17条憲法を国家政治の根源としてゐるのである。後藤が政治の理想に聖徳太子を挙げてゐるのが、非常に興味深く感じられる。
この演説が行はれたのは、大正15年(1926)のことである。我が国の現状を鑑みるに、後藤が約90年前に指摘した問題点は悉く当てはまるやうに思はれる。そして、この現状を変へていく基となるものが聖徳太子の御言葉であるといふことが、私たちに力を与へてくれるやうに思ふのである。
最後に、合宿の準備をしながら、小柳陽太郎先生の「歴史を学ぶといふことは、人物ととことん付き合ふことだ」といふ御言葉を思ひ出してゐる。合宿に向けて、後藤新平の足跡を辿っていきたいと思ってゐる。
(NTT西日本、数へ34歳)
はじめに
昨年夏刊行された長谷川三千子氏の著作、『神やぶれたまはず』を読んで以来、「神とは何か」について、改めて考へてゐる。少しばかり以前、本居宣長の『古事記傳』に暫くの間親しんできた。その折、上古の日本人が抱いてゐた「神(カミ)」の古意についても、隨分と考へさせられた。今回は現代にあって、天皇に「神」を感じる心といふのは、あり得る思想なのだらうか。現代では非常識とも思はれる、そんな考へがわが心を占めてゐる。その事を記してみたい。
「神としての天皇」 - 宣長と重なる三島 -
長谷川氏は『神やぶれたまはず』といふ著書の題名は、折口信夫氏が戦後に創った詩、「神やぶれたまふ」に由来すると冒頭で述べてゐる。それなら「やぶれたまふ」か「やぶれたまはず」かの違ひはあっても、長谷川氏と折口信夫とでは、「神」の意味の捉へ方が一緒である。つまりこの著書の題名にある「神」とは、「現御神としての天皇」を意味してゐると、私には思へた。
『古事記傳』の「神代一之巻(カミ ヨノ ハジメ ノ マキ)」で、「カミ(迦微)」の古意について宣長はかう語ってゐる。
|
「凡て迦微とは、古御典等(イニシエノフミド)に見えたる天地の諸(モロモロ)たちを始めて、其(ソ)を祀(マツ)れる社に坐(マシマ)ス御霊(ミタマ)をも申し、又人はさらにも云ず、鳥獣(トリケモノ)木草のたぐひ海山など、其余(ソノホカ)何(ナニ)にまれ、『尋常(ヨノツネ)ならずすぐれたる德(コト)のありて』可畏(カシコ)き物を迦微とは云なり」 《※宣長の註すぐれたるとは、尊(タツト)きこと、功(イサオ)しきことなどの、優(スグ)れたるのみを云に非ず。悪(アシ)きもの奇(アヤ)しきものなども、よにすぐれて可畏(カシコ)きをば、神と云なり。さて人の中の神は、先ずかけまくもかしこき天皇(スメラミコト)は、御世々みな神に坐(マシマ)スこと、申すもさらなり》 |
長谷川氏の著作を読み終へた時、私は「人の中の神は、先ずかけまくもかしこき天皇は、御世々みな神に坐スこと、申すもさらなり」といふ宣長の一節を思ひ出してゐた。
「神としての天皇」を主題とするなら、長谷川氏の著書の内から、第八章「三島由紀夫『英靈の聲』」を取り上げざるを得ない。この章で取り扱はれるのは、三島の晩年の作品、『憂國』と『英靈の聲』である。前者の主人公は、二・二六事件の青年将校の神霊であり、後者のそれは、大東亜戦争における神風特攻隊の英霊である。そしてその主題とは、天皇が持つ「神」としての属性といっていい。
三島は天皇についてかう語った事がある。
| 「日本の天皇には、勿論人間としての属性はあるが、日本人にとつては、天皇は神としての属性をも、兼ね備へてゐる」(「文化防衛論」新潮社刊) |
この一節は、先に引いた宣長の文章と、意味が重なり合ふ。戦後、日本では「人間天皇」といふ言葉が、一世を風靡した。「天皇には神としての属性がある」といふ三島の思想は、そんな「戦後民主主義」の時代では、異端そのものといへるだらう。
戦後の空虚と偽善性…
第8章で長谷川氏は、三島由紀夫の性格について、こんな表現をする。
「しかしここでも、告白するやう な顔をしてかくし、かくしながら ひそかに告白する、といふ彼の習性はかはつてゐない」
「ここでも」といふのは、三島のデビュー作『假面の告白』を長谷川氏が意識するからである。それにしてもこの短い文章は「言ひ得て妙」とでも言ひたくなる程、簡潔で、見事な三島由紀夫評になってゐる。確かに三島の文学には、いつも表と裏がある。
長谷川氏がいふ通り、三島は昭和20年8月15日といふ「特別な瞬間」について、直叙形では語ってはゐない。だが三島には、『私の遍歴時代』(昭和39年 講談社刊)といふ随想集的な著書がある。その中に「8月21日のアリバイ」と題する、短い一文(昭和36年8月21日「読売新聞」初出)がある。この短い随想は、次の二行で始る。ちなみに三島は大正14年生れで、昭和20年に20歳になってゐる。
| 「二十歳の私は、何となくぼやぼやした心境で、終戦を迎へたのであつて、悲憤慷慨もしなければ、欣喜雀躍もしなかつた。その点我ながらまことにふがひなく思つてゐる」 |
かう書く三島は、「終戦の日」の瞬間を意識的に無視しようとしてゐる。だがこれにも三島特有の文章の反転があって、それが締め括りの二行に現れてゐる。
| 「当時すでに私の心には、敗戦と共に躍り上がつて、思想の再興に 邁進しやうとする、知的エリート たちへの、根強い軽蔑と嫌悪が芽生えてゐた」 |
三島は戦後の日本人の思想が、天皇の「神格」を否定する事で、空虚で偽善性を帯びてしまった事に、ひどく腹を立ててゐた(『林房雄との対話』昭和41年 番町書房刊)。
人間であらせられる その深度のきはみにおいて…
では三島の思想にあっては、「天皇」とは「神」であると本当にいへるのだらうか。三島は『憂國』の中で、二・二六事件の青年将校の神霊たちに、かう語らせてゐる。
| 「こは神としての御心にあらず、人として暴を憎みたまひしなり。(中略) このいと醇乎たる荒魂(アタミシマ)より人としての陛下は面(オモテ)をそむけ玉ひぬ。 などてすめろぎは人間となりたまひし」 |
重臣たちを殺された事で、怒りを覚えた天皇は、「神としての御心」ではなく、人としての暴力を憎む心に支配されてゐたと見る。その事実を指して、神霊たちは「などてすめろぎは人間(ヒト)となりたまひし」と、昭和天皇に対して嘆く。この嘆きは、当然著者三島の嘆きでもある。だが三島由紀夫は、天皇の人間としての属性までをも否定はしない。『英靈の聲』の中で、三島は特攻隊員の英霊に、かう語らせてゐる。
|
「昭和の歴史においてただ二度だけ、陛下は神であらせられるべきだつた。何と云はうか。人間としての義務(ツトメ)において、神であらせられるべきだつた。この二度だけは、陛下は人間であらせられるその深度のきはみにおいて、正に、神であらせられるべきであつた」 二度といふのは、二・二六事件と、敗戦の時である。この文章で注目すべき一節がある。 「人間(ヒト)としての義務(ツトメ)において、」である。 |
さう語る文章に、私は三島の真意を感じる。三島の思想にあっては、やはり宣長のいふ通り、時には「天皇は神に坐(マシマ)ス」であって欲しいのである。
8月15日の「残酷な実感」を決して直叙形では語らない三島由紀夫であっても、三島の性格に由来する曲折した心情の吐露に、長谷川三千子氏は充分に気付いてゐる。
英霊たちの発する「鬼哭としか云ひやうのない、はげしい悲しみの叫び」、つまりは慟哭をこのやうに描き出したといふ事は、三島由紀夫も又、敗戦を「怖ろしい残酷な実感」として、共有した一人であったと、長谷川氏は語る。私もその通りと思ふ。
『英靈の聲』『憂國』と終戦の詔勅」
それに私はもうひとつ付け加へたい。大東亜戦争を終らせた昭和天皇の「終戦の詔書」のお陰で生かされた日本人は、戦後の時代に何をして、或いは何を考へて生きてゐるのか。戦後の日本人の精神生活ほど、三島にとって腹立だしいものはなかったのだらう。
『英靈の聲』も『憂國』も、戦後の日本人に、昭和天皇の「終戦の詔勅」を思ひ返へさせる為の、三島由紀夫の渾身を込めた著作だった。それを思へば、天皇は「神」であるといふ思想に、私は納得する。長谷川三千子氏の著作で、私はそんな気持になった。戦争を継続する事で、日本の国民をこれ以上犠牲にはしたくはない。そんな昭和天皇の御心を書き綴ったのが、「終戰の詔勅」である。詔書の最後は次のお言葉で締め括られる。
| 宜(ヨロ)しく挙國(キョコク)一家(イッカ)子孫(シソン)相(アイ)傳(ツタ)へ、確(カク)く神州の不滅を信じ、任重くして道遠きを念(オモ)ひ、総力を將來の建設に傾け、道義を篤(アツ)くし志操を鞏(カタ)くし、誓て國體の精華を發揚(ツヨク)し、世界の進運に後(オク)れざらむことを期すべし。爾臣民其れ克(ヨ)く朕が意を體せよ。 |
御名御璽
「神」でなければ書けない「美しく」、「胸を博つ」文章である。三島の文学の特徴は、「美しいもの」への賛歌といっていい。三島はこの二つの作品で、「神に坐(マシマ)す天皇」への賛歌を語ったと、私は考へたい。そして「神としての天皇」としての、最期のお言葉が、「終戦の詔勅」であった。
((株)柴田取締役社長)
「台湾は日本の生命線だ」
「いまだかつて、私は『尊敬できる日本』といふ言葉を聴いたことがありません」とは、元台湾総統の李登輝氏が、東京青年会議所60周年記念フォーラム(平成21年9月、於・日比谷公会堂)で約2000人の聴衆に向って語った言葉である(1)。
総統退任後、残された人生を台湾人、そして日本人を励ますために使ふと話してゐた李登輝氏だが、87歳(当時)の高齢にして、心臓に持病を持つ身でありながら、まさに自分の命の限りを尽して、日本の青年たちに語りかけてゐる。氏を駆り立ててゐるのは何なのか?
永山英樹氏のブログ『台湾は日本の生命線!』には、李登輝氏は「…日本に対し、増大する中国の軍事的脅威から東アジアを防衛するため、日台が「運命共同体」「生命共同体」であることを繰り返し訴へ続けてゐる。「台湾は日本の生命線だ」「台湾が中国に取られれば日本は終わりだ」とあった(2)が、李登輝氏が最も日本人に伝へたかったことは、「かつてのやうな智恵と勇気に溢れる日本と言ふ国を取り戻せ」といふことであったはずだ。日本人を激励してゐるとしか思へない。
「君は君、我は我なり、されど仲良き」
李登輝元総統は今回の講演では、「竜馬の『船中八策』に基づいた私の若い皆さんに伝へたいこと」と題して、幕末に坂本龍馬の提示した近代日本の国家像に倣(なら)って、今後の日本の あるべき姿を語った。
たとへば、「船中八策」の第4の「外国の交際広く公議を採り、新に至当の規約を立つべき事(外交は公論に従って、新たに対等の条約を結ぶ)」に基づいて、李登輝氏はかう説いてゐる。
|
「アメリカへの無条件の服従や中華人民共和国への卑屈な叩頭外交、すなわち頭を地につけて拝礼するような外交は、世界第二位の経済大国の地位を築き上げた日本にそぐわないものです。特に、これからの日本と中華人民共和国との関係は、『君は君、我は我なり、されど仲良き』という武者(むしゃの)小路(こうじ)実篤(さね あつ)の言葉に表されるような、『けじめある関係』でなければならないと思います」(1) この言葉から思ひ起されるのが、李登輝氏の総統時代の対中外交である。 「たとへば、私の総統時代、中共から絶えず激しい挑発を受けました。すると、台湾の国民も大きく動揺して、『とにかく恭順の意を表しておこう』という者や、『いや徹底的に戦って相手を屈服させよう』という者など、さまざまな人々からさまざまな反応が出てきます。こういうときにこそ、もっと大局的な視座からもっと大きな判断を打ち出すのが、民の上に立つ者の務めだと痛感しました。…台湾に対しても中共は絶えずミサイルなどで脅しをかけてきます。しかし、それぐらいでぐらつくほど『新台湾』はひ弱ではありません。 あんなものは、単なるブラフ(編註・脅し)にしか過ぎない。大陸は、台湾に対して八十発ぐらいのミサイルを重要な個所に撃ち込めると言っています。しかし、私たちは、それに対する態勢も十分に完備していますから、文字通り「備えあれば憂いなし」で全く恐れてはいないのです」(3) |
中共のミサイルなにするものぞ、と立ち向ふ李登輝氏の姿は、まさに日本の古武士の姿を見るが如くである。
李登輝氏の新渡戸との出会ひ
右の(3)は、李登輝氏が新渡戸稲造の英文著書『武士道』を解説した本『武士道解題』の一節である。この英文『武士道』は、新渡戸稲造が日清戦争後、国際社会にデビューした日本の精神伝統を説くために、明治33年(1800)、アメリカで刊行されたものである。
時のアメリカ大統領セオドア・ルーズベルトは徹夜でこの本を読破し、感動のあまり、翌日ただちに数10冊を購入して、世界中の要人に「ぜひ一読することを勧める」といふ献辞を添へて送り、ホワイトハウスを訪れる政・財・官界の指導者たちも手づから配ったといふ。
この4年後に勃発した日露戦争で、日本軍は「武士道」に則った戦ひぶりを見せ、世界を感動させた。乃木将軍や東郷元帥が日本古武士の典型として国際社会からの尊敬を受けた。ルーズベルト大統領も日露講和の仲介を買って出た。
その新渡戸の著書に、どうして李登輝氏が関心を持ち、自ら日本語で直接、それも300頁以上もの解説書を書くことになったのか。
昭和15年、日本統治下の台湾で、旧制の台北高校に進んだ李登輝青年は、図書館で多くの書物を読み漁ってゐるうちに、新渡戸の講義録を見つけた。
新渡戸は『武士道』を刊行した翌年、明治34年に台湾総督府の農業指導担当の技官として赴任し、台湾製糖業の発展に大きな貢献を為したのだが、毎年夏に台湾の製糖業に関係してゐる若き俊秀たちを集めて講義をしてゐた。それはイギリスの思想家トーマス・カーライルの哲学書を解説した講義だったが、その講義録を読んで李登輝氏は新渡戸の偉大さに心酔するやうになり、新渡戸の著書をすべて読んで行った。その過程で出会ったのが『武士道』だった。
「公義」
中国からのミサイルの脅しに対して、敢然と立ち向ふ姿は、いかにも勇ましい武士らしき姿だが、新渡戸稲造が説き、李登輝氏が解説する「武士道」とは、そのやうな「勇」一辺倒のものではない。
新渡戸は、武士道の徳目の第一に「義」を挙げてゐる。「義」とは「義務」であり、「義理」すなはち「『正義の道理』がわれになすことを要求し、かつ命令するところ」と言ふ。孟子が「義は人の路なり」とし、キリスト教で「義」は神からの要求であるとするのも、同様の意味である。
李登輝氏は「義」は「個人」のレベルに閉ぢ込めておくべきことではなく、必ず「公」のレベル、すなはち「公義」として受け止めなければならない、と説く。それは社会のために各人が為すべき事を指す。
人の生き方として実践を重んずる武士道は、「義」について抽象的哲学的にあれこれと論じたりはしなかった。それよりも「義を見てせざるは勇なきなり」の一言で、武士としての生き方を表現した。武士道の二番目の徳目である「勇」とは、あくまで「義」を実践する時の姿勢であって、「義なき勇」は「匹 夫の勇」(思慮分別なく、血気にはやるだけのつまらない人間の勇気)として、軽蔑された。
「義を見てせざるは勇なきなり」
新渡戸稲造の生き方そのものに「義を見てせざるは勇なきなり」があった、と李登輝氏は説く。
| 「新渡戸稲造先生が台湾に来てくれるよう要請されたとき、彼はまだアメリカにおり、健康状態もかなり悪かった。しかし、『義を見てせざるは勇なきなり』の武士道精神に基づいて、総督府の一介の技官(地方の課長)という大して高くもないポストに従容(しょうよう)として赴き、いったん現地に入ったからには命を賭して大事業の成就に向かって全力疾走を続けたのです。なぜなら、国家がそれを必要としていたからです。これこそ、「武士道」の精華であらずして何でありましょう」(1) |
李登輝氏自身の生き方も同様である。進学先を決めるときにも、何の迷ひもなく、新渡戸稲造がかつて教授を務めたことのある京都帝国大学の農学部農林経済学科を選んだ。立身出世のためなら、東京帝国大学で法律を学んでエリート官僚となる道を選ぶこともできた。しかし、台湾の発展のためには、新渡戸と同じく農林経済を学ぶべきだと考へたのだらう。
しかし、天は李登輝氏に学者としての道を歩ませなかった。
| 「私事にわたりますが、もともと学者か伝道者として生涯を全うしようと思っていた私が、思いがけなくも政治の道への足を踏み入れてしまったのも、いまにして思えば、『天下為公』(編註・ 天下をもって公となす。天下は公のもの)『滅私奉公』といった武士道精神に無意識のうちに衝き動かされてのことであったように感じられてなりません」 |
「中華人民共和国」といふ擬制
李登輝氏に政治家への道を歩ませた一因は、祖国台湾を覆ふ中国の脅威であった。
|
「そもそも、「中華人民共和国」という擬制そのものが、根本的に嘘ではないですか。孫文の『三民主義』を実現するための国家体制であると広言しながら、かつて民主主義的だったことがありますか? 『人民』に対して自由や平等を許容したことがありますか。天安門事件にしても、チベット抑圧政策にしても、法輪功弾圧にしても、すべてが独裁国家的で、冷酷かつ残忍なことばかりしてきている。いったい、何万人、何百万人の無辜の民を殺してきたというのですか」(3) |
この「中華人民共和国」が、「祖国統一」といふもう一つの「擬制」のもとで、「台湾は中国固有の領土」「同じ中国人どうし」といふ「嘘」をつき、台湾併合を狙ってゐる。
|
「私は、これまで一度たりとも『統一には絶対反対する』などと言ったことはありません。中国の指導者が嘘をつくのをやめ、本当に自由で民主主義的な体制をつくるようになれば、いつでも統一に応じる用意がある、と言い続けてきたのです。それまでは、台湾の人々のために、万民のために、一国の責任ある指導者として『特殊な国と国との関係』という現実を維持しないわけにはいかない、とだけ言ったきたのです。 それなのに、彼らは自己権力を保持し拡大したいということばかりに気をとられて、最も大切な国民の自由や幸福を追求する基本的な権利まで、一方的かつ完全に踏みにじってしまっている。そして、このような、ごく当たり前の「公義」を述べる私のことが目障りで恐怖心さえ覚えるからでしょうか、平然と虚偽に充ちた個人攻撃を仕掛けてきている」(3) |
中国の独裁政権は国家を私し、国民を搾取してゐる。台湾の民をそんな体制に住まはせるわけにはいかないといふのが、李登輝氏の「義を見てせざるは勇なきなり」なのである。
「公義」と「友愛」
87歳の高齢にして病身の李登輝氏が、中国の反発と日本政府の抵抗を押し切って来日し、日本の青年に語りかける姿も、同じく「義を見てせざるは勇なきなり」の心からであらう。
中国の独裁体制による脅威といふ点では、日本と台湾は運命共同体である。台湾が中国の支配下に入れば、西太平洋は「中国の海」となり、海上輸送のライフラインを握られた日本は中国に膝を屈せざるを得なくなる。そのやうな日台両国民の不幸を避けるために、李登輝氏は高齢を押して、台湾と日本の人々に語り続けてゐるのである。
氏の講演の直後発足した民主党政権の鳩山由紀夫首相は「友愛」を掲げ、首相就任後、初の訪中で「今までややもすれば米国に依存しすぎていた。これからはアジアの一員としてアジア重視でいきたい」旨を語って脇の甘さを見せてゐた(これがこの一年後の中国漁船のわが巡視船への体当り事件に繋がり、さらにこの事件の対処を誤って、周知の如く尖閣危機を増大させてゐる)。自国民を弾圧し、ウイグルやチベットなど他民族の土地を簒奪する中国に対する無警戒ぶりは常軌を逸してゐた。
李登輝氏は、「公義」を基盤とする武士道精神には「仁」、すなはち「惻隠の情」があり、孟子はこれを「井戸に落ちようとしている幼児を救おう」とする人間なら誰でもが持つ心、と説いてゐる。「公義」を根幹とし「惻隠の情」を持つ政治家なら、「友愛」は中国政府ではなく、自由を奪はれてゐる中国人民、そして土地を奪はれ民族文化を破壊されつつあるウイグル人、チベット人に対してこそ示されなければならない。「義なき友愛」は「匹夫の友愛」である。民主党内閣は問題外であったが、これまで、ことさらに台湾を軽視してきた歴代の自民党政権の対中姿勢も大きく転換しなければならない。
そうした「義に基づいた惻隠の情」による外交を展開することで、初めて国民の安心安全を確保し、国際社会の中でも「尊敬できる日本」になっていけるのである。
蔵にあるものは蔵から出せば良い
国内の諸問題についても、同様である。李登輝氏はさらに語ってゐる。
| 「しかるに、まことに残念なことには、一九四五年(昭和二十年)八月十五日以降の日本においては、そのような『大和魂』や『武士道』といった、日本・日本人特有の指導理念や道徳規範が、根底から否定され、足蹴にされ続けてきたのです。…いま日本を震撼させつつある学校の荒廃や少年非行、凶悪犯罪の横行、官僚の腐敗、指導者層の責任回避と転嫁、失業率の増大、少子化など、これからの国家の存亡にもかかわりかねないさまざまなネガティブな現象も、『過去を否定する』日本人の自虐的価値観と決して無縁ではない、と私は憂慮しています」(3) |
武士道は、我々の先人が七百年の時間をかけて国民精神の 根幹として育て上げてきたものである。それを戦後の六十余年ほど、我々は「お蔵入り」させてゐたわけだが、蔵にあるものは蔵から出せば良い。
| 李登輝氏は『武士道解題』を次のやうな言葉で結んでゐる。「最後に、もう一度繰り返して申し上げておきたい。日本 人よ自信を持て、日本人よ「武士道」 |
を忘れるな、と」。
(在米国 会社役員)
(1)愛知李登輝友の会ブログ「【李 登輝講演録全文】竜馬の「船中八策」に基づいた私の若い皆さんに伝えたいこと」
(2)「李登輝氏、帰国―日本人はこの人物をたった一人で戦わせていいのか」、永山英樹氏ブログ『台湾は日本の生命線!』
(3)李登輝『「武士道解題」ノーブレス・オブリージュとは』小学館文庫
- 国際派日本人養成講座六一五号・一部改稿 -
1
大学生のときに(昭和52年)、小林秀雄氏が雑誌「新潮」に11年半にわたって連載した「本居宣長」が一年の推敲を終へて出版された。函に入った布張りの分厚い本が忘れられない。本は秋10月の末に出たが、見返しには奥村土牛(とぎゅう)氏の山櫻が満開であった。宣長が遺書に、わが奥津城(おくつき)には山櫻を植ゑるやうにと指示した、その山櫻を、小林氏は宣長に手向けたに相違ない。
『本居宣長』は刊行当初、4,000円といふ高価な値段でありながら、よく売れたさうである。僕は刊行後すぐに購(あがな)った。なにしろ四百字詰原稿用紙千枚の大作であるから、しばらくはあちこちを拾ひ読みしてゐたやうに覚えてゐる。読み始めたのがいつだったかは忘れてしまったが、刊行からさう経ってゐなかったやうに思ふ。
2
十月の半ば、江藤淳氏は『本居宣長』の校正刷りを通読して、小林氏との対談「『本居宣長』をめぐって」に臨んだ。江藤氏が『本居宣長』に中江藤樹、伊藤仁斎、荻生徂徠などといふわが国近世の学問の雄たちが取りあげられてゐることに触れて、「あの時期にきわまっていたのではないかという気がして来ました。あれに匹敵するようなまねびというか、学問探求の楽しみや喜びを、明治以来100何年間果してわれわれは経験し得たのか」といふ感慨を発すると、小林氏が「宣長にとって学問をする喜びとは、形而上なるものが、わが物になる喜びだったに違いない」と語り、「(現代の)学問が調べることになっちまった」と深い歎きを語るのである。
『本居宣長』は現代の学問への挑戦なのだが、それはわが国の伝統的学問からの挑戦でもある。小林氏はかうも江藤氏に語ってゐる。「訓詁(くんこ)ということが昔の言葉にあるけれども、いまの学問は訓詁から全然遠ざかって、こちら側からの新解釈を求めるのに急になった。それから見ると私のは、宣長の文章の訓詁の仕事なんですよ」
作者がみづからいふ「訓詁」の上になされた『本居宣長』に僕は不思議な印象を覚えた。往時、読み進む僕に、これは僕のために書かれた、といふ感触を与へ続けたのである。このことは誰にも話さなかった。不遜の言とみなされるのが必至と思ったからである。
ところが、面白いことが起った。昭和55年の暮れに福田恆存(つねあり)氏が「小林秀雄の『本居宣長』」といふ文を発表したのである。僕は早速読んだ。
《私は全文を実に楽しく読んだ。筆が滑(すべ)るといふ言葉があるが、私は読み滑る事を絶えず警戒した。良薬は口に苦い筈(はず)だ、全文がかうも抵抗無く流れるやうに胸に落ち入るといふのは、何処(どこ)かに読み誤りがあるのではないか、我が田に水を引く類(たぐ)ひの過ちを犯してはゐはしないか、さう自戒しながらも、一方では、この本をこれだけ読み熟(こな)せるのは私だけではないかといふ、これは自惚(うぬぼ)れとは全く異(ことな)る、一種の喜びに絶えず浸ってゐた。自惚れは他者との比較を前提とする、が、私の頭には他人は存在しない、私の前にゐるのは著者だけである。》
さうなのだ。『本居宣長』を読み進みながら、他との比較を絶して、実によく解るといふ感触が「僕のために書かれた」といふ言葉になったのだ。それを福田氏は「この本をこれだけ読み熟せるのは私だけではないか」と表現したのだ。作家の安岡章太郎氏が、「本居宣長」の連載が終りつつあるころ、小林氏との対談「人間と文学」(昭和51年10月)の中で、「ちゃんと続いてきちっと読んでいるわけではない」と断った上で、「拝見しますと、非常に言葉が澄んでいますね」と感想を語ってゐるが、この「非常に言葉が澄んでいます」も福田氏や僕の感触と同趣旨のことを語ってゐるのであらうと思ふ。文は、澄むと、鏡となり、見る人の心をそのままに映すのだ。
3
『本居宣長』には、昭和30年代の中ほどから「本居宣長」の連載がはじまる前年の39年まで「文藝春秋」に連載された、わが国近世の学者たちについての哲学的エッセイともいふべき「考へるヒント」にも取りあげられた人たちがあらためて考へられてゐるが、『本居宣長』の文体と『考へるヒント』の文体が違ふのである。書く対象は同じながら、『考へるヒント』には、「これは僕のために書かれた」といふ感触を覚えないのである。これはどこから来るのか。―『本居宣長』を贈呈された遠藤周作氏は同書に〝信仰的認識〟を読み取ってゐる。小林氏は、宣長の『古事記伝』を読んだとき、キリスト教は解らないが、「これならわかる」と国民文化研究会主催の合宿教室で講義をした際に語ってゐる(『小林秀雄 学生との対話』)。『本居宣長』は小林氏の祈りなのである。
((株)寺子屋モデル 世話役)
伊藤哲朗著 『国家の危機管理 -実例から学ぶ理念と実践 -』
(株)ぎょうせい 刊 2,300円
この度、東京大学客員教授(生産科学研究所)の本会会員・伊藤哲朗氏が標題の著書を刊行された。
著者は、昭和47年4月、警察庁に入り要職を歴任。平成18年に警視総監を拝命し、平成20年には内閣危機管理監に就任して、福田、麻生、鳩山、菅、野田の各内閣で内閣危機管理監の重責を担ってきた。
3年前の東日本大震災はもとより、新型インフルエンザへの対処、口蹄疫への対処、放射能汚染水の放出問題、さらには領海内での国籍不明潜水艦発見事案など、国内秩序の根幹を揺るがせかねない多くの事態に直面した筆者ならではの実践を踏まへた著書である。
刊行元発行のチラシによれば、本書の特色は次の3点にある。
◎危機に直面した際、どのような考えで、何を優先して対処すべきなのか。危機に備えて日頃からなすべきことは何か、について体系的に解説!
◎クライシスマネジメント(緊急事態対処)の根底となる考え方を考察し、自治体、警察、消防、自衛隊等の組織や民間企業の危機管理に通じる理念と危機対処のために実践すべき行動を明示!
◎著者が経験あるいは目撃した自然災害やパンデミック(世界的な感染の流行)等の数多くの危機事例を、失敗事例も含めて紹介し、陥りがちな陥穽の数々と、これらを避けるために行うべき具体的事例を実務に役立つよう項目ごとに解説!
本書で採りあげてゐる事例の一部を記すと左のやうになる。
・豚由来新型インフルエンザ発生時の対応
・阪神淡路大震災時の交通規制と人命救助
・大規模地震時の公助の限界
・領海内国籍不明潜水艦発見事案
・口蹄疫発生時の初動対応
・東日本大震災時の県市町村の役割
・津波ハザードマップの危険性
・放射能汚染水の放出
・言霊信仰が訓練を妨害
・アルジェリアの天然ガス関連施設での人質事件 等々
危機管理の責任者としていつ何時、何が起るか予測できない緊張した日々にあったであらう著者は「おわりに」の中で次のやうに述べてゐる。
「約4年弱に及ぶ内閣危機管理監の職務を終えてつくづく感じたことは、危機への備え、すなわちリスクマネジメントがなされていないところでは、危機が発生したとしても、危機管理の前提となる事前の危機の研究も危機を想定した対応策もないということであり、それでは決して的確で効果的なクライシスマネジメントはできないということである。
大事なことは、起こりうる危機の姿を現実のものとして考えるイマジネーションの力とその危機に備えるための対応策を、危機発生の蓋然性と発生した場合の被害の大きさを考慮しつつ実際の施策として決定して行くことである。また、危機発生に当たっては、想定外の事態が常に起こりうることを念頭に、想定外の事態が発生しても慌てず的確にクライシスマネジメントを行っていくことなのである」
まさに「エキスパート」による、空論の入り込む余地のない危機管理の基本書である。
(山内健生)
編集後記
ソチ冬季五輪の次は四年後、韓国・平昌での開催だ。雪不足の恐れや競技会場、交通アクセスなどの諸課題、そもそも冬季スポーツ人口がどれだけなのか等々の懸念が指摘されてゐる。さうした中で日韓経済協会(会長、佐々木幹夫三菱商事相談役)が、平昌冬季五輪とその二年後の東京五輪を通じた「両国の経済界の協力を、韓国側に呼びかけている」(四月十三日付朝日、吉岡桂子編集委員)さうだ。朝日の〝誘動論説〟か。財界人はどこまで人が良いのか。算盤しか念頭にないのか。
(山内)