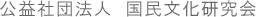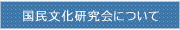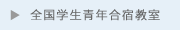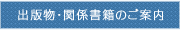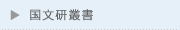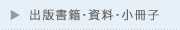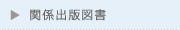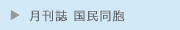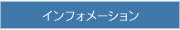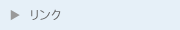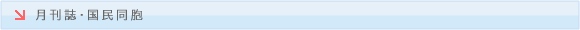
第625号
| 執筆者 | 題名 |
| 武澤 陽介 | 秋からの読書会を前に思ふこと - 今こそ国文研の価値が認識されるべきと感じてゐる - |
| 北濱 道 | 「九大信和会」の思ひ出 - 悪戦苦闘しつつ「沈黙して感じること」を学んだ - |
| 名和 長泰 | 「南風競ふ」(上) - 新しい校舎の窓から - |
| 新刊紹介 廣木寧著 総和社 税込1575円 『小林秀雄と夏目漱石 - その経験主義と内発的生』 小柳 志乃夫 |
|
| 資料 産經新聞10月16日付 一面 から引用 元慰安婦報告書 ずさん調査 氏名含め証言曖昧 河野談話 根拠崩れる |
近代フランスの作曲家クロード・ドビュッシーの有名な「月の光」には、作品の後半に冒頭部分が同じ形で再現され全く同じ旋律が奏されるが、その中に突如これまでに存在しなかった「変ハ音」が一音だけ響く。高名な音楽家で、我が国の音楽教育に計り知れない功績を残したアンリエット・ピュイグ=ロジェ女史は、この不思議な一つの音符に対し、「(完璧な芸術に対して)思わず溢れた一滴の涙」であると嘆じた。私は、感受性を強く揺さぶる真の感動とはこのやうな欠片にこそあると実感してをり、教壇に立つ時、教育者として後進の心にこの様な小さな光を与へたいと常に願ひ、日々精一杯努めてゐる。
私はこの感動の光を、学生の時に初めて参加した平成17年の伊勢での合宿教室で体験した。当時、大学で音楽を学び、自己の芸術の在り方に跪き苦しんでゐた私に、父が参加を勧めてくれたのが切っ掛けであった。最初は何も分らずに参加した合宿であったが、講師の方々の講義や、多くの友人との語らひ、さらには旅の道程までもが掛け替へのない思ひ出となって、今もその一つ一つが鮮やかに蘇って来る。あの時の合宿での感動の欠片を綴ったノートは今も常に座右に有り、今も創作や仕事に迷った時、一筋の道標を私に示し続けてくれてゐる。
伊勢合宿の後、暫く国文研との縁は遠退いてしまってゐたが、去年の秋、国文研東京事務所(渋谷)での古事記の輪読会へのお誘ひを頂いたことを機に、正式に「正会員」として入会した。それ以来、時間の許す範囲で輪読会などに参加し、新たな学びを続けてゐる。今年夏の厚木での合宿教室では、指揮班として廣木寧運営委員長の下、合宿を運営側の立場から体験するといふ貴重な経験を得た。
また9月23日(月・祝)、私は東京大神宮にて執り行はれた慰霊祭に参列した。都会の喧噪とは別世界の厳粛な斎場に入り、まづ最初に目を引いたのは祭壇の両脇に掲げられた国文研の道統に連なる方々の御遺影であり、また神主によって読み上げられる多くのお名前を聞き、その伝統の重みと緊張感に身が引き締まる思ひがした。
しかし、合宿においても慰霊祭においても、会員方々の口から発せられるのは、次世代の担ひ手である学生や若手の減少への嘆きや危機感であった。実際、合宿教室に参加する若い世代の少なさは誰の目にも明らかで、焦るのは当然であらう。
しかし、私は現状を深刻に受け止めつつも、このことに対し決して悲観はしてゐない。
恐らく、国難の正体が混沌とし解り難くなりつつある現代にこそ、国文研の価値が再認識されるべきと感じてゐる。軽薄な偏向報道を日々垂れ流して憚らない大手メディアらの力が弱まり、新聞やテレビのみが情報源として主流であったかつてに比べ、現在はそれらに安易に影響を受けないフェアな感覚力を持つ若者は以前より明らかに増える傾向にある。むしろインターネット等からの多角的な視点を得て、氾濫する情報から取捨選択する能力を持ち始めてゐる。昨今の政治経済の動静にも少しづつではあるが、今までとは異なる潮流が見られる。そのやうな意識の高い若者への受け皿として、今こそ国文研の役割は大きいと信じるのである。様々な形での情報発信ができれば良いのではと思ってゐる。
国文研の会員となって約一年程度の私自身は、国文研について未だ詳しく識ってゐるとは言ひ難い。今は尊敬する諸先輩方の姿に惹かれ、その後ろについていってゐるに過ぎないが、今年10月から、小田村寅二郎先生の御著『昭和史に刻むわれらが道統』をテキストとする中堅若手世代を対象とする勉強会が始まる。今後仕事の合間を見付け積極的に参加し、国文研の成り立ちについて一から学んでゆきたい。そして今後の会の発展に、自分の専門や経験を微力ではあるが生かしてゆきたいと強く願ってゐる次第である。
(作曲家・桐朋学園大学講師・上野学園高校音楽科講師)
九州大学への道
昭和54年のことである。横浜市内の県立高校に通ってゐた私は、大概の高校3年生と同様に、卒業後の進路で悩んでゐた。自分の人生を打ち込むものを見つけたいと思ってはゐたが、何をしたいのかといふ具体的な希望を持ってゐなかったからである。そんな時、倫理社会の時間に「チャイナシンドローム」といふ言葉があることを知った。「アメリカで原発事故が発生して炉心が溶け落ちた時、地球の裏側の中国まで達するだらう」といふ意味の言葉であった。学校帰りに立ち寄った町の図書館で、原発事故を描いたSF小説を借りて読み、主人公が水で冷やすため炉心に向ふ姿に感動した。読後、危険ゆゑの緊張感があるのではないかと考へて、原子力を学ばうと思った(福島原発の事故当初、被曝を顧みず任務を全うされた自衛隊、消防の方々に頭が下がった)。
学科名に“原子”を持つ大学は少なかった。それまで両親の庇護の下で安穏に暮してゐた私は、親元を離れて自分を変へたいとも思ってゐた。私は、横浜から遠くのいくつかの大学を思ひ浮かべた。
一方、私は、自分にない潔さ、決断力に憧れてゐた。現代国語の授業で、三島由紀夫氏の事件について話があり、関心を持った。町の小さな書店で、『尚武のこころ』といふ氏の対談集を買ひ、夢中で読んだ。他に『葉隠入門』等、彼の武士的実践に関する本をいくつか読み、彼の決然たる行動と言葉に牽きつけられた。また、クラスの友人が学校に持って来た『男一匹ガキ大将』といふ漫画の、九州の人物の果断と篤い友情に血湧き肉躍った。当時まだ九州に行ったことがなかった私は、九州に行けば情に篤い武士的男、即ち九州男児に会へると信じた。
私は、思ひ浮かべてゐた大学の中で九州大学を選び、昭和55年4月に進学した。
先輩との出会ひ
入学式の数日後、授業履修のオリエンテーションを迎へた。
オリエンテーションでは、教務課の職員による単位履修の説明の後、生協職員(以下職員)が登壇し、生活協同組合(生協)の説明だけでなく政治的発言(反原発の)をした。話の後、職員は質問は無いかと聞いたが、教室にゐた私を含む100名ほどの新入生は誰も質問せず、そのままその場が終るかと思はれたその時、窓際の通路に立ってゐた一人の学生が質問した。職員の政治的発言が他の人の意見の羅列であったのに対し、「君自身はどう思ふのか」と質問したのである。職員は何も答へられなかった。
職員が退出した後、この学生が登壇して、教務課から少し時間を頂いたと言って話を始めた。私と同じ学科の4年生だった。正岡子規が病苦の中、活き活きと生活し、短歌革新に尽したことを熱を込めて話された。大勢の新入生を前に堂々としたものだった。話の終りにこの4年生は、「学問と生き甲斐」といふガリ版刷りの冊子を示し、興味のある人は声を掛けて下さい、と言って降壇し教室の出口の辺りに立った。
オリエンテーションの時間が終り、教室から出て行く時、私は思ひ切ってその人に、冊子に興味があります、とおずおず話掛けた。先ほどのお話に感動しました、とも伝へた。これが弓立忠弘先輩との出会ひであった。
先輩は、その日輪読会があるから参加しないか、と言ってくれた。私は先輩に連れられて学生会館の和室に行った。部屋を見渡すと、参加者は新入生だけで10名以上ゐたやうに記憶してゐる。他に上級生らしき人が10名ほどゐて、皆大人に見えた。テキストは、文芸評論家小林秀雄氏の講義録『感想- 本居宣長をめぐって- 』(国民文化研究会の昭和53年夏季合宿教室でのもの)であった。
その頃の私は、文学は行動と関係なく言葉で飾り立てるだけのものと思ってをり、興味がなかった。小林秀雄氏についても、高名な文学者としてしか知らず、単に読書会といふだけなら、文学青年や少女がお喋りするだけの軟派サークルと嵩を括り、参加しなかったと思ふ。先輩との出会ひがあったお蔭で輪読会に参加し、その後お世話になる多くの先輩に出会ふことができた。
苦しみながら学んだ
大学に入るまでの私は、本で読み齧った断片的知識ばかりの人間だった。環境が人間を決定するといふやうな、素朴な唯物論的考へを持ってゐた。“感じる”といふことがわからなかった。大学に入り、先輩方に出会った後でいろいろと学ばなければならなかったが、その学びが知的理解といふお喋りから一歩踏み込んで、沈黙して感じるといふところに至るまで、乗り越えなければならないいくつかの壁があった。その一つが文章を書くことであった。
会では文章を書くことを求められた。読書感想や輪読会の案内文である。読み手を意識して、独り善がりの表現を避け、わかるやうに文章を書くのは難しい。書けるやうになるには、誰か書ける人に文章を見て貰ひ、批評を乞うて、実地に学ばなければならない。自分ではよく書けたと思ふ文章を、先輩が御覧になった後、ふと溜息をつき考へ込まれるのを見るのが苦しかった。独善的表現だったのだと思ふ。その度に、自分の表現力の拙さに心が暗くなった。気を取り直して、書き直し、また見ていただくことを繰り返した。さうして、文章ができることもあれば、できないこともあった。私は文章を書くことを、苦しみながら学んだ。いつでも先輩は、書き手の私の思ひを汲み取り、引き出さうと、徹夜で付き合って下さった。さうして私は、少しづつ自らの思ひを文章に表現できるやうになっていった。
書くことが考へることである。書くことで始めて自分が考へてゐること、感じてゐることがわかる。言葉にできなければ感じたことにもならない。言葉をよく選ぶことは行動そのものである。
これは、現在の私の感想である。学生時代はそこまで意識できず、悪戦苦闘の連続だった。
もう一人の先輩
知識の習得や理解のための学問の場は、世の中にいくらでもあるだらう。しかし心で感じる力を育てるため、文章を徹夜で見てくれる場は、一体どこにあるのだらうか。
私は偶々その場に巡り会ふことができた。それからが大変だったが、先に述べた経験と、もう一つの壁である文章を正しく読むことで作者の生きた言葉を自分の心に沁み込ませる輪読会で学ぶ裡に、人並みに素直に感じる情感を取り戻すことができた。それは言ひ換へれば、相手の身になって考へるといふことであった。
会に顔を出すやうになって、多くの先輩に面倒を見て貰った。中でも医学部4年の長澤一成先輩には可愛がっていただいた。地元福岡の御出身で、「葦牙寮」(以下寮)といふ名の学生寮に住んでをられた。入学後、暫くして私はそこに出入りするやうになったが、東区の筥崎宮の参道脇にある古い木造二階建ての建物で、入ると黴臭く、一階の床板が腐ってゐたためか踏むと畳が沈んだ。その質素さが学生寮らしくて、私は好きだった。その頃先輩から、「照れや衒ひは何も生まない」と言はれ、ドキリとした。照れたり格好を付けて、心を曝け出せない私の一番の弱点を見抜いての指摘であった。「好きなら何で告白しないのか」「一人の女を思へない奴にどうして国を思ふことができるか」とも言はれた。その後一年生の冬休みに帰省した私は、中学校時代の同窓生に思ひ切って告白し断られたが、もやもやした気持ちは晴れた。さらに先輩は、今の自分があるのは寮で共に生活してゐる友のお蔭だ、と言はれ、心に沁みた。
私は長澤先輩と同じ寮に入りたかったが、訳あって西区の「大観塾」(以下塾)に1年生の10月末、それまでの下宿から移った。塾に入ってからは先輩の指導は厳しくなった。人の話を勝手な解釈をせず黙って聞くのは難しいと気付かされた。又、自分が話してゐて話題を変へる時は、ところで、とか、話は変りますが、と断るやうにせよと注意された。それまで誰にも教へられことがなく、有難かった。これも、相手の身になって考へよ、といふことだったと思ふ。
他にも五年間(一年留学した)沢山の指導をいただいた後、私が卒業を目前にした頃、先輩と色々お話しする中で、そもそもお前さんは何で九州くんだりなぞに来たのだ、と言はれた。私は、九州男児に憧れたこと、そして輪読会でその幾人かにお会ひできましたと答へたところ、先輩は暫くして、「もう飽きたろ」と恥しさうにぽつりと言はれた。
私が出会ったサークルの名称は「九大信和会」と言った。「九大」は大学の略称、「信和会」は、聖徳太子の御思想で大切な意味を持つ言葉、「信」と「和」から来てゐた。
学恩を思ひ返す日々
さて私は、大学卒業後実家近くのメーカーに就職した。私が大学二年の時父が一度倒れ、それが心配で実家に戻らうと思ってゐたことと、研究室の教授にその会社を熱心に薦められたことによる。原発ではなかったが関連はあり、機械設計技術者として経験を積んだ。面白いことに、ここで設計の極意として叩き込まれたのが、部品の気持ちになって考へよ、といふことであった。今、福島の原発事故現場で技術者が日夜、事態の改善を目指し奮闘されてゐるが、とても他人ごとには思へない。先日の産経新聞で、汚染水問題に関して、ある研究グループが地面を舗装で雨水の浸透を減らせると提案してゐることを知った。地道に黙々と研究をしてゐる心ある技術者は、他にもきっと沢山をられるに違ひない、と思った。
私は昨年、訳あって会社を辞め、新たな仕事を求める一方で、合宿運営委員として東京地区の学生達と一緒に勉強してゐる。学生時代に先輩方からいただいた学恩を日々思ひ返してゐる。
(元(株)アルバック)
筑後川流域の眺望
本校(久留米大学附設高等学校)は昭和25年(1950)に久留米市東部の久留米大学御井学舎に創立された。昭和44年(1969)に現在の校地へ新築移転。平成17年(2005)3月20日に福岡西方沖地震が発生し、校舎の耐震補強か建て替へか種々検討の結果、旧高校寮跡地も含め全面的な校舎建て替へになった。平成22年から足掛け3年を費やして校舎を建設し、昨秋やうやく完成した。同じ敷地内の工事と隣り合はせで、中高1000余名の学校を通常通り稼動させながらの建設や移転は何かと大変であった。
新校舎は五階建てで、東棟に高校、西棟に中学の教室が各学年1フロアに配置され、やうやく「40学級」が実現できた。中央部には保健室、2階分の図書館、職員室、合同講義室、美術室、LL教室、音楽室が整備されてゐる。校地がやゝ高台にあるため、筑後川流域を広々と眺望できる。遠景には東の方から、古く山伏の修験道場であつた英彦山(1200平米)、大宰府政庁の鬼門(北東)の方位とされた宝満山(830米)、天智天皇2年(662)白村江の戦ひを機に築かれた基肄城址がある基山(405米)、古く山岳密教の修験場であつた脊振山(1055米)などの山々である。
「附設」の由来
久留米大学の前身は昭和三年(1928)創立の九州医学専門学校である。昭和21年(1946)大学令により旧制久留米医科大学となり、昭和25年(1950)の学制改革により新制久留米大学が設置される。それと同年に本校は戦後のいはゆる新制高校の男子校として創立された。その際、校名を「久留米大学附設高等学校」としたのは当時の久留米大学初代学長小野寺直助先生(1883- 1968)と本校初代校長板垣政参先生(1882- 1967)お二人の関係が背景にある。
両先生は、ともに岩手県の旧制盛岡中学の御出身であり、ともに医師・医学者であり、ともに九州帝国大学医学部の同僚であられた。先に久留米大学学長となつてをられた小野寺先生が新設高校の初代校長に板垣先生を招くにあたり、先輩で元同僚でもあるので上下の従属関係を示す「附属」とするわけにいかず、「附設」といふ校名を選ばれたのである。現在も学校法人久留米大学に属するものの、「附属」校のやうな大学との従属関係はほとんどない。
校歌に歌ふ高良山
創立にあたって旧制中学教育のよい面を継承せむといふ意識が働いてゐたことは容易に想像される。校歌の作詞は草創期に国語を教へてをられた大石亀次郎先生で、その歌詞は後掲の通り簡素ながら普遍的な教養がこめられてゐる。今日の生徒や若い保護者にとっては耳慣れない言葉もあり、初め古めかしく感じられるかも知れない。それでも卒業生に聞くと、卒業後、何かにつけ校歌に励まされたといふ卒業生は多い。附設は時代とともに中高一貫校、男女共学校と変遷をしてきたが、親しみをもって歌はれる校歌は創立当時のまゝであり、今後も当分変らないだらう。
| 1、高良山下の学園に 万朶の桜咲きそろひ 若き血潮の高鳴るを 見ずや希望の揺籃地 2、江月冴えて悠久の 流れは遠し千歳川 高き彼岸の光明を 見ずや試練の理想郷 3、修羅道の世を救ふべく 平和の偉業任として 築く不朽の真善美 見ずや我らの大使命 (語注) 千歳川=筑後川の古称。 修羅道=争ひの絶えない世。 |
まだ終戦後四年余りといふ時期であったから、草創期の職員・生徒の中には家族・親類・同僚・友人が戦災に遭ひ命を失ったものも少なくなく、国民みなが戦後復興を希求してゐた。「平和の偉業」に貢献する「大使命」を自覚させる歌詞は誰にとっても極めて自然なものであっただらう。
そして国民は努力を重ねて戦後復興を成し遂げ、さらに今日の繁栄を築き上げた。では、日本の現状は満足のいくものだらうか。「成熟社会」といふ言ひ方があるが、多くの国民は、わが国と国民の現状と将来には重い課題が山積し、前途はそれほど平坦ではないと感じてゐるのではないか。校歌を歌ひ、本校の原点と来し方を省みるたびに、また新しい気持ちで「我らの大使命」を自覚させられる。
久留米のシンボル「高良山」
校歌の歌詞は「高良山」から始まる。高良山(312米)は学校の東にあり、教室の内外から四六時中見える身近な山である。豊かな自然と歴史のある久留米のシンボルともいへる山で、久留米つゝじの咲くころには遠足で訪れたり、普段はクラブ活動で走って登ったりもする。
高良山に鎮座する筑後一の宮高良大社の歴史は景行天皇12年(82)まで遡る。筑後平野に突き出した地形は古代から戦略的要衝として重要で史跡も随所にある。山をとり囲む古代の神籠石はまだ分ってゐないことが多い。吉見嶽は天正15年(1587)に島津征伐に向ふ豊臣秀吉が本陣を敷いた城跡である。高良山の頂きには、南北朝時代の筑後川合戦の際に、征西将軍宮懐良親王方の毘沙門岳城がおかれた。
数々の往時を偲ばせるもの
一方、校舎の北側の窓からは市街地の向ふに筑後川の流域の田畑の広がりが望める。この一帯は南北朝の頃、合戦の場となった。文和2年(1353)には大宰府に迫る「針摺原の戦ひ」が現在の筑紫野市の中央部の平地で戦はれた。延文四年(1359)には筑後川北岸の10キロ四方で双方約10万の将兵が死闘を繰り広げた。九州で最大の合戦で「大保原(大原)合戦」または「筑後川の戦ひ」といはれる。
懐良親王率ゐる南朝方は菊池武光、赤星武貫、宇都宮貞久、草野永幸ら約四万、大宰府を本拠とする北朝・足利勢は少弐頼尚、少弐直資の父子、大友氏時、城井冬綱ら約6万の壮絶な戦ひであった。
菊池氏らの奮戦を讃へて頼山陽(1781- 1832)は「下筑後河過菊池正観公戦処感而有作」といふ36句の長詩を詠んでゐる。
| その途中の21~30句、 歸來河水笑洗刀 血迸奔湍噴紅雪 四世全節誰儔侶 九國逡巡西征府 棣萼未肯向北風 殉國劍傳自乃父 嘗卻明使壯本朝 豈與恭獻同日語 丈夫要貴知順逆 少貳大友何狗鼠 (読み下し) 帰り来って河水に笑って刀を洗へば 血は奔湍に迸って紅雪を噴く 四世の全節誰か儔侶せん 九国逡巡す西征府 棣萼未だ肯て北風に向かはず 殉国の剣は乃父より伝ふ 嘗て明使を卻けて本朝を壮にす 豈恭獻と同日に語らんや 丈夫要するに順逆を知るを貴ぶ 少弐大友何の狗鼠ぞ (語注) 四世=菊池武光公の父武時、武重、子の武政ら四代。儔侶=仲間。棣萼=にわうめの花の萼。兄弟(の情の美しいこと)。嘗卻明使=正平23年(1368)明国の使者が博多に来た時その無礼を怒って追ひ返した。恭獻=足利義満が明に臣礼をとり、没後恭献王の諡号を受けた。 |
菊池氏らの奮戦により九州全域は征西府の支配が実現する。
今日も筑後川の北岸(往時は南岸)に「宮ノ陣」といふ地名がある。菊池武光が太刀を洗った故事が地名となり、太刀洗公園には立派な銅像もある。さらに敵味方なく戦没者を供養する大原合戦五万騎塚、など往時を偲ばせるものが数多い。
(久留米大学附設中学校教頭)
廣木寧著 総和社 税込1575円
『小林秀雄と夏目漱石 - その経験主義と内発的生』
小柳 志乃夫
本書の概要
本会会員の廣木寧氏の二冊目の著書が刊行された。前著『江藤淳氏の批評とアメリカ- “アメリカと私”をめぐって』と同様、『正統と異端』といふ、本人が主宰する同世代の友人との同人誌に掲載した論考が主体ではあるが、今回は、本紙等に寄稿した文章や本会の合宿教室での講義録、さらには書き下ろしの文章などを織り交ぜ、大小15篇の文章を一つの書としたものである。前著は江藤淳氏の文章と周辺の文献を丹念に読み込んで、江藤氏のアメリカ体験の意味を明かした大作であったが、本書は著者自身の思ひがよりストレートに窺へる内容で、よりコンパクトな仕上がりになってゐる。
冒頭の一篇「内発的に生きるということ- 漱石から小林秀雄、江藤淳まで」と巻尾の「小林秀雄氏の經驗主義- 『信ずることと知ること』をめぐって」の二編が本書の副題に呼応して二つの大きな峰をなすが、その双峰の間にも魅力的な山々が連なってゐる。漱石の『心』をめぐる諸論考、漱石と池辺三山の友情、俗物を焼き尽くす小林秀雄と漱石の眼、かつて聴講した合宿教室における小林秀雄氏の姿など、読者は好きな山から登ることもできるだらう。
著者の学問体験の書
夏目漱石と小林秀雄といふ、近代日本を代表する巨人の文学を、著者は学生時代から愛読してきた。著者は「小林氏の文章も話も、いつもそうであるが、僕らの魂に深く届いて、永く響くのである」と記してゐるが、本書は長年の読書経験の中で、漱石や小林秀雄の魂に著者の魂が共鳴した記録といへる。
あとがきには次のやうにある。
「青年ほど危い存在はない。青年期ほどあらゆる配慮が必要な時期はない。そして青年ほど他人の配慮を拒絶する者はない。この青年期に幾人もの人がみずからの痩躯を貫く言葉をさがし求めて文学をひもとくのではないか。小林秀雄であれ、漱石であれ、一流の文学は、一言一句に作者がみずからのいのちの全重量を懸けて綴っている。そのかけがえのない言葉が青年の渇きを癒すのである。本書は、青年期から小林秀雄と漱石の、その人格と切り離せない文学に魅かれて耽読している者の、まだ言葉足らずの『Xからの手紙』である。」
ここには著者の青年時代の読書経験とともに、現在も学生への読書指導を続けてゐる著者の青年学生への願ひが、さらには本書執筆における自身の「一言一句にみずからのいのちの全重量を懸けて綴らう」といふ思ひが込められてゐるやうである。
「言葉が青年の痩躯を貫く」といふことについて、著者自身の経験も本書の中に記されてゐる。昭和53年、本会の阿蘇合宿での小林秀雄氏の講義のときのことである。小林秀雄氏はプラトンを引きながら「信頼し合った者同士が語り合うとき、本当の生きた知恵が生まれる」と対話の大切さを説かれた。以下は本書からの引用である。
「小林さんは語る、『対話といふものをだんだんとつきつめて考へて行くと、心を割つて話す相手が、必ずしも現実にゐなくてもいいでせう。自分自身と話しあへばいいでせう。だから、対話の最も純粋なる形は、自問自答であるとも言つていいわけでせう。』
35年前の夏、440名の者が“阿蘇の司”というホテルの一室に集い、小林さんの講義を一個の耳と化して聴いていた。そういう時であった、僕の五体を『自問自答』という言葉が貫いたのは。
あとは、僕が“学問”という自己との対話を始めればよかった。自分の顔をみるために鏡がいるように、自分自身と話しあうために、人は「鑑」を必要としている。その鏡を、古来、僕らの先祖は、古典としてうやまって来たのである。」(「阿蘇合宿の小林秀雄」)
この「五体を貫く」大きな感動から、著者は学問の道を踏み出した。それは自分と向き合ふことであり、古典と真向ふことであり、しっかりと大地に自らの足で立つことでもあったらう。著者はこの道を一途に歩んできたのである。本書は漱石・小林秀雄を「鑑」にした、長年にわたる著者の自問自答の記録でもあるわけである。
以下、内容を少し紹介しよう。
「内発的に生きるということ」
冒頭の一篇である本編は『正統と異端』創刊号に「発刊の辞」として書かれたものであり、平成12年の文章である。自問自答といふ学問を地道に続けてきた著者が40代半ばにして、その同人誌立ち上げの志を世に問はんとした論考であり、内容的には、漱石の講演『現代日本の開化』での「西洋の開化(即ち一般の開化)は内発的であって、日本の現代の開化は外発的である…」といふ視点を、様々な文献や事象を用いて、さらに広げ、深めて、日本の近現代の精神史を浮き彫りにし、問題を提起したものである。
「ペリーの恫喝によって国を開いた先人たちは外発的受容性を強いられながらも、その受容の内発化に努めて来た。そう努めさせたのは日本の内発的開化を願う- そうしなければ日本人は日本人でなくなるのだから- 日本人の内発的意志であった」。しかし、戦後占領下の検閲で日本人の内発的意志の表現は困難になり、逆に「日本人が日本人に石を投ずる」事態が生じた。「戦前も戦中も戦後も歴史の内的連続性の中で生きて行こうとしていた」小林秀雄も進歩的知識人から石を投げられた一人であった。時代に迎合し、浮遊する生き方は今に続いて、内なるものを見失った日本人は「現世の利益を求め続け」、今や「この世への執着は古今を絶している」- 「日本人が日本そのものを外発的開化の中で捨て去ろうとしている」のである。
それへの対応はいかにも困難であるが、著者は漱石のいった「内発的に変化して行く」といふ道にもう一度光を当てる。その先例としての指標を聖徳太子の「大陸思想批判綜合の内的事業」に求め、黒上正一郎先生の三経義疏研究の文章を紹介した上で、以下のやうに結んでゐる。
「『批判総合』という、内発的に生きようとする烈しい批評精神の活動を一つの回転運動とするならば、回転を維持継続させるためには一つの芯が要る。その芯こそが日本人としての自覚なのである。太子にあり、漱石にも白鳥にも小林秀雄にも江藤淳にもあったが、私たちに欠落しているのは、日本人の人生観への信なのである。」
著者の内心から迸り出た憂国の切言である。
「小林秀雄の經驗主義」
この巻末論文は、「『信ずることと知ること』をめぐって」といふ副題が付されてゐる通り、昭和49年の本会霧島合宿における小林秀雄氏の講義をベルグソンや柳田国男の原典などを辿りながら丹念に読み解いたものであり、この講義に小林秀雄氏がどういふ気持ちを込めてをられたか、どれだけ深い気持ちを込めてをられたかを明らかにしてゐる。
科学的合理主義に対して、人生の直接経験を守らうとする小林秀雄氏の戦ひは自身の若き日の母親の悲苦を受け止めた体験に裏打ちされてゐたといふ。著者の言葉を引いておく。
「小林氏は、自らの大学入学からほぼ半世紀経った昭和49年、大学生に向って自らの悲痛な經驗とそこから出発した学問の初心を心に秘めて、講義を行なったのである。霧島で小林氏は語った、- - 諸君、科学に負けてはいけない。」
「小林氏は、日本人に、自らの『經驗』に還って、『科学的經驗』に限定されぬ、『私達が、生活の上で行なってゐる廣大な經驗の領域』を押し広めて欲しいのである。……
今一度、言おう、素直な心をもち、いたずらな反省を去って、事実とのありのままな經驗に還れ、と小林氏は願うのである。……」
著者は小林氏の語った柳田国男『山の人生』の炭焼きの親子の話を本書に何度も引用してゐる。忘れがたい「ありのままの經驗」として。
本会の学問の道統の中で
「素直な心をもち、事実とのありのままな經驗に還る」とは、本会で学ぶ「しきしまの道」を想起させる言葉でもあるが、本書を読んで思ふのは、本書は独り廣木氏の作品にとどまらぬといふことである。かつて廣木氏は九州大学の学生時代の友らとの輪読体験が実に充実したものだったと述懐したことがある。浪人時代の漱石愛読から本格化したらしい彼の読書は、黒上先生の“太子のご本”や松陰の講孟余話の輪読体験を通じて、次第に私的関心の領域から公的な世界に広がっていったやうに思はれるが、本書はさうした国文研での活動の中での輪読、寮生活での交流、或いは合宿教室での「一個の耳と化した」真摯な聴講などから生み出されたものであって、その点では、廣木氏といふ個性的人格を介して、国文研の学問の伝統が発現した著述であるともいへるだらう。
本書の冒頭に「恩師、岳父そして父の御霊に」との献辞が記されてゐる。恩師といふとき、著者が尊敬し追慕してやまない小田村寅二郎先生を思うてゐることは疑ひない。先生の学恩を謝しつつ、先生に自分の学問の現在をご覧いただきたいといふ思ひがそこに込められてゐる。
かうした意味でも本書は是非会員の皆様に手に取って頂きたい書であるし、また、世に広めていただきたい書である。
(興銀リース勤務)
産経新聞は15日、慰安婦募集の強制性を認めた平成5年8月の「河野洋平官房長官談話」の根拠となった、韓国での元慰安婦16人の聞き取り調査報告書を入手した。証言の事実関係は曖昧で別の機会での発言との食い違いも目立つほか、氏名や生年すら不正確な例もあり、歴史資料としては通用しない内容だった。軍や官憲による強制連行を示す政府資料は一切見つかっておらず、決め手の元慰安婦への聞き取り調査もずさんだったと判明したことで、河野談話の正当性は根底から崩れたといえる。産経新聞は河野氏に取材を申し入れたが、応じなかった。
慰安所ない地域で「働いた」
5年7月26日から30日までの5日間、ソウルで実施した聞き取り調査に関しては9年、当時の東良信内閣外政審議室審議官が自民党の勉強会で「(強制性認定の)明確な根拠として使えるものではなかった」と証言している。ところが政府は、この調査内容を「個人情報保護」などを理由に開示してこなかった。
産経新聞が今回入手した報告書はA4判13枚で、調査対象の16人が慰安婦となった理由や経緯、慰安所での体験などが記されている。だまされたり、無理やり連れて行かされたりして客を取らされるなどの悲惨な境遇が描写されている。
しかし、資料としての信頼性は薄い。当時、朝鮮半島では戸籍制度が整備されていたにもかかわらず、報告書で元慰安婦の生年月日が記載されているのは半数の8人で空欄が6人いた。やはり朝鮮半島で重視される出身地についても、大半の13人が不明・不詳となっている。
肝心の氏名に関しても、「呂」と名字だけのものや「白粉」と不完全なもの、「カン」などと漢字不明のものもある。また、同一人物が複数の名前を使い分けているか、調査官が名前を記載ミスしたとみられる箇所も存在する。
大阪、熊本、台湾など戦地ではなく、一般の娼館はあっても慰安所はなかった地域で働いたとの証言もある。元慰安婦が台湾中西部の地名「彰化」と話した部分を日本側が「娼家」と勘違いして報告書に記述している部分もあった。
また、聞き取り調査対象の元慰安婦の人選にも疑義が残る。調査には、日本での慰安婦賠償訴訟を起こした原告5人が含まれていたが、訴状と聞き取り調査での証言は必ずしも一致せず二転三転している。
日本側の聞き取り調査に先立ち、韓国の安秉直ソウル大教授(当時)が中心となって4年に行った元慰安婦への聞き取り調査では、連絡可能な40人余に5、6回面会した結果、「証言者が意図的に事実を歪曲していると思われるケース」(安氏)があったため、採用したのは19人だった。
政府の聞き取り調査は、韓国側の調査で不採用となった元慰安婦も複数対象としている可能性が高いが、政府は裏付け調査や確認作業は一切行っていない。
談話作成に関わった事務方トップの石原信雄元官房副長官は産経新聞の取材に対し「私は報告書は見ておらず、担当官の報告を聞いて判断したが、談話の大前提である証言内容がずさんで真実性、信憑性を疑わせるとなると大変な問題だ。人選したのは韓国側であり、信頼関係が揺らいでくる」と語った。
- 産經新聞を読んで思ふこと -
自民党の責任は重大だ!
近年、ますます顕著になる韓国の度外れた「反日ぶり」には憐みを覚えるのみだが、この記事に見られるやうに、わが政府の無責任さにも開いた口がふさがらない。根拠がないまま韓国政府が望むからと強制性を認めたわけだが、ことはこれだけではない。
①中韓の干渉を躱すために「近隣諸国条項」を定めて教科書の記述を規制し②中韓から抗議が来たからと検定済み教科書を書き換へ③平和条約で外交決着してゐるにも関らず「多大の損害と苦痛を与えた」との首相談話を出し④中韓が騒ぐからと靖国神社とは別の国立追悼施設建設を目論んだ。これらはここ30年余の間に、全て自民党政権の下でなされた。一時しのぎの退歩で波風を収めて来た。そのひとつが河野洋平官房長官談話だった。
自民党の責任は重い。無責任な指導者によって青少年の心がどんなにか傷ついてゐることか計り知れない。今や総理の靖国神社参拝も儘ならず、尖閣諸島を無人に放置して来たため中国公船の領海侵犯が繰返されてゐる。かうした自民党政権の失態を糾弾するどころか、使嗾したのが天下の大朝日であった。メディアは重篤だ。
(山内健生)
編集後記
10月3日、米国のケリー国務長官とヘーゲル国防長官が、千鳥ヶ淵戦歿者墓苑に拝礼。「氏名不詳及び遺族の不明」の御遺骨の納骨堂が墓苑だ。昭和34年竣工の際、靖国神社は「全戦歿者の霊を祀るもの」、墓苑は「特別の事情にある御遺骨を納める施設」とされ、「外国使臣を案内しない」といふことだった。墓苑も重い所ではあるが、両長官の拝礼は「日本との同盟強化に取り組む米国の姿勢を示す狙いがありそうだ」(産経)といふなら、先立って靖国に参拝して欲しかった。政府・外務省よ!、しっかりせよ。妙な先例をつくるな。
(山内)