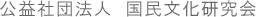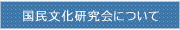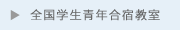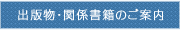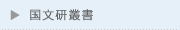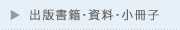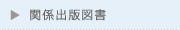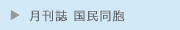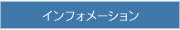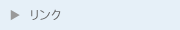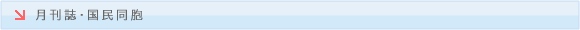
��U�P�V��
| ���M�� | �薼 |
| �T��@�F�V | �u�j�n�p���������ɐ}�邩�v�Ř_�c�̐i�W�� - �u�c���T�͂̉����v�ɂ��A���{�����Ɋ��҂��� - |
| ��糁@���v | - �w����x��W�W���i�����Q�S�N�P�P���P�T���j���� - �T�؏��R�I���P�O�O�N |
| �T�؏��R�̒Z�� | |
| ����@�g�� | �w�����N�ցA�u���{�_�b�v�Ɩ����̓��{�ɂ��� - �g�c���A�搶�́w�u�З]�b�x�Ɋw�� - |
| �����@���� | ���{��ɂ�ǂ���������� |
| �R���@���� | a href="#06">���̊��i���a�Q�U�N�j�A�喾�c�@�u��呒�v�̍Z������ - ���w�Z���w���X�̑̌� - |
| �u�싞��藧�čٔ��̉��v - ��ȁu�싞�ٔ��v�������� - |
�@�P���R�O���A���{�W�O�̏��M�\�������i�P���Q�W���j�ɑ���e�}�̑�\���₪�O�c�@�{��c��ōs�͂ꂽ�B���{�ېV�̉���\���ēo�d�����������v�c���́A�c���T�͉����ƍc���̑����ɂ��Ď̌������������B����ɓ��ւĈ��{�́A�j�n���ێ�����ė����d�݂܂ւ�K�v������Ƃ��āA��c���F����}���t���������������{�Ƒn�݂ɂ��Ă͔����ɖ߂��l�ւ������B����܂łɂ��͎Y�o�V���̃C���^�r���[�Ɂu�c�ʌp���͒j�n�j�q�Ƃ������̕��j�͕ς��Ȃ��v�i�����A�Q�S�E�P�Q�E�R�P�t�j�Ɠ��ւ�ȂǐM�O��\�����Ă���A����̏�Ŗ����������ƂɈ��g�̔O���o�����B
�@�ƌ��ӂ̂́A��c�O�������ژ_�����{�Ƒn�݈Ăɂ��Ắu�_�_�����v�ɑ�����t�̈ӌ�����̌��ʁA�u�����A���n�V�c�ɂȂ��鋰�ꂪ����A�Ɣ����鍑���̈ӌ����������߂��v�i�Y�o�V���A�Q�S�E�P�Q�E�P�X�t�j�ɂ������͂炸�A�u�_�_�����v����l�������Ă��܂ӂ̂ł͂Ȃ����ƌ��O���Ă����ł���B
�@���ӂ܂ł��Ȃ��A�c�ʂ̈���I�Ȍp�����ێ����邽�߂ɁA�����Ȃ鐧�x�������K�v����_�c���邱�Ƃ͏d�v�ȉۑ�ł���B���̓_�ł͖�c�O�����g���Ƃ͕]���ł��邪�A���̏ꗽ���̕���Ř_�c�����̍ق����U�炤�Ƃ����Ƃ���ɊԈ�Ђ̌����������Ǝv�ӁB
�@���x������_�c����ꍇ�A���Ɍ������ׂ��ۑ�́A���{�Ƃ̍c�Е��A�̐���ł��炤�B��c�����́u�_�_�����v�ł́A���c���̒j�n�j�q���̗{�q�E���A�Ắu�����ΏۂƂ��Ȃ��v�Ɩ������ꂽ���A����͍c�ʌp���c�_�ɂ����Ă͐藣���Ȃ��d�v�ȉۑ肾����ł���B
�@�Ȃ��Ȃ�A�c���T�͂ɂ́u�c���q�v����u�c���f���y�т��̎q���v�܂ŁA�c�ʌp�����ʂ̒�߂�����A�p�����i�ɒ�߂��Ă��c�����Ȃ��Ƃ��́u�ŋߐe�̌n���̍c���ɁA�����`����v�i��Q���Q���j�ƂȂ��Ă��B�c���T�͂͏��a�Q�Q�N�T���R������{�s���ꂽ�@���ł���A���c�����f�g�p�̐�̐���ɂ���Đb�Ѝ~��������ꂽ�̂́A���N10���ł���������A�c���T�͂ɒ�߂��u�ŋߐe�̌n���̍c���v�Ƃ́u���{�Ƃ̒j�q�c���v���w�����Ƃ͖����ł���B�]���āA�ɒ�߂�ꂽ�ŋߐe�̌n���̍c������c�ʌp���������͂����̂��f�g�p�̐���ł������킯�ł���B
�@����16�N���ɁA�����̏���Y�̎��I����@�ւƂ��Đݒu���ꂽ�u�c���T�͂Ɋւ���L���҉�c�v�ɂ����Ă��A��c�������s�����u�L���҂���̈ӌ�����v�ɂ����Ă��A���c���̕��A�̈ӌ����q�ׂ����҂����݂����ɂ������͂炸�ӌ��W��ł͖������ꑱ�����B
�@���{�Ƃ̍c�����A�ɂ��āA�u����ʍ����ƂȂ��Ă��琶�ꂽ���܂ōc���Ƃ���͖̂����v�Ƃ��A�u����V�c�Ƃ̋��ʂ̑c��͖�U�O�O�N�O�ɂ����̂ڂ鉓�����ł���v�Ƃ����X�̗��R�Ŕ�����L���҂Ə̂���l�X�́A�P�Q�T��̗��V�c���j�n�ł���Ƃ��ӔF���ɖR�������A���n�V�c��F�߂������ׂɔ������Ă��̂ł��炤�B�c���T�͐��莞�ɍc�ʌp�����i�����n���ƔF������Ă���{�Ƃ̕��A�Ă�^���Ɍ������ׂ��������Ă��ƍl�ւ�B
�@���Ɍ��������ׂ��ۑ�́A�c���T�͂̈ꕔ�����ł���B
�@��̓I�ɂ́A�|�c�P�����u�c�������c���̒j�n�j�q�Ɍ����ė{�q���Ƃ��悤�ɍc���T�͂�ύX����K�v������v�i�Y�o�V���A�Q�S�E�P�Q�E�R�O�t�Ȃǁj�Ǝw�E����Ă��₤�ɁA�u�V�c�y�эc���́A�{�q�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��v�i�����j�Ƃ��邪�A��ւu�A���c���ɑ�����j�n�̒j�q��{�q�Ƃ��邱�Ƃ�W���Ȃ��v�����ւ�B�������邱�Ƃɂ��A���ɒj�q�̌p���҂������Ȃ��헤�{�A�j�{�̗��{�Ƃ͋��{�Ƃ̒j�q��{�q�ɂ��邱�Ƃ��ł��A�O�}�{�A���~�{���Ƃ̏����ɂ́A�ӂ��͂����j�n�j�q�𖹗{�q�Ɍ}�ւ邱�ƂŁA�{�ƌp�����\�ɂ��邱�Ƃ��ł���B
�@���{�������A�u�j�n�p���������ɐ}�邩�v�Ƃ��ӊϓ_�ɗ��_�c����̓I�ɐi�W������₤���҂��ě߂܂Ȃ��B
�i���c�{��q���j
�@�X����Ƃ��ӕ�������ꂽ�B���R�X�l�A���m�R��������������㗝�Ƃ��ē싞�U����ɎQ������A�u�싞�s�E�͂Ȃ������v���Ƃ������A�b���A�i�ւÂ���ꂽ���ł���B��㉺�ւɏZ�܂͂�A�����P�P�N���ւŖS���Ȃ�ꂽ�i�X�P�j�B�̖̂L�Y���w�Z�̑��Ɛ��ł��鎄�̂P�Q����y�A�ӔN�̂������Ђ��������A�悭����ɂ��ז����Đ̘b�⎞���k���f�������̂ł���B���̒��ŁA�T�ؑ叫���M�����Ė����V�c�ɌR���t�コ�ꂽ���̂��Ƃ�400���p���̂T���ʂŏ����ꂽ�Z�����͂Ղ������Ƃ�����B���S���Ȃ�ɂȂ��Ē����������̋@�֎��w�������E�x�ɒ��Ղ����Ă���������A����͑�O�R�T�ؑ叫�̖����ɍ݂�������Y�t���i��̑叫�j���璼�ڏ������b���ƌ����Ă���������Ă�B
�@�u��R���i�ߊ����n�ߍ��ؑ��A�����i�ߊ��̑t����I��A�����ŔT�ؑ�O�R�i�ߊ����É��̌�O�ɎQ�i���đt�シ�鎖�ɂȂ莟�̊ԂɍT�ւ��ɒn�m�Q�d���ȉ��e�Q�d�͔T�،R�i�ߊ��̑t��̐������܂��đ҂��ċ����B�R��ɌR�i�ߊ��̐��͑҂Ăǂ��������Q�d���ȉ��@���Ȃ鎖���N�����̂��B�B�S�z����̂݁A���Ǒ叫�̐��҂��S���ӊO�ɂ��䎺����k�ꕷ���ė����͔̂T�ؑ叫�̚j���`�W�̐��ł������B�Q�d���ȉ������ꓯ�͎��̈ӊO�ɗB�ׂ��p���Ȃ����Ԃ̐��ڂ�҂��͂Ȃ������B�b��������T�ؑ叫�̚j��̐����Q����܂萋�Ɉꌾ�̌����������O��ޏo����悤�Ƃ��ꂽ���̎��w�҂āA���������ċ�����苨�̖��͒����a���邼�x�Ƃ̕É����d���ɑ叫�͖ܘ_���̊Ԃɍ݂��đ叫�̑ޏo��҂Q�d���ȉ����ɓd���ɑł��ꂽ��u�ł������B�z�����ĔT�ؑ�O�R�i�ߊ��̌R��t��͑叫�̚j���`�W�ɏI�����B�����V�c�͈����ȉ����点��ꂽ�̂ł���B�v
�@�����̂Ƃ����ʂ̖{�����L���Ă݂�ƁA���̖{�i���c���F�w�T�؊�T�x�j�ɂ͔T�ؕ������̑S�����L���ꂻ�̌㔼�A
�@�u���P�U�����ԁA�䂪�����̏�ə��G�ƌ������A���E�`�����邱�ƋA���邪�@���A�e�ɝ˂ꌕ�ɟo���ҊF�A�É��̖������Ă��ӑR�Җڂ�����́A�b����t�������Ɨ~������\�͂��i�ȉ��������ȗ��j�T�́i�����Ɏ����āj�M�ܟ�Ƃ��ĉ���Ђɂނ��ы������B�V�c���܂�����������点�������B�v
�@�X������̕��������Ƃقڑ�����ӁB�b�͂Ƃ���ǂ���p�����ւđS���Ɋg�������Ǝv�͂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�u�������́v�Ƃ��ӕ��ꂪ����B�������q�������ꂽ�@�،o�̒��ߏ��w�@�؋`�`�x�̒��Ɏg�͂ꂽ���t�Łi�O���́u���v�ɕ����u���v�ւ�A���Ɖ�����ɂȂ�̈Ӂj�A�������̌Â���y���[�S�܂���͂��́u�������́v�ɌN�b�̓�Y�ւāu�N�b�������́v�Ƃ��ӌ��t�Ō䎩���̑̌�����u���́v�����ꂽ���Ƃ�����B��������̂܂܂��肵�Č��Ђ����B�T�ؑ叫���S�S�g�������ĕÉ��ɂ��d�ւ��A���̐\���Ă��u���v�̎p�̂��ׂĂ��A�g����ݔ[�߂Ă��u���v�ւɂȂ�A���́u���v�Ɓu���v���ʂЍ��ӎp�A���ꂪ�킪���̕����̒��j�ɂ���B���̂���1��N�b�̊��Ɖ�����ɂȂ邱�ƁA�����{�������̒��j���Ȃ��Ă����Ƃ��Â��v�ӂ̂ł���B�T����̒�����[���Â����܂ӕÉ��ƔT����̂܂�����̒ʂЍ��ЁA���ɕ���̂ݐՂ�ǂ��Ď��n�����A���̏����������A�S�т�����{�̎p�ɁA�����̍����͊��������̂ł���B
�@���ꂩ��S�N���o�č���������B�������I��������ɉ��B�ł͂ɂ͂��ɑ�킪�N��A�����ŋ��Y�v���A�x�ߓ����A�哌���푈�A���̔s�k�Ɣ��̂ƂÂ��A��̌��@�A�������̔�Q�͍����Â��Ă��B�g�ӂ̈ꎖ���L�����Ă��������B���̏o�g���w�͌����L�Y���w�Z�i�����j�őn���͖����R�Q�N�i���N�͈ȗ��P�P�R�N�j�A���a�R�N�ɐ��肳�ꂽ�Z�́i�쎌����C�V�A��ȐM�����j�͎��̒ʂ�ň�ԂɎn�܂�O�ԂɏI��B
�@�@�@�i�P�j�T�؏��R�̐���ɂ��Ƃ���@���F�R���ꂵ�Ƃ���
�@�@�@�@�@�@���ɕM�Ɉ̐l���������@��C������n����䂪�L�Y
�@�@�@�i�Q�j�̋���Ɏl���i�R�Ɂ@���슱��̓�̓���
�@�@�@�@�@�@�̂��̂тĖ]�ɂ����@�����W�ւ肱��䂪�w��
�@�@�@�i�R�j�����̏h�������@�������č�������������
�@�@�@�@�@�@�����S�Ƒ̂ɐ����ā@�~�܂��i�ނ����̗��z
�@�w�����v�ɂ���Ċw�Z�͌����L�Y�����w�Z�ƂȂ������Z�̂͂��̂܂܌p�����ꂽ�B�R����Ԃ͍폜����A�O�Ԃ́u�����̏h�������v�́u�L�Ȃ����������������v�Ɖ�₂��ꂽ�B�u�����v�Ƃ͖����R�T�N�����V�c���{�s�K�̐܁A�{�Z�V�z�u�������s�ݏ��ɏ[�Ă�ꂻ�̍ۂ̌䉺�����ōZ������������ꂽ���Ƃ��̂������̂��B�S�Z���k�������Ċ�����}�����v�Џo�������Ƃ��Đ˂��A�u�T�؏��R�v�̈�ԂE�����̂͐��̉��ł������̂��B���ݍZ�̂͊w�Z�s���̎��T�ł��̂͂��A�h�����ĉ����c���K�Ő��͂��܂Łi��Ԕ����Łj�̂��Ă�邳�������A����������ł͍ݍZ���u���X�o���h�̔��t�őS�͋傪�����升������Ă��B��������ɂ��Ă����̖����Ɖ���͒p�Â��������Ƃł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�哌���푈�ɔs��A��̌��@�ɂ���ēƗ��͂�����ے肵�āA�킪���͍ċN�s�\�ɂȂ��Ă��܂ӂ̂��B���₢��A�����ł͂Ȃ��B�哌���푈�I���ُ̏��̖w�ǂ̂����t�́A�I����߂����O��c�ŏ��a�V�c���܂Ȃ���ɋ��ɂȂ����䌈�f�̂����t���̂܂܂��ƕ����B
�@�@�@�@�@���̈��
�@�@�@���n䢃j��铃��쎝�V���e�A���ǃi�����b���m�Ԑ��j�M�߃V�A��j���b���g���j�݃�
�@���̗��j��̎��_�ɂ����āu��铃��쎝�V���e�v�ƕÉ��͖��炩�ɋ���ꂽ�B�V�c�É��ɂƂ��Ě�铂̑��`�́u�����i�I�z�~�^�J���j�v�̑����ɂ���A�Ƃ̌�ӂł͂���܂����B���܂���ƕ����ē����̌䐻�����L���B
�@�@�@�����ɂ��ӂ�䂭���̏�������Ђ������Ƃ߂���g�͂����Ȃ�ނƂ�
�@�@�@���������������Ƃ��瓹�����݂䂭�Ƃ��������Ƃ߂���
�����炱�������ɂƂ��č��̂̑��`�͍c���A�Ȃ́u�V�c�v�ɂ���̂ł͂Ȃ����B���a27�N���a����̓��̌䐻���Ĕq�u�������B
�@�@�@�������ݓ~�͉߂��Ă܂��ɂ܂������d���炭�t�ƂȂ肯��
�@�@�@���̏t�ƍ������͂Ȃꑚ���ق�~�ɂ��ւ������̂������
�@���ꂩ��̍ċ��o���_�ɗ����C�����ł��炤�B��a�Ɗ���̌���������ق݂��Ƃ̂���ׂɏd���Ă��₤�ɔq������B
�@���Ă��̓x�̓��k��k�Ђ����������鍑���̗͂́A����É��̌䎜����đS���I�ɋ������ӓ`���I�ȍ��������͂ɑ��Ȃ�ʂƎ��o����Ă����Ǝv�ӁB����������A���͕����ɂ���Đ������ߗ��̌R���I�N���Ɲs�����U�̐�`��Q�͂킪���̓Ɨ���Ƃ����́A���R�̑唼�͂킪���̖���ɂ���B���@�������ČR���͂𐮂ւ邱�Ƃ����B���͋��t�Ƌ��ȏ����������ċ`�����炩���т��Ă킪���̗��j�Ɠ`�������t����邱�ƁB���t���G��ł���������������̂łȂ�����ւ�����̂ł͂Ȃ��B�u�N����v���p���𐳂��ĉ̂ӂ��ƁB�`���@���ɓ���ތ��l�ȑ������A�S�������T�܂����A������ʼn̂ӂ��Ƃ��瓥�݂������ƁB
�@�����V�c�ƔT�؏��R�Ɩ����̍����A���̊Ԃɑ��ʂӁu�������́v�A���̎����Ɖ�z�͍��������ĕ����̖��ɑ傫��������^�ւ�̂ł���B
�i�{���A��糏��X���k���j
�@�@�@�|���̌�������Ȃ肢���ⓢ�Ęh�@�̂��ނĂӋw�̂Ƃ�ł�
�@�@�@����̔��A�͂܂��܂���Y���₪���̍��ӂ݂����݂䂭
�@�@�@��������_����܂�����N�̂݁@���Ƃ����Ђĉ�͂䂭�Ȃ�
�@�T�؊�T�͎R�����o�g�̗��R�叫�B�����R�V�N�i�P�X�O�S�j�W���P�X���A���j�Ɏc����I�푈�E�����v�ǍU�͐�̑��U�����A�T�ؑ�O�R�i�ߊ��̖��߈ꉺ�J�n���ꂽ�B���ڂ͖̉̂�P��̐܂̍�B�u�|���̌��v�Ƃ͌������|�̂₤�Ȍ��B�o���́u�h�v�̓��V�A�c��̖�͂ŁA���V�A�̍����ɂ��f�U�C������Ă��B�������̎R�����Ђ��i�ލc�R�̕��m�����B�|���̌��̈����i�邻�̖�̐�ɂ�����̂́A���V�A�R�̗����Ă�v�ǂł���B�܂����A�|�����͎R�̒[�ɒ��܂��Ƃ��Ă��B�����B���A���𗘂��鎽���̈łƂȂ�B�U���̂��߂̏������͍��₷�ׂĐ��ւ�A�����ⓢ�āB�c���̖��^��q���A�܂��Ɋ����ꝱ�̐퓬���J�n����悤�Ƃ��Ă��A���ْ̋����݂Ȃ���͋����̂ł���B�u����v�́A�u�˂�v�Ɂu����i�������ނ̈Ӂj�v���d�˂Ă��̂��炤�B
�@�����S�O�N��ɂ͑�a�n���⋞��n���ŗ��R�剉�K���s�͂ꂽ�B���ڂ͂��̐܂̍�B�u����v�Ƃ͍��т̔n�A�u���A�͂܂��v�Ƃ͔n�̌����甒���A���ӂ�����قǔn��E�݂������āA�u�ӂ݂����ށv�Ƃ͓��ݕ����i�̈ӁB������䂵�Ȃ���A�l�n��̂ƂȂ��Ċ��̍��ݕ����i�݂䂭�R��̗l�q���A�ْ��������ׂŕ\������Ă��B
�@�O��ڂ̉̂́A�吳���N�i�P�X�P�Q�j�X���P�R���̖�A�����V�c��呒�ɍۂ��A���l�i�V�c�̌�l�j���i�������鍆�C�̍������Ȃ���}�������T�؏��R�̎����ł���B�u�������v�Ƃ͂��̐��A�u�_����܂����v�Ƃ͕��䂳�ꂽ�̈ӁB�u�݂��Ƃ����Ђāv�̈��ɖ����̎v�Ђ����߂��Ă��B���R�̎��o�̗��H�ɂ��������Îq�v�l�̎����́u�o�ł܂��Ă��ւ�܂����̂Ȃ��Ƃ������ӂ̌�K�Ɉ��ӂ����Ȃ����v�ł������B
- �w���̂ł��ǂ���{�̐S�x���� -
�@�@�@�@�@�͂��߂�
�@�Q�O���I�ő�̗��j�w�ҁA�ނ̑咘�w���j�̌����x�ŗL���ȃC�M���X�̃A�[�m���h�E�g�C���r�[���m�́u�ǂ̖������P�Q�E�R�����܂łɎ����̐_�b�Ɋ������G���@��Ȃ���A���Âꂻ�̖����͖ŖS���Ă��B�Ñ�G�W�v�g��\�|�^�~�A���łт��₤�Ɂc�v�Əq�ׂāA��N�̃X�p���ŗ��j���ς��A�x�����Ă�܂����B�Ƃ���ł��Ȃ����A�w�����N�͗c�N���ɁA���{�̐_�b�Ɋ��������̌�������܂����H �w�Z�̋���ł́A���j�ł�����ł����ނɐ_�b�������Ă�Ȃ������ł������狳�͂����o�����Ȃ��͂��ł��B
�@�����Ȃ�g�C���r�[���m�̌��Ӂu���Âꂻ�̖����͖ŖS���Ă��v�̉ӏ��͂ǂ��Ȃ�܂����B����͂ǂ������̖����̂��Ƃł͂Ȃ��A���������{�����̂��ƂƂ��Đ[���Ɏ~�߂˂Ȃ�Ȃ��ł����B
�@�@�@�@�@�P�A���A�搶�ƖЎq�̌�
�@�Ўq���u����P�S�@�s�S�͋剺�v�Łu�����M���ƂȂ��A���T�V�Ɏ����A�N���y���ƂȂ��i���Ƃɂ����Ă͐l�����������M�d�ł�����l�̐_�ɂ���ďے�����鍑�y�͂��̎��ŌN�傪��Ԍy�����̂��j�v�ƌ��ւA������ċg�c���A�搶�́A�w�u�З]�b�x�Ŏ��̂₤�Ɍ��͂�܂��B
| �u���̋`�A�l�N������ނ鏊�Ȃ�B�W���l�N�̓V�E�͓V�������ނ邱�ƂȂ�B���ׂ̈̌N�Ȃ�A���Ȃ���ΌN�ɂ��y���B�̂ɖ����M���Ƃ��A�N���y���Ƃ��B�����̂Ƃ���͓ĂƖ��ӂׂ��v |
�@�Ўq�̌��͂�Ƃ���Ƃ���́A�N�傪���������߂�Ƃ���ɂ���B�v�ӂɌN��̓V�E�͓V����a�����Ă�閯�O�����߂邱�Ƃł���B�������̂��߂̌N�ł��邩����������Ȃ������Ƃ�����A�N����K�v�Ȃ����ƂɂȂ�B����̂Ɂu�����M���Ƃ��A�N���y���Ƃ��v�ƁB���̉ӏ����u�ĂƖ��ӂׂ��v�ƁA���A�搶�͋�̂ł��B
�@���j��[�����͂ւΖ��͂ӂقǁA�V�i�iChina�j�̗��j�̒��ł́A�����m�̒ʂ�A�Ўq�����z�Ƃ���w�̎���͂����m�炸�A�V�i�̗��j�́A�O�̉��������͂œ|�����v���irevolution�j�ɂ���Ď��̉���������܂��B�����������f�����鍑���ł��B�O�̉�����ے肷��̂��v���ł�����f��͗��̕K�R�ł��B�ł�����V�i�̗��j�ł́A���Â�̎�����A�l���͌y���A�N��̌��͈ێ��̕��������d��ꂽ���̂ƂȂ炴��Ȃ������̂ł��B�u�l�����M���Ƃ��A�N����y�����v�Ƃ���A����ȌN��Ȃnj�������Ȃ��B�����珼�A�搶�͑����āu�ٍ��i�V�i�j�̎��͌Ƃ��u���v�ƌ��͂ꂽ�̂ł��B���̎��͏��A�̎v�z�ƍs���̖{�������ɂ߂�ɂ͌��߂����Ȃ��ł��d�v�ȓ_�ł��炤�ƍl�ւ܂��B
�@�@�@�@�@�Q�A�_�b�Ə��A�搶
�@���A�搶�̐S�́A���R�ɓ��{�̗��j�̏�ォ��_��ւƌ��ӂ̂ł��B�ǂ�Ō��܂����B
| �u�Ⴊ���͐J�Ȃ������헧�����A��X�̐_�_���o�āA�ɜQ�����E�ɜQ�f���Ɏ���A�唪�F���y�юR��E���E�l�����ЁA���V���̎�Ȃ�c�c�V�ƍc��_�ʂւ�B�v���ȗ��������A���N�̗��A�V��Ɠ����Ȃ��A������̌�ɓ`�͂邱�ƂȂ�A���y�E�R��E���E�l���A�F�c�c�ȗ��ێ�쎝���ʂӎ҂Ȃ�B�̂ɓV����莋��ΐl�N�������҂͂Ȃ��B�l�N��莋��ΐl���قNjM���҂͂Ȃ��B���̌N���͊J蓈ȗ�����������꓾��҂ɔB�̂ɌN����Ζ�����A�N�Ȃ���Ζ��Ȃ��B��������ΌN����A���Ȃ���ΌN�Ȃ��B�v |
�@���A�搶�́u�ٍ��̎��͌Ƃ��u���B�Ⴊ���͐J�Ȃ������헧�����A��X�̐_�_���o�āA�ɜQ�����E�ɜQ�f���Ɏ���A�c�v�Ɖ䂪���{�̗��j�̂��������̎n�܂�ɐS�����āA�����̓�����������̂ł��B
�@�@�@�@�@�R�A�V�c�ɒ������鏉��O�@- �u�Ⴊ���͐J�Ȃ����c�v-
�@��l�œǂ�ł��Ɠǂݔ���Ă��܂Ђ����ł����A���l���Ɨ֓ǂ��Ă��Ǝ����̐S�ɂ��ĕ��͂ɏW���ł��Ē��҂̐S�ɔ���[���Ƃ���Œ��҂ƐS���q�芴�������L�ł�����̂ł��B�����ŁA���́u�Ⴊ���͐J�Ȃ����v�Ɠ���Ă�����̂��l�ւĂ݂܂����B�����~�܂��Ă�������ƍl�ւĂ݂ė~�����̂ł��B
�@�u�J�Ȃ����v�Ƃ́A�����́u���ɉ߂������b���Ă��v�Ƃ��āA�[�r�̂��肪������\�͂���ł��B�N����u���ɉ߂������b���āv���Ɗ����Ă��̂ł������H ���̌�͂ǂ̕��͂��C�����Ă��̂ł������H ���A�搶�ƑΘb������₤�Ȍ����ȋC�����ɂȂ��čēx�ǂݒ����ė~�����Ǝv�Ђ܂��B
�@�ŏ��̕��͂����u�c�c�V�ƍc��_�ʂւ�v�̏����l�ւ��܂��B�c�c�V�ƍc��_���J���Ă��ɐ��_�{�ɂ́A�������S�����炨��Q�������l�̗₦�Ȃ������܂����A��������ߐ��ɂ����Ăǂ�ǂ�Q�w���L�܂�A���A�搶�̓���������ł����B
�@�������A���~�߂��u�J�Ȃ����v�Ƃ��ӎv�ЁA���������ɂ͂Ƃǂ܂�܂���B
�@���̕��͂�ǂ߂��̎v�Ђ͈�w�[�܂��Ă�邱�Ƃ��f�ւ܂��B
| �u�v���ȗ��������A���N�́@���A�V��Ɠ����Ȃ��A������̌�@�ɓ`�͂邱�ƂȂ�A���y�E�R��@�E���E�l���A�F�c�c�ȗ��ێ��@�����ʂӎ҂Ȃ�v |
�@�Ƃ���܂����A�����Ɏ���܂ŗ��̓V�c�����c�ʂ��p������āu���N�̗��A�V��Ɠ����Ȃ��v�ƈ�C�Ɍ��͂�܂��B���{�̐_�b���Ⴋ���A�搶�̓��S�ɑ��Â��Ă�̂��Ǝv�Ђ܂��B
�@�u���N�v�Ƃ́w���{���I�x�Ɂu�c�c�V�ƍc��_���c�����X�n���ɔ������ȋʁE���@���E���㌕�̎O��̕�����v�Ƃ���܂��B�O��̕Ƃ͍c�ʌp���݈̂�Ƃ��đ�X�̓V�c���p�����_��̂��Ƃł��B���ł́u�����̐�ܕS�H�̐���̚��́A���A�Ⴊ�q���̉�����ׂ��n�Ȃ�B�X�������c���A���Ď��点�v�Ƃ���܂��B
| �i�Ⴂ�w�����N�ɂP�R�O�O�N�����O�̉䂪���ÓT�̒��ׂ̑f���炵���𐺂ɏo���ēǂ݊����ė~�����Ǝv�Ѓ��r��t���Ă�܂��j |
�@���A�搶�͂��炷��ƈÏ����Ă���ꂽ�̂ł͂Ȃ��ł������B���̓V�c�����c�ʂ��p������āA�����ł͍���É��i�����͍F���V�c�j���u�A���Ď��炵�v�Ă�����B�w���{���I�x�́u�s��B���N�̗����܂��ނ��ƁA���ɓV��Ƌ���Ȃ���ׂ��v�Ƃ���܂��i������w������ɂ悭�̂����^���̂��v�Џo������₤�ȋ������������܂��B����̂ɐ��͓��{�̃o�C�u���ƌ��͂��̂ł������j�B
�@�u�V��̗����v�͏��A�搶�ɂƂ��Ē��ۓI�Ȏ��ł͌����Ė��������͂��Ǝv�Ђ܂��B�u���N�̗����܂��ށv�Ƃ��Ӊӏ����Ă��鉽���ɂ���֓�F���g�ɟ��݂Ċ����Ă�����Ɉ�Ђ���܂���B
�@�u�J�Ȃ��v�ƌ��Ӎc���ւ̕��ӂ̔O�͂����ɂ����Ă�āA���̕��͂ւƂقƂ���₤�ɗ���čs���܂��B
�@�@�@�u���̌N���͊J蓈ȗ�����������@�꓾��҂ɔv
�@�������{�������猩��ΓV�c�قǑ����䑶�݂͂Ȃ��B�V�c����䗗�ɂȂ��鎞�͍����͑���ł���B�����ʒu�t�������̈��J�����F���Ă����܂����B���̌N���W�������L���A�����J����Ă��ȗ��������Ƃ��N�������꓾�Ȃ����̂ł���A���̂��Ƃ����{���Ɋ���̌���~���炷�₤�ɗL���u�J�Ȃ��v���Ƃ��A�ƌ����Ă�����Ɠǂݎ�邱�Ƃ��ł��܂��B
�@���ꂱ�������A�搶�̍c���Ɋ��鏉��O�ł���A�i���A�搶�݂̂Ȃ炸����ɂ͑��͂̎u�m�B�̐S��k�͂��āj�����ېV�ithe Meiji Restoration�j�ւƑٓ����鍪���̗͂ł͂Ȃ������ł������B
�@�@�@�@�@�S�A ���A�搶�̐^����
�@�����āu�̂ɌN����Ζ�����A�N�Ȃ���Ζ��Ȃ��B��������ΌN����A���Ȃ���ΌN�Ȃ��v�Ƃ���܂����A����Ƃ����R�Ƃ��Ďx�z���Ă�]�ˎO�S�N�̊Ԃ��u���̌N���͊J蓈ȗ�����������꓾��҂ɔv�Ə��A�搶�͌��͂�܂��B�u���̋`�������č��̏͂�ǂ܂A�ѓ��l�̌��^�����āA�w�V���͈�l�̓V���ɔA�V���̓V���Ȃ�x�ȂǂƔl��A���̂�Y�p����Ɏ���B����ׂ��̐r�����Ȃ�v�Ƌ����x�������̂ł��B
�@�Ō�Ɂu�̂ɌN����Ζ�����A�N�Ȃ���Ζ��Ȃ��v�Ƃ���܂����A���A�搶�͂ǂ̂₤�ȏ�ʂ����Č��͂ꂽ�Ǝv�Ђ܂����B����ɁA�u��������ΌN����A���Ȃ���ΌN�Ȃ��v�Ɛ�����Ă�܂����A����͌�C���͂��Ōy�����͂ꂽ�̂ł͂Ȃ��͂��ł��B�����Ō��͂��u���v�Ƃ͉�������̖������ł������B���A�搶�͎����͓V�c�É��̑��S�̉��ɂ��閯�ł���Ǝ�������Ă�邩�炱���A�u�J�Ȃ����v�i�ܑ̂Ȃ����Ƃ��j�Ƃ̌ꂪ���R�ɏo�Ă����̂��Ǝv�Ђ܂��B�u���̌N���͊J蓈ȗ�����������꓾��҂ɔv�B���̂킪���̗��j�A������l�ւ̊m�M�����A�搶�̐^�����ł��炤�ƍl�ւ܂��B
�@�@���ł����B���́u���v�ɂ��Ȃ����g�������Ă��Ǝv�͂�܂����H�Ɩ�͂ꂽ���A�����u�ہv�Ɠ��ւ�Ƃ�����A�`���Ɉ��p�����g�C���r�[���m�̌��ӂ₤�ɓ��{�������łтĂ��܂ӂƍl�ւ���܂���B�X�J�ł��邱�Ƃ��F��M������������ł��B
�i���������������w�Z�q�p��r���@�j
�@�@�@�N�҂Ƃ킪���Ђ���킪��ǂ̂����ꂤ�������H�̂����ӂ�
�@�ݗt�W�ɂ����߂�ꂽ�z�c���̂��̉̂͐�l�S�N���̂̂��̂ł����A�����̗��S�������ɂ���͂�Ă�܂��B���Ȃ��͂����邾�炤�Ǝv�Ђ��������đ҂��Ă��ƁA�䂪�Ƃ̂����ꂪ�h���B���Ȃ����A�Ǝv�ӂƂ����ł͂Ȃ��ĕ����h�炵�Ă��B�����n�镗�ɁA�����H���ȂƊ�����B�H�Ƃ��ӌ��t�ɂ͈ꖕ�̎₵��������܂��B���̑@�ׂȊ����́A���̂܂ܗ�����l�ւׂ̍₩�Ȏv�Ђ��������������܂��B
�@�@�@���ꂪ�������ȂōK������Ă��Ђ����t���Y�ꂩ�˂�
�@�ޗǎ���ɖh�l�Ƃ��Ă͂邩���������B�ɂ���Ă��������Ȃ���҂̉̂ł����A�������܂������t���Ђ����������f�p�Ȋ������Ăт܂��B�����ɋA�邱�Ƃ��ł��邩�ǂ������킩��Ȃ����̗��A���ꂪ���������Ȃłāu���C�ł�Ă����v�ƌ��������̌��t�͖Y��邱�Ƃ��ł��Ȃ��A�ƌ̋��̗��e����ӂ�̂ł����A����͌���̎������Ƃ����Ƃ��ς邱�Ƃ͂���܂���B
�@���̂₤�ɁA��ꓮ���S���̂܂܂�����A���̏��[�߂Ă������̂����������{�l�̌Ñォ��p���ꂽ�����ł���܂����B���Ƃ��ݗt�W�ɂ́A���̖��������₤�Ɏ��ɑ����̐l�X�̌��̗t�����߂��Ă�܂��B�V�c���珎���܂ŁA�Ȃ��ɂ͌�H�̘a�̂��֍ڂ����Ă��B�j�⏗�̋�ʂȂǂȂ��B�܂芴��������͂����t�̑O�ɂ́A�ǂ�Ȑl�������ł���Ƃ��Ӑl�Ԋς��������B����͋����ׂ����{�̕����ł���A���E�ɂ��H�L�Ȃ��̂ł����B
�@�������Ñ�̌��t������ɑ��Â��͂��\���Ɏ����Ă��B��т�߂��݂ɂ݂����l�X�Ȏp���̂̂Ȃ��Ɍ��A�����Ċ������o���鎞�A�������͂����Ɏ�����l�ł͂Ȃ������̐��E�����邱�Ƃ�m��̂ł����A����͂��̂܂����̐S�̍L����Ƃ��Ȃ��āA�������̐l���������̂ł��B
�@�ÓT���͂��߂Ƃ����f���炵�����w�͎������ɂƂ��Ă܂��ƂȂ���ł��B����͐l�����ʂ��Ă����l�X�̐S�̕\���ł���A������ׂ₩�ɕ\�����Ƃ̂ł���͎̂������̍���ł�������܂���B���ꂾ���������ɂƂ��č���Ƃ��ӂ��̂ɂ́A���ӂɌ��͂�ʍʂ�����A��������B�܂��ĕ����Ō����b�����t�ɂ́A�Ȃ�Ƃ����ւȂ������������������Ă�܂��B���������t���ނ��ł����Ȃ��ɁA�������S���h���Ă����B���������{����w�Ԃ��Ƃɂ���āA�������͔������S�ɖڊo�߂�������Ƃ����Ă������Ǝv�Ђ܂��B
�@���w�҂̉� ���͒����w�t���\�b�x�̒��ŁA�u�l�̐l����䂦��͂ǂ��ɂ���̂��B���͈�ɂ���͐l�Ԃ̎v�����̊���ɂ���Ǝv���v�Əq�ׁA�Ƃ��ɐl�̐S�̔߂��݂��킩�邱�Ƃ��ł���ł���ƌ����Ă�܂��B�����l���̒��Ŏ������͗l�X�Ȕ߂��݂��o�����܂����A����ɑ傫�Ȕ߂��݂��ق��̐l�X�̌��t�Ɍ��o���Ƃ��A�ǂ�قLjԂ߂��͂Â����邱�Ƃ��B
�@�ߔN�A�w�Z�Ȃǂł̂����ߖ�肪�܂��܂��傫�����グ���Ă�܂��B�����ɂ͐l�̔߂��݂ɑ��ē݊��ɂȂ�������l�̎p���_�Ԍ��܂����A����͍����̃e���r�▟��ɂ݂���h���I�ʼn������t�Ɩ����ł͂Ȃ��B���C�Ől���̂̂��邱�Ƃ��Ђɂ��Ă�閳���o���ɜɑR�Ƃ��܂��B
�@�v�Ђ��̊�����ǂ���߂悢�̂��B���̑�Ȏ藧�Ă̈�́A���������Ƃ�������ӂ�錾�t���Ƃ���ǂ����Ƃł���܂����B�䂪���͌×����猾�t�̕�ɖ����Ă��B�������q���̎������炵������g�ɂ��邱�ƂŁA�l�̊�т�߂��݂�������S�͎��R�Ɉ�܂��ɂ����Ђ���܂���B�L���Ȋ�������ނ��Ƃ��l�ƐS��ʂ͂��A�₪�čK���������炷�Ǝv�ӂ̂ł��B
�i�����a�@�@�\�s��a�@���j
�@�@�@�����z���Y���Ғ� ���P�C�T�O�O�~
�@�@�@�w���̂ł��ǂ���{�̐S�x
�@�@�@�������Ł@�@�����Q�X�O�~
�@�u���͂������j�v�������邽�߂ɂ́A���j�̏�����R�����āA���j�̐^���������炩�ɂ���͓̂��R�̂��Ƃł������A����Ɠ����ɑ�Ȃ��Ƃ́A���j�ɓo�ꂷ��l�̐S�ɂӂ�邱�ƁA���̐l�̐S���������̐S�ł�������ƎƂ߁A������u������v���Ƃł͂Ȃ��ł������B
�@�ł͗��j��̐l���ɒ��ڂɂӂ��A�Ƃ͂ǂ����ӂ��Ƃ��A�ǂ�������̂₤�Ȃ��Ƃ��ł���̂��B����́[���ꂱ�����{�ł����ł��Ȃ��A���Ɍb�܂ꂽ���ƂȂ̂ł����[���̐l���r�u�a�́v��ǂ߂����̂ł��B�������̑c��͉��������_��̎��ォ�猻��Ɏ���܂ŁA�������Ƃ��ӈ�т������Y���̒��ɁA��낱�т��߂��݂��A���̂��ׂĂ̊��������Đ����Ă��܂����B
- �u�͂������v���� -
�@���a�Q�U�N�S���A���͏��w�Z�ɓ��w�����B�S�C�̐搶�͕�Ɠ��N�z�̂S�O�ΑO��̏����t�������B
�@���w���Ă��炭�o����������A�ߑO���������ƋL�����邪�A�S�C�̎w���Ŋ��ƈ֎q���S�����ɉ������A���O�̍L�������ɃN���X�̑S���S�V�A�W��������������ꂽ���Ƃ��������B�u������ƍ����Ď��O�ɂ��Ȃ����v�A����Ɂu�z�����ɂ��Ȃ����v�Ɖ��x�����x�����ӂ���A�ӂ�������^���Ȍ��Е��������̂ʼn������Ǝv�Ђ��͂��܂܂ɐ���t�A�������܂����B
�@�Ԃ��Ȃ����āA���̏�̃X�s�[�J�[����A��������Ȃ��J�̉�������Ă����B���Ղ�̂Ƃ����ɂ��邨���q�Ƃ͏�����Ӊ��F�ŁA���̂��Ƃ��T�b�p������Ȃ��������A������ƍ���Ȃ����A�z�����ɂ��Ȃ����Ƃ��Ӂu�搶�̐��v�ƃX�s�[�J�[���畷���Ă����u�s�v�c�ȓJ�̉��v�́A�ǂ����ӂ킯���]���ɏĂ����A���̌���ӂƂ����܂Ɋ��x�ƂȂ��v�ЋN���ꂽ�B
�@���̓�����Q�O���N��̂��ƁA�w�̐l�E����V�c�x�i��v���Y���j�Ƃ��Ӗ{��ǂ�ł�āA���̒��Ɂu�喾�c�@�����̂ԓ��v�Ƒ肳�ꂽ�É��i���a�V�c�j�̂��̂ɖڂ��������B�u���ł܂�����Ԃ̎R�̂ӂ��Ƃ���̂��܂Ђ����̑��͂��v�u�r�ׂ̂̂������������邲�Ƃɕ�̐S�̎v�Ђ��ł��v�Ƃ��ӌ䐻���������A���̉���ɂ́u�喾�c�@�̂��Ȃ��Ȃ�Ȃ�ꂽ�̂��A���a�Q�U�N�T���c�v�]�X�ƋL����Ă�B���̂ɖڂ��������̂́A������������A���̂Ƃ��X�s�[�J�[���痬��Ă����u�J�̉��v�͒喾�c�@�̌�呒�̃��W�I���p�������̂ł͂Ȃ����A�Ǝv��������ł������B�m�F�̂��ߏ������ׂ��݂��B�ʂ��āA�\�z�����ʂ肾�����B���a�Q�U�N�T���P�V������A�U���V���u�喾�c�@�v�̒Ǎ������肳��A��呒�͂U���Q�Q���������̂��B�S���ȂĉI舂Ȃ��Ƃ������B
�@�Q�O�N�]��̊ԁA���w�Z���w�Ԃ��Ȃ����̕s�v�c�ȏo�����Ƃ��ċL�����Ă���Ƃ��A���ۂɂ͂U���Q�Q�����������Ƃ��m�߂�ꂽ�킯�����A���̓��̑̌����喾�c�@�̌䑒�V�Ɋւ���̂������Ɗm�M���Ă���́A�ƂĂ��Ȃ��Ӗ�����o�����Ɏ������Q�����Ă�Ǝv�ӂ₤�ɂȂ����B�傰���Ɍ��ւΎ��̏��̍c���̌��ł������B�u������ƍ���Ȃ����v�Ɖ��x�����x���J��Ԃ����u��̂₤�ȁv�搶�̐��͍������S�Ɏc���Ă�āA���̂Ƃ��c���ɑ��Ắu�p�������炽�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��ӂ��Ƃ�̂Ŋw���킯�ł���B
�@�䑒�V�̗l�q���Z�������ŗ����ꂽ�Ƃ��ӂ��Ƃ́A���̋����ł������₤�Ȍ��i���W�J����Ă���ƂɂȂ�B��呒�̕����������ƋC�����܂ł͉����������s�v�c�Ȏv�Џo���������A�䑒�V�̒��p�����ł������Ɗm�F�ł��Ă���́A���̈Ӗ����l�ւ�₤�ɂȂ����B����͂P�w�N�S�N���X�K�͂̑S�Z������S�l�]��̒������w�Z�i�V�������o���A���E�����s�j�ł̂��Ƃ������B�����āA�S�Z�I�ȒǓ��̎��g�݂͎��̊w�Z�����łȂ��A�����̑��̎s�����́A�ہA�����炭�S���̏��w�Z�ł����l�������̂ł͂Ȃ����Ǝv�ӂ₤�ɂȂ����B��呒�̂Ƃ��ɂ͏��a�V�c�́u�喾�c�@�����̂ԁv�Ƃ��ӂ��͖̂������\����Ă�Ȃ������₤�����A�����̍����͂ǂ̂₤�Ȏv�ЂŌ�呒�̓����}�ւ��̂��炤���ƁA����ɍl�ւ�₤�ɂȂ����̂ł���B
�@���̔]���ɏĂ������u�������Ă������܂����v�L�����琄���ł���̂́A��N��S�����ꂽ�V�c�É��̂��߂��݂����@�����A����Ɍ�v�N�E�吳�V�c�𑁂��S�����ꂽ�c���@�É��i�喾�c�@�j�̌䐶�U��Ǖ炷�鍑���I�ȘA�ъ���Z���������̂ł͂Ȃ����Ƃ��ӂ��Ƃł���B�����łȂ���Ό�呒�̗l�q���S�Z���������͂����Ȃ��B������������Ƃ����A�喾�c�@�͗{�\��~ᚁA����E���ւ̈ԕ��Ȃǂɂ��s�͂��ꂽ���ł������B���ꂱ��U��Ԃ��Ă݂�ƁA�c���@����̔ߕ�����͏��w���Ȃ���u�������܂��āv�~�߂Ă�킯�ŁA���̓��A���͗L�`���`�̑厖�Ȃ��Ƃ����ւ��Ă���ƂɂȂ�B
�@���a�Q�U�N�Ƃ��ւA�|�c�_���錾�������U�N��ŁA�����匠�r���̔��̊��ł������B�O�N�ɂ͒��N�������u�����ă��b�h�E�p�[�W���s�͂��ȂǗ��ɂ��C�f�I���M�[�Η��̉e���y��ł����ł��������A���̈���Ŏ��̂����₩�ȑ̌�����M�͂��₤�ɁA�c��������`���I�ȍ�������ɗh�炬�̂Ȃ����Ƃ������ꂽ�N�ł��������B
�@�����a�Q�V�N�S���A�u�a��������Đ�̂������ꂽ���{�́A���a�V�c�̂��ƁA�{�i�I�Ȍo�ϕ����ւƕ��ݏo�����ƂɂȂ�̂ł���B
�i�ʍ��w���_�x�P�P�A�uꡂ��Ȃ鏺�a�v�����j�|���ƌ���J�i�|
�@�@�@��L
�@�喾�c���@�̌䑒�V�̍ۂɑS���̊w�Z�Ŗق�������ꂽ���Ƃ͎����ł����āA���̂��Ƃɂ��āA�@���W���[�i���X�g�̍֓��g�v���́A�_�����u�R����`�v�u�����Ǝ�`�v�̌���Ǝv�Ѝ��ݏ����u�_���w�߁v�Ő_�������ʓI�Ɉ��������f�g�p������̐_���ς̌��ɋC�Â�������ł͂Ȃ����A�Ƃ��Ă��i�w���_�x�����Q�S�N�S�����j�B
�i��B��w���{�����������q�������j
�@���݁A��ȍ��J�I�ȍٔ��������n�قŎn�܂��Ă��B�����̖@��ŏo���ꂽ��������{�����Ŏ��s����Ƃ��Ӓ����l�̑i�ւ𓌋��n�ق���������ł���B
�@���{�����͓��{�̖@���Ɏ���A����Ɉᔽ���Ȃ����蔱�����邱�Ƃ͂Ȃ��B��������ɂ��Ă��A�ٔ��Ŗ@���ᔽ�̔������m�肵���ꍇ�Ɍ�����B���߂̃P�[�X�ł͗����̋N�i�E���߂Ȃǂ�����₤�����A���̏ꍇ�ł�����ɕs���ł���ٔ����̔��f�������Ƃ��ł���B���Â�ɂ��Ă������͍��@�����炵�Ă�����i�ٔ����ɋ����Ĉ�@�Ɣ��f����Ȃ�����j�A�@�I�ӔC���͂�邱�Ƃ͂Ȃ��B
�@�i�@���̓Ɨ��́A�����I�ɂ͎O�������̌������獑��i���@���j�E���{�i�s�����j�Ƃ̑��������Ӗ�������̂����A�ΊO�I�ɂ͍��Ǝ匠�̈ꕔ�Ƃ��āA���@�i���@�E�@���j�ȊO����]�ӂ��̂Ȃ��̈Ӗ��̂͂��ł���B�����獑���͍����ɂ�č��@�Ɉᔽ���Ȃ�����ٔ����ɂ���Ď���邱�Ƃ͂����Ă��A�Ԉ���Ă��퍐�Ȃɍ��炳��邱�Ƃ͂Ȃ��͂��ł���B�ٔ��͍��@�ɏ������čs�͂�邩��ł���B
�@�]���āA�����ł̔�������{�Ŏ��s����Ƃ��Ӓ����l�̑i�ւ́A���R���{�̍ٔ����Ŗ�O���Ђɂ����ׂ����̂��������A�ǂ��������Ƃ������n�ق��������Ƃ���A�R�����n�܂��Ă��̂ł���B
�@��N�P�O���Q�R���t�Y�o�V���́ufrom Editor�v���A�u�싞��藧�čٔ��̉��v�i���q���ҏW�ψ��j���Q�Ƃ��A��̓I�ɊT�����q�ׂ�ƍ��L�̂₤�ɂȂ�B
�@�����̒����l�͂P�X�R�V�N�i���a�P�Q�N�j�̏����u�싞�����v�̔�Q�҂𖼏�鏗���ŁA�W�]�Ђ������P�O�N�Ɋ��s���������r�v�����w�u�싞�s�E�v�ւ̑�^��x�ɂ���āu���_�I��ɂ����v�Ƃ��āA�������ƓW�]�Ђ�싞�̐l���@�@�ɑi�ւ��B���҂Əo�ŎЂɏ����͂�����������`���͂Ȃ��o�삵�Ȃ������B�싞�@�@�͑����A���҂ɓ��{�~�łT�O�O���~���̔����𖽂��锻�����������B�����Ԃɂ͍ٔ��́u���ݕۏv�̎�茈�߂��Ȃ��A�싞�@�@�̔�������{�Ŏ��s���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����ł��̏����͓����n�قɋ������s�����߂�i�ׂ��N���Ď��ꂽ�B�u�����Ă݂�Γ싞�ʼn��������Q���������A��藧�Ă���悤�ɓ��{�̍ٔ����ɑi���Ă����̂ł���v�i���L�ҁj�B
�@�����A���̍ٔ��Ō����̏��i�ƂȂ����Ƃ�����A�싞�ň���I�ɉ����ꂽ�������A���{�ł��L���Ƃ���Ď��s�����Ƃ��ӑO�㖢���̂��ƂɂȂ�B�i�ւ��������Ǝ��̂��S���������Ȃ��ƂŁA���Ǝ匠�̑��ݑ��d�Ƃ��Ӎ��ۖ@�̊�{�I�����ɂ�����ُ�Ȏ��ԂȂ̂ł���B�ǂ��l�ւĂ��������i�͂��蓾�Ȃ��͂����A�R�����s�͂�Ă�邩��ɂ͗\�f�͋֕��ł���B�����ɗ͂��S���ٌ�m�����݂���i������ٔ����n�܂����̂��j���A���R�ɓW�]�Б��ɂ͍��r���F�ٌ�m�����߂Ƃ���P�X�l�̑i�ב㗝�l�i�ٌ�c�j���T�ւĂ��B���̒��ɖ{�����i�Q�^�j�̒����Ɏ��ٌ�m�����͂��Ă��B
�@����܂œW�]�Ђ͏����u�싞�����v���^�⎋���鏑�Ђ𑽂����s���ė����B���̑i�ׂɂ͓��{�̏o�ŊE��e�@�ւɑ��āA�^�╄���Łu�싞�����v�����グ��Ɩ��Ȃ��ƂɂȂ邼�Ƃ̌��O�̃��b�Z�[�W���߂��Ă��₤�Ɋ�������B�����Ɍ������̑_�Ђ�����₤�ɂ��v�͂��B�]���Ĉ�o�ŎЁA��l�̖��ł͂Ȃ��A�u���_�̎��R�v�ɂ��֘A���鎖���Ȃ̂ł���B
�@�傫���́u��t�v�u���ȏ��v�u�����Q�q�v���X�ō��̑ނ����Β��p�������葱�������ƂŁA���{���Ƃ��y���Ă�邱�Ƃ̌��ꂾ�Ǝv�ӁB�܂��ƂɎc�O�ł���B���ɒn�ْi�K�ł������ɂ��Ă��A�������i�ȂǂƂ��Ӓp�Âׂ��������o�Ȃ��₤�ɍٔ��̍s���𒍎����������̂ł���B
�@���ܕ]�_�ƁE�ߌ���j�����Ƃ̈������ꎁ����Ɂu�싞�ٔ� �W�]�Ђ��x�������v���������āA�ٔ���p���܂ރJ���p�����Ă��B
�@�X�U�����u�O�O�P�V�O�|�P�|�U�V�X�P�S�Q�@�W�]�Ђ��x�������v�B
�@��N�P�P���X���ɊJ�삵���ٔ��́A�P�Q���Q�P���ɑ�Q��̐R�����s�͂�A�R��ڂ͂R���P�T���ߑO�P�P������A�����n�قP�O�R�@��̗\��B
���W�]�� TEL �O�R�i�T�R�P�S�j�X�S�V�O�@�@�@�@�@�i�R�������j
�@�ҏW��L
�@�Q���P�P���́u�����L�O�̓��v�������B��㎞����̂m�g�j�j���[�X�́A��j�s���Ɣ��ΏW���S�������ɕĂ�B����͖{���I�ɂ��Ԉ�Ђ����A�`���I�ɂ��S���ŕ�j�s���̐��E�Q���Ґ����A���Δh�̂���̐��S�{�ɒB���邱�Ƃ͒��ׂ�܂ł��Ȃ����炩���ƁB�u�̒����v���Ĕ��Δh�������グ�邩�������Đ��I�͉��߂�ׂ��ŁA���_�����Ă�邩�̌������ۂ�S���̎����҂̔]���ɍ��ނ��̂ŕS�Q����݂̂��B�����Ό��Ƃ��ӁB
�i�R���j