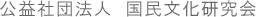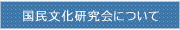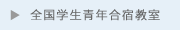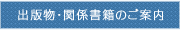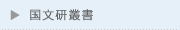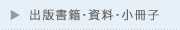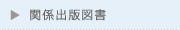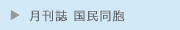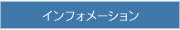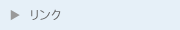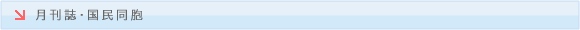
第583号
| 執筆者 | 題名 |
| 第55回全国学生青年合宿教室(阿蘇) 運営委員長 古川広治 |
一人でも多くの学生青年の参加を - 日本を良くしたいと願ふ方なら「年齢は問はない」 - |
| 廣瀬 誠 | 萬葉集と私 - 増刷刊行『万葉集その漲るいのち』(国文研叢書30)〈はしがきに代へて〉から - |
| 小林 国平 | 「今、我ら若手に求められてゐるもの」 - 日頃、心に掛かってゐること - |
| 小柳 志乃夫 | 新刊紹介 (慧文社 3,000円税別) 廣木寧著「江藤淳氏の批評とアメリカ-『アメリカと私』をめぐって」 |
| 新刊紹介 長内俊平著 頒価600円 『文化と文明 -祖國再生の道を念じて-』 |
|
| 新刊紹介 守屋 純著 錦正社刊 税別 1,800円 『国防軍潔白神話の生成』 |
今朝この原稿を書かうと3時に起床して、しばらく心を整へる時間を持った。小雨が落ちてきて蛙の声が聞こえてきた。今年初めて耳にする鳴き声である。なぜか懐かしい気持ちになって、手帳に披き書き写してある天皇陛下の新年のご感想と歌会始の御製とを拝誦させていただいたが、陛下を戴く幸をしみじみと感じた。ここに改めて謹記しておきたい。
「昨年は、引き続く厳しい経済情勢の下で、多くの人々がさまざまな困難に直面し、苦労も多かったことと察しています。
新しく迎えたこの年に、国民皆が互いに助け合い、励まし合って当面の困難を克服するとともに、世界の人々とも相携え、平和を求め、健全な未来を築くために力を尽くすよう願っています。…」
御題「光」
木漏れ日の光を受けて落ち葉敷く小道の真中草青みたり
皇居吹上御苑のお庭を散策された折のお歌とのこと。落ち葉が敷き詰められたやうに小道を覆ってゐる。その上に木漏れ日が射し込み、日の光を受けた小道の真ん中に草が青々と生ひ育ってゐる、といふ情景をお詠みになってゐるが、なんとも言へない温かさが感じられた。微かな光を受けて落ち葉の中から青々と生ひ育つ草の生命に目を止められ、そして射し込む光の方をじっと見上げられたのではなからうか。本当に心が温くなり清められるやうであった。そして新年のご感想を改めて拝読する時、私ども国民に信頼のお気持ちを寄せられる大御心が感じられて心底から「力を尽さう」との思ひがまた湧いてきた。
本会の主催する夏毎の全国学生青年合宿教室は今年の阿蘇で55回目を迎へる。昨年の厚木合宿教室の折、次の合宿教室の運営委員長を引受けるやうにとの話があった。私の中では、合宿運営委員長と言へば学生時代からリーダーとして活躍し、皆を引っ張って行く指導力のある人が担ふものとばかり思ってゐたので大いに戸惑った。しかし、日頃の私を知る先輩が今の私で良いと言はれたのでお引受けすることにした。
合宿教室は毎年10名前後からなる運営委員会が経緯を踏まへつつ企画運営していくが、今年は20歳代30歳代を中心とした例年に比べ若い世代で構成されてゐる。これまで呼びかけに応へてきた者が、今度は呼びかけて行くことになったのである。それは、合宿教室とは何か、自分にとって合宿教室とは何だったのか、何のために学ぶのかを自らに問ふことであった。果てしのない問ひである。その中で、目の前の一人を合宿教室に誘ふためには、自らに問ひ質して生れた言葉を語りかけて行かなければならないと思った。
先日、ある会合で今就職活動中だといふ学生に出会った。面接や希望する業界等の話から「言葉の力」に話が及び、一緒に本を読まないかと呼びかけた。彼はすぐに応へてくれて、隣にゐた友人も、それでは自分も一緒に参加すると言って、一人の学生と職場の同僚とともに加はってくれた。今二週間に一度、社会人を含む七、八名で輪読会を続けてゐる。文章を読んで感じたことを率直に伝へることはいつになっても難しい。心が動いてゐないのに文章から離れた不用意な発言をすると、何が言ひたいのか分らないと直ぐに指摘される。
著者の思ひに心を寄せる、そして聞こえてきた著者の声に耳を澄まして自分の心がどう動いたか、その心の動きを見つめ、それを正しく伝へるべく相応しい言葉を探す。一方で仲間の言葉にも耳を傾ける。かつて合宿教室で体験したかうした輪読の経験は、今の私の業務遂行にも生きてゐるはずである。他では学べない本当に貴重な経験だった。この学びの場に一人でも多くの学生青年に参加して欲しい。政界も教育界も混迷を深めつつあるが、日本をより良い国にしたいと願ふ方ならば年齢は問はない。皆様のご参加を心からお待ちしてゐる。
(福岡中央公共職業安定所)
『萬葉集』は一大山彙である。ふところの深い大山群である。壮大な人麻呂山脈が天を突いて連なり、長大な家持山脈の山脚は遠く海に没してゐる。憶良山脈・虫麻呂山脈・赤人山脈・旅人山脈等々いくつもの山脈が折り重なり、ところどころから火山塊が噴き出し、盛りあがり、錯綜し、その間に谷川がきらめき、大森林が山腹を埋めて黒々と茂り、天上の楽園のやうなお花畑が開け、かと思ふと、巨岩累々たる山稜が烈風に吹かれてゐる。雪渓の割れ目からは落ち激つ水の音が聞え、冷たい霧を吹きあげてくる。そんな感じだ。
この奥深い山路は、いくたび歩いても新鮮だ。その目のさめるやうな風景に、私は驚き、感動し、嘆息し、興奮する。先人の踏み分けた跡は縦横についてゐるが、時には、その踏み跡は細々と樹海に没し、途方に暮れることもしばしばだ。『萬葉集』とはそんな古典だ。
顧みれば、山群の背後には、古事記山脈、書紀山脈、風土記山脈、祝詞山脈が相重なって、碧青に匂ひ、縹渺、天に溶けてゐる。
ゆくてには、平原に没した萬葉大山脈が彼方で再び隆起し、実朝山塊となって聳え、更にかなたには真淵・宗武・良寛・元義・篤好・曙覧らの山々を起こし、そのいや果には、子規の巨峰に始まる根岸山脈が、いくたの近代山群を率ゐて都市地の彼方に連なってゐる。すべて萬葉山脈の山勢のつづきだ。
この深山路の一角を、たどたどしく辿った私の、拙い山岳紀行が本書だ。
◇
私が『萬葉集』を初めて読んだのは富山中学二年の頃であった。勿論、萬葉の神髄などわかるはずもなく、当時、愛誦してゐたのは、
秋風に大和へ越ゆる雁がねはいや遠ざかる雲隠りつつ(10、2128)
さ夜中と夜はふけぬらし雁がねの聞ゆる空に月渡る見ゆ(9、1701)
おちたぎち流るる水の磐に触り淀める淀に月の影見ゆ(9、1714)
山のまの雪は消ざるをたぎちあふ川の柳は萌えにけるかも(10、1849)
のやうな自然詠であった。まだ人生の労苦を知らず、社会を知らず、専ら自然の美しさを讃嘆し、かつ古雅なものを愛好してゐた少年時代の私は、どちらかといへば萬葉よりも、古今調の伝統美の世界に惹かれてゐた。
中学3年の時、たまたま『子規随筆』を読み、その歌論に接し、雷に打たれたやうに愕然として目ざめ『萬葉集』を読み直したのであった。文庫本の『萬葉集』(しかも凝って『白文萬葉集』)をいつもポケットに入れて持ち歩くほど熟読した。当時、中学の校友会誌『文武会報』に「柿本人麿の歌」と題する拙い文を発表したのが、私の文が活字になった最初のものであった。
更に同時代の文学といふことで4年の時から『古事記』『日本書紀』『記紀歌謡集』『風土記』『祝詞・寿詞』(いづれも文庫本)なども読み、神韻縹渺たる『古事記』には魂を奪はれる程感動した。
昭和14年、伊勢・熱田に参拝した時の私の歌がやはり校友会誌に載ったが、「忌火屋の御屋根にゆらぐみけぶりを畏み仰ぐその御けぶりを」「酒殿の瑞しめ縄の白ぬさの揺れもかすかに秋の風吹く」「廣前に神の御鳩の羽ばたきの音すがすがし八剱の宮」といったもので、萬葉調の根岸派からの影響とともに神祇に対する関心の程が顕著だ。萬葉にまねて長歌も2、3試作したが、「山虎の吼ゆるが如く高く叫ばね強く叫ばね」と結んだ稚拙な作があったことを記憶してゐる程度で、ノートはすべて戦災で焼失してしまった。
『書紀』の文が漢文調でごつごつしてゐるのを残念に思ひ、これを(内容的に感銘した神話伝承の一部分を)『古訓古事記』の文体で改作するといふ幼稚なことをやってみたのもその頃であった。とにかく、中学後半が最も記紀萬葉に熱中した時期であった(熱中といっても、学問的研究とは全く無縁で、十分意味も分からないまま、その言葉の調べに惚れこみ、陶酔したのであった)。
一時、萬葉から遠ざかった時期もあったが、また萬葉に戻り、不即不離、50年余にわたって『萬葉集』『古事記』を味はって来たわけだ。
◇
図書館に勤務し、郷土資料を担当し、郷土史会などにかかはり、『萬葉集』の越中関係の部分、いはゆる「越中萬葉」に関心を持ち、これに関する論文・随筆をいくつか書き、『富山県史』にも『富山市史』にも「記紀の伝承と越国」「越中萬葉」などの項目を担当執筆した。市民大学その他各所で私が講演したうち、最も多く扱ったテーマは「立山の歴史・立山の信仰」と「越中萬葉」とであった。その立山と萬葉の接点は家持・池主の立山賦唱和だ。
昭和51年2月、皇太子殿下が冬季国体に来県された時、私は立山の歴史についてお話申上げたが、『萬葉集』に立山が歌はれてゐることに言及すると、「それはどんな歌ですか」と御下問になった。私が朗々と立山賦を暗唱したところ、殿下も妃殿下もニッコリほほゑまれた。なつかしい思ひ出だ。
昭和56年、癌研病院で生死をかけた大手術を受けた時、妻は幾夜も徹夜で看病してくれたが、妻は萬葉の歌「わが背子は物な思ほし事しあらば火にも水にもわれ無けなくに」(4、506)を誦しながら、私を看とった。小学校を卒業するとき、担当の先生から一人に一首づつ萬葉歌を贈られたが、たまたま妻はこの歌を与へられ、それが40年後、口をついて出て来たのであった。
やうやく死地を脱し、療養期間に入ったが、舌の3分の1その他を切り取られた私は、発声思ふにまかせず、毎日病院の屋上で、発声訓練を兼ねて萬葉の長歌を朗誦し、これによって機能を七分通り回復したのであった。私と萬葉の因縁はまことに遠くして深い。
◇
国民文化研究会の小田村理事長から『万葉集』について「国文研叢書」の一冊としてまとめるやうお電話をいただいた時、簡単にお引受けしてしまったが、考へてみると、今まで書いたものはほとんど「越中萬葉」ばかりだ。全国の国民文化研究会の方々に読んでいただくには、「越中萬葉」だけではぐあひが悪い。『万葉集』全般について書かねばならぬと覚悟し、新たに稿を起した。従って2、3を除き、大部分は書きおろしだ。
◇
小田村さんのお話では、萬葉をまだ読んだことのない学生たちの「入門書」が目標といふことなので、最初に概説めいたものを書いたが、その他、多少専門的な書き方の篇もまじり、不揃ひになった。研究調のもの、評論調のもの、随筆調のもの、さまざまだが、雑然たるところに魅力のある『萬葉集』についての書だから、本書も雑然となったと弁解しておく。
「海ゆかば」「大君は神にしませば」「葦原中国と葦原水穂国」など思想史的なテーマ、あるいは記紀伝承に関説した個所は多いが、相聞-恋愛歌についての取り上げ方は甚だ少なかった。遣唐使・遣新羅使関係の歌はぜひ取り上げたいと思ひながら、紙幅が遙かに予定を超え、他の事情もあって断念した。この他にも用意した粗稿のいくつかは紙幅の関係で割愛した。
◇
目下、萬葉ブームとかいはれ、書店の店頭には萬葉関係書は汗牛充棟もただならず、紀要・雑誌等に載る関係論文はおびただしい数だ。私が目を通したのは、その何千分の一、否、何万分の一、何十万分の一にもならぬであらう。是非読まねばならぬと買ひ揃へた書も、読むにいとまなく、空しく書架の一隅に鎮座させたままだ。
そんな不勉強な私が書いたのだから、得々として筆を揮っても、すでに学界では旧説陋説として顧みられなくなってゐて失笑を招くのもあらう。独創的意見と思って書いたことが、すでに先学の発表したものに近く、「今更何をいふのか」或は「口真似、盗作でないか」と批難される場合もあるのではないかと、ちょっと気がかりだ。中には、ずっと以前に読んだ知識を、自分の考へついたことのやうに錯覚してゐる場合もありさうだ。さうなると、先人に対しても失礼で、はづかしく、恐ろしいが、「何とか蛇におぢず」、目をつぶって、五十年間読み味はって来た私の『萬葉集』を一気にここに打ち出した。萬葉の大山脈、その山ふところに足を踏み入れ、先人の足跡を辿ったり、見失ったりしながら、自己流に縦横に歩き廻り、ちび筆をなめなめ書きしたためた紀行文、それが本書である。
不勉強とはいひながら、やはり先学の深い恩恵を蒙ってこそ本書は成ったのである。あらためてその学恩に感謝するものである。- (後略) -
昭和63年8月28日(大伴家持卿・1203年祭の日)
(元富山県立図書館長・故人)
好評 品切につき増刷
廣瀬 誠著(国文研叢書30)『萬葉集 その漲るいのち』価900円 送料290円
私は今年5月で32歳になります。昨年結婚し、娘も生まれて、父親になりました。そんな私に近年、「これからは君達若手の出番だ。君達のやうな若手に大いに頑張って欲しい。思ふやうにやっていい」といふやうな言葉をよく掛けられます。有難い激励の言葉であると受け止めてゐますが、非常に荷の重い頭を悩ませる言葉でもあります。
この度、『国民同胞』への寄稿のお話をいただき、これも私自身を見つめ直すいい機会だと思ってお受けしました。そして何を皆様にお伝へしようかといろいろと考へました。近況報告の意味を込めて日頃の教育実践について書かせていただきながら、さらにいま念頭から離れずいつも心に掛かってゐることについて、この機会に述べさせて貰ひたいと思ひます。それは「今、我ら若手に求められてゐるもの」についてです。
教員生活の原点
現在、私は福岡県内の私立高校に勤務してゐます。着任6年目で、大学進学を目指す生徒達に「日本史」を教へ、学校行事の中心となる生徒会活動の指導も担当してゐます。さらに、とくに私学は少子化の影響もあってどこの学校も生徒数確保に必死ですが、そのための広報活動も私の重要な仕事となってゐます。私自身、要領が悪いことも多々あって、連日のやうに職員室に遅くまで残ってゐます。そのため、たまにしか吾娘を風呂に入れてやることが出来ませんが、まだ何も喋れない吾子の笑みや泣き声から大きな活力を貰ってゐる感じがします。
そんな日常を【忙しい】とは思はずに、【充実してゐる】と思ふやうにしてゐます。【忙しい】といふ字は「心を亡くす」と書きますので、なるべく口にしたくないのです。学級経営の他に、毎週の学級通信〈ちり積も通信〉の発行、七夕・クリスマス・節分などの際のクラス行事の企画、家庭訪問や父母懇談での保護者と話し合ひ等々、生徒のために担任として費やす日々の労力は、生徒の笑顔や成長といふかたちで返ってきて、私の充実感の原点となってゐます。
毎年のことですが、年度当初に「クラス全員の進級」といふ目標を自分の胸の中で立てます。当り前で簡単な目標のやうに思はれるかも知れませんが、これまで1年生を担任した年に、この目標を達成できたことはありません。高校入試の際、志望が叶はず、複雑な思ひで入学してくる生徒もゐて、必ずといっていいほど学校へ足の向かない者が出てきます。原因はその生徒の心の問題であり、また家庭環境が影響してゐることもあります。何度も家まで足を運び、悩みを聞き、時には叱り、時には励まし、登校を促します。そんな時でも全く話さない生徒もゐます。また、時には朝家まで迎へに行き、力尽くでも登校させようとすることもあります。それでも最終的には力及ばないこともあります。
妙なことですが、手の掛からない生徒よりも、心に残る生徒となるものです。学校をやめても私は元担任としてつながりを大切にしたいと思ひ、年賀状を送り続けました。本人からの返事はなかなか来ませんが、2年前の春、退学したある生徒から突然電話があって、「皆とは1年遅れたが、国立大学に合格した」といふのです。元気を取り戻したその声を聞いただけで涙がこぼれました。
ちなみに、昨年は3度目の1年生の担任でした。「今年こそクラス全員の進級を」の強い覚悟で臨み、幾度かのピンチに見舞はれながらも、初めて目標を達成することが出来ました。2年後には、この生徒達を全員卒業させて、溢れるやうに涙を流したいと思ってゐます。
期待をひしと感じつつ…
このやうに、何とか学級経営が出来るやうになってきた私が、「これからは君達若手が…」と声を掛けられるわけです。求められるものは自分のクラスだけではなく、学校全体に向けられてゐるやうです。少子化・「ゆとり」教育・経済不況といった様々な教育を取り巻く困難な環境の中で、生徒も保護者も、社会全体も変容してきました。確かに今、学校は変はる必要があると思ひます。転換期を迎へてゐます。しかし、何10年といふ積み重ねた歴史と伝統を持つ私立高校です。変へることは容易なことではありません。この学校を築き上げてこられた諸先生方を前に、先が長いといふことで私たちの年代は、時代のニーズに合った学校運営のあり方や生徒募集の方策を期待されてゐます。今、何か行動を起すべきであることは分ってゐながら、日々の業務に埋没し、時の流れに身をまかせてゐるのが実情です。それでも我ら若手にはこの苦境を乗り越えるための何かが必要だと日々感じてゐます。
さて、今年の合宿教室は四年ぶりに九州は阿蘇の地で開催されます。古川広治運営委員長の下、今までにない若手中心のメンバーで準備を進めてゐます。その運営委員の1人として、合宿教室では指揮班長を務めさせていただきます。昨年末から何度か運営委員会(総勢11名)を開く中で、頭を悩ませてきたのが合宿内容・スケジュールと学生勧誘です。なぜ今年は運営委員の年齢が例年より若くなったのか。それは、やはり国文研も合宿教室も転換期を迎へてをり、そこで我々に今何をなすべきかを考へる機会を頂いてゐるのだと思ひます。これまで54回積み重ねて培ってきた合宿教室の本質を大切にしながら、新たにどういった要素を取り入れていくかで智恵を絞ってゐるのが、古川先輩を中心とした運営委員会であるやうに思ひます。
中でも諸先輩方が苦労されてきた学生勧誘がやはり一番重い課題です。いかに学生を合宿に連れて来るか。合宿後にどう学生とつながりを持つか。また、勧誘方法とともに、今の学生に焦点を合はせた合宿内容・スケジュールを検討する必要があると思ひます。当然、「世界における日本のあり方を考へる」「我が国の歴史と文化を理解する」「古典や短歌に学び感性を育む」を三本柱として講義が進んでいきます。そこで、心懸けるべきことは、これらの講義内容をいかにして学生参加者たちに心に留め吸収して貰ふかといふことです。そのために何が大事なのか。具体的にどんな方策があるのか。それが合宿後の学生とのつながりに結びつくはずです。そのための合宿内容・スケジュールを考へる余地があるやうに思ひます。今年度の運営委員会はかうした思ひで準備を進めてゐます。
「同胞ともにあり」との信頼感を
しかしながら、本当にこれで大丈夫だらうかといふ不安は拭い去れません。それは今回で第55回を迎へる合宿教室に歴史があり重みがあるからです。今年の阿蘇合宿だけに限らず、今後の国文研・合宿教室を支へていきたいと願ふ1人として、「今、我ら若手に求められてゐるもの」が何なのか考へていかなければなりません。
このやうに、職場でも国文研でも、同じ課題を抱へてゐます。さらに、物事を大きく考へると、日本の国全体においても、やはり我々に何が求められてゐるのかを考へさせられます。近年、とくに憲法・教育・外交・防衛など国家にとっての重要課題で行き詰まりが感じられ、誰もが国の将来を憂ふる時代を迎へてゐます。我々の先人は幾多の苦境を、皇室を戴く連綿とした我が国の歴史と文化を心の拠り所にして乗り越えてこられました。特に、幕末の国難打開に奔走した志士や先の大戦に殉じた学徒の方々が思ひ起されます。今の私よりも若くして公事に尽くした先人の方々です。私も今の日本を真に支へる一人にならなければならないと思ってゐます。
「今、我ら若手に求められてゐるもの」とは何なのか。
今回、このやうに自分を見つめ直す機会を頂き、ふと長内俊平先生の著書『若き友らへ語りかける言葉』(国文研叢書)を手にとりました。その中で、「国民同胞感」といふ言葉に出会ひました。奇しくもその前日、父が私の問ひに答へてくれた中で「同胞感」といふ言葉を耳にしたばかりでした。少し心の中に光が射し込んできた思ひがしました。私の解釈ですが、職場を支へ国文研を支へ、日本を支へていく1人となる自覚を持ちつつ、「同胞ともにあり」といふ信頼感を持って臨むことだと思ひました。日本国民誰しもが同胞であり、ともに国を支へていきたいといふ心の温もりをお互ひに感じ合へる国にする生き方といふことが、私なりの答へであらうかと思ひます。
学校には生徒や同僚がゐます。国文研には阿蘇合宿を共に支へ作り上げていかうとしてゐる仲間、かつての班友の皆さん、そして導いてくださる諸先生・諸先輩がをられます。広く日本の歴史を築いてこられた数多の先人の方々がをられます。ふと、明治天皇の御製「友」が思ひ起されました。
もろともにたすけかはしてむつびあふ友ぞ世にたつ力なるべき
この文を書きながら、私自身に伝へるための学問が不足してゐることを改めて痛感しました。指揮班長として合宿の準備を進める中で自己研鑽を積み重ね、阿蘇の地に向かひたいと思ひます。同輩の諸兄と「今、我ら若手に求められてゐるもの」を共に語り合ひませう。(4月15日記)
(福岡県・ 私立高校教諭)
本書の著者、廣木寧君(昭和56年九州大学卒)は我々の同年代の友人であり、今般、彼の精魂を傾けた筆業が刊行されたことは何よりもうれしいことである。廣木君は学生時代から大変な、そして徹底した読書家であり、彼が語る読書の話は、著書の急所を押さへて実に生き生きとしたもので、そこに僕ら友人は読書の喜び、学問の喜びを教へられてきたものである。
廣木君は、10年前に「正統と異端」といふ同人誌を立ち上げ(同人誌といっても著述の大半は彼自身の手になるものである)、夏目漱石や江藤淳を、或いは聖徳太子を論じてきた。独創的な、しかも正確なテキストの読み込みから生まれた彼の諸論考は著名な文化人からも注目されてきたと聞くが、私自身、最近の保守論壇にない彼の独自の論考に惹かれ、毎号を待ちわびてきた読者の一人 である。
今回の著書はその同人誌に平成十六年四月から平成20年11月まで発表した江藤淳氏を論じた文章をまとめた大著である(今回の出版に当たって削除された部分も少なくないがそれでも470頁に及ぶ)。五年を超える本書執筆の時期は、著者の生活においていろいろと苦労の多かった時期だと思はれるが、その中での精励の成果である。皆さんにも是非お買ひ求めの上、お読みいただきたく思ふ。
本書の概要
この本は3章からなってゐる。第1章「アメリカとは何か」、第2章「アメリカでの江藤淳氏」、第3章「アメリカでの江藤淳氏夫妻」であり、第三章は書き下ろしである。書名の副題にある通り、本書は江藤淳氏の著書『アメリカと私』(現在は講談社文芸文庫でよむことができる)を軸としつつ論考を加へたものである。昭和7年生まれの江藤淳氏は昭和30年、慶応大学在学中に『夏目漱石』でデビュー、『小林秀雄』刊行の翌年である昭和37年、満29歳のときにロックフェラー財団の招きで慶子夫人と共に渡米し米国プリンストン大学に留学、2年目は同校教員として日本の古典文学などを講じ、昭和39年に帰国する。この2年間はキューバ危機やケネディ大統領暗殺といふ大事件が起きた年でもあったのだが、この2年間の経験と思索を綴ったものが『アメリカと私』である。
第1章「アメリカとは何か」
第1章の冒頭は「江藤淳氏はアメリカを避けてきた。わが国がアメリカとの戦争に敗れたからである」といふ印象的な一文で始まり、日本が戦ったアメリカとはどういふ国なのか、なぜ日本はアメリカと戦はねばならなかったのか、そして、戦ひに敗れるとは一体どういふことなのか、かうした問題が次々と展開され、深く堀り下げられていく。
著者は、「戦後も占領が解けた後になって生まれたものには、戦前も戦中も「軍国主義」の時代ということになっていて、ああいう暗黒の時代に生を享けなくてよかった、ああいう時代に生まれていたら命が幾つあっても足りぬという感慨が恐怖感を伴って湧く歴史の授業を何度も何度も受けた。…今思うと、あの歴史の授業で覚えた恐怖感は戦前戦中の国民の恐怖感ではなく、戦後を生きていた教師の、被占領下にたたき込まれた恐怖感であったのだろう」と記してゐる。それでは「恐怖感をたたき込まれた被占領下」とはどういふ時代であったのか。著者は、庄野潤三氏『相客』などの戦後文学の考究や本著執筆時期を通して全巻を読み込んだ『パル判決書』によって、占領軍による「戦争犯罪人」の追及といふアメリカによる復讐劇の真相と当時の日本を覆ってゐた「暗い、不吉な空気」を明らかにする。具体的に紹介する余裕はないが、俘虜虐待の嫌疑で逮捕された庄野潤三氏の兄英二氏や巣鴨の絞首刑第一号となった由利敬陸軍中尉を記す文章のトーンは重い。
所謂「東京裁判史観」の問題は広く認識されつつあるが、著者が冒頭に記した「江藤淳氏はアメリカを避けてきた。わが国がアメリカとの戦争に敗れたからである」といふ戦後の国民精神の様相は私自身見過ごしてきてゐた。この言葉には戦ひの持続感といふもの、戦後を「堪えがたきを堪え、忍び難きを忍んで」生きてきた国民の生の持続感といふべきものがある。著者は深い読書の果てに、江藤氏らとともに、戦後占領下の時代の「空気」を深く呼吸したのだと思ふ。それは戦前と戦後に架け橋をわたす作業でもあったらう。
前述した通り、本章で検討された問題は多い。江藤氏が留学中に耽読したエドマンド・ウィルソン『憂国の血糊』の紹介では、米国南北戦争における北軍における南部民族精神の弾圧が語られるのだが、それは日本占領の光景と二重写しになってゐて驚かされる。また、福田恆存氏の著述の検討では、日本の近代化を論じ、それが従来の日本人の自然な人間性を否定し、日本人に「適応異常」をもたらす酷薄な性質を有してゐたことを示してゐる。今に続く深刻な問題である。
第2章「アメリカでの江藤淳氏」
第2章は「プリンストンにやってきた江藤淳氏は、当初しばらくの間死んでいた」といふ一文に始まる。プリンストンで自分は何をするのか、学生を教へるわけでも学位を目指すわけでもなく、氏は「社会的な死」を体験してゐたといふ。
その「死んでいた」氏が、ミシシッピ大の黒人学生入学拒否といふ米国内を騒がせた事件やキューバ危機といふ国家安全保障の危機を通してアメリカといふ国の本性を発見し、アメリカ社会の中に分け入っていく。日本人としての自己を隠すことなく主張する中で氏は自分を恢復し、アメリカ社会に受け入れられていくのだが、それは反面で氏自身がアメリカ社会に同化されていくことをも意味した。しかし、氏はついにある切実な経験を通して祖国日本との深いきづなを確かなものとする。
ある晩何気なく繙いた世阿弥の『風姿花伝』の言葉が江藤氏の心の奥底に沁み透った。音読してゐるうちに知らぬ間に少し涙をながしてゐた。以下、本書から引用する。
「英語はどれほど熟達しても隔靴掻痒の感を拭い難い。だが、遠い遠い昔の日本人の語る日本語は心の奥底に沁み透るように理解できる。この事は、江藤氏にとって母国語の再発見を意味していた。プリンストン大学で江藤氏が荷風を講じたのも荷風の文章が見事な日本語であったからである。プリンストンでの漱石の『こころ』熟読は、日本で幾度も読んだにも関らず、身体がゆすぶられるようなものであったと江藤氏は述べている。こういう異国での、全身が震えるような、母国語体験は、鴎外も漱石も荷風も語っていない」
江藤氏自身の言葉を聴かう。
「私にとって自分の存在の核心につながる言葉はただ一つしかない。…そう思ったとき、『古事記』『万葉集』から今日にいたる日本文学の持続は、ひきうけなければならないある有機的な全体として私の眼の前に浮びあがって来た。その背後にはなつかしい日本という国があった」(『世阿弥に思う』)
本章は、アメリカにおける江藤氏のいはば「日本への回帰」の体験を浮き彫りにし、国語のいのちの流れを引き受けようといふ氏の志の確立の様子を感動的に描く。
この章には、このほかにも、江藤氏の数々の体験的エピソードが生き生きと紹介される。江藤氏の接したアメリカの隣人たち、初めてのホームパーティ、学会での初の発表、教育者としての教へ子との真率な交流、学生暴動と性の問題、江藤氏の幼時の特異な言語体験、などである。そして、さらにそのエピソードを端緒に著者は論考を進める。人種差別に対する大正時代の我が国の戦ひ、真珠湾奇襲や日米交渉の考察、ケネディの追悼と明治天皇崩御、江藤氏の漱石論における『こころ』の取り扱ひ(最初の漱石論においては『こころ』がなぜか伏せられたといふ)、鴎外や荷風の留学体験と江藤氏のそれとの比較など一つ一つ実に興味深く、学ばされる点が多い。
江藤淳氏に関する優れた評論
本書では山あり谷あり縦横に著者の筆は走っていく。著者の解説で江藤氏の言葉が光彩を放ち、香りをかもし出す。著者の江藤氏に対する深い敬愛、共感、驚きが生んだ優れた評論であり、また、著者の祖国への思ひが随所に示された論考でもある。
本書は江藤淳論であるのみならず、アメリカ論でも、近代化論でも、戦後論でも、さらには国家論でもある総合的な論考である。特に戦後生まれの私たちが学ぶべきものがそこに多く詰め込まれてゐる。是非手にして読んでいただきたい書である。
最後に第3章「アメリカでの江藤淳氏夫妻」についてひと言触れる。私は江藤氏のキーワードの一つに「きづな」といふ言葉があるやうに思ってゐる。第2章において国家と個人のきづなや教師と教へ子のきづなが印象的に記されてゐるのに対し、第3章では夫婦のきづなが謎解きのやうな筆致で、しかも美しくうたひあげられる。江藤氏が夫人の後を追ふやうに自裁して既に10年の歳月が経ったが、その深い愛情がこの章に知られるのである。
(興銀リース)
―右の新刊書の特別頒価―国文研事務局にお申し込みの場合 送料込3,000円
青森県在住の著者が10年ほど前に地元の月刊『東奥春秋』誌に22回に渡って連載した論考を、岸本弘氏(元富山工業高校教諭)が1冊にまとめて刊行したものが本書である。
「はしがき」によれば、昨年春、著者から送られてきたコピーを拝読した岸本氏が「これは自分一人が読ませていただくだけでは勿体ない」とさらにコピーして知友に送付したところ、「反響はまことに大きく、出来れば正式の書籍として出版してはどうかとのご意見が多く寄せられた」ことから、自ら発行者と成るべく具体的な作業を始めたといふ。大仕事のワープロ作業には20歳代から60歳代の24名の協力があったともいふ。何れも国文研の合宿教室で学んだ者たちであった。巻末にワープロ作業に協力した人達の、本論考を拝読しての感想が収められてゐる。これについて「あとがきに代へて」は次のやうに記してゐる。
「十人十色と申し上げればよいのでありませうか、著者・長内俊平先生を温かくつつみ込むそれぞれの思ひが表現されてゐるやうに思はれます。それはまた、著者と手を携へて『文化と文明』に示されるところに歩み出さうとする足音のやうにも聞こえてまゐります」
副題はこの度の刊行に際して付されたものといふ。半生を回顧しつつ学問と教育のあり方に思ひを馳せられる著者の、祖國再生への熱き「祈り」がここからも拝察される。(国文研事務局にお申し込み下されば発行者に取り次ぎます)
「戦争で負けて、戦史叙述で勝った旧ドイツ参謀本部」「第二次世界大戦の惨敗にもかかわらず、ドイツ国防軍と参謀本部の名声はなぜ残ったか?」と本書の帯にあるが、戦後、西ドイツではドイツの敗戦は「素人的直感に頼ったヒトラーの作戦指導への過剰干渉」と「ヒトラーに盲従した取り巻き」の所為であって、国防軍は敗戦にもユダヤ人虐殺にも関係ないとした論述が旧軍幹部達からなされたとふ。
かうした「国防軍による清い作戦とSS(ナチ親衛隊)による汚い戦争」とを峻別した論説が定着し普及した背景に何があったかを本書は緻密詳細に検証してゐる。たしかにヒトラーの暗殺未遂事件が何度もあり反ナチ派の軍人が逮捕されるなどしてゐるが、それは必ずしも「高潔な国防軍」を意味するものではなく、クリーンな国防軍のイメージは、米ソの対立の冷戦下、旧軍幹部達がソ連軍と実際に戦った軍事専門家として自らの経験を米国軍側に売り込むことで保身を図らうとしたことに始まり、一方でそこに対ソ戦の情報を欲した米国軍の意図が絡んでゐた…。ニュルンベルグ国際軍事法廷では「全ドイツ国防軍そのものも組織としては無罪」となって、指揮官としての不法行為は新たに用意された「継続裁判」で訴追された…。
数年前、欧州外遊中の盧武鉉韓国大統領(当時)が「ドイツは戦後処理をきちんとしたが日本はまだだ」云々と語ったとの報道に驚いたが、ことほどさやうにここ20余年来、朝日新聞辺りが繰り返してきた「ドイツに比べて日本は」云々といふ言ひ方を時折耳にする。かつてドイツ紙の日本特派員の中にもドイツのみが矢面に立たないやうにしたかったのか似たことを言ふ者がゐた(ところで、ドイツ研究の専門家から誤りを指摘されたからだらうか、近頃の朝日は「ドイツに比べて日本は」と言はなくなった。しかし彼らが広めた不正確な認識は放置されたままだ)。蛇足ながら一言すれば、日本は1950年代半ばまでに全交戦国と講和条約(国交協定)を締結してゐる。ドイツの場合は1990年のドイツ再統一(東ドイツ併合)による「ドイツに関する最終規定条約」(講和条約の代替)まで待たねばならなかった。「ドイツに比べて…」等と言はれる筋合ひはないのだ。
本書を一読すれば、戦後ドイツの狡知に長けた動きに目を開かされるだけでなく、反面教師として我が国の一面的なあり方に自づから思ひが及ぶ。戦後の日本の歴史認識がいかに単純で底の浅いものであるかが浮び上がってくる。
(山内健生)
編集後記
先頃増刷された廣瀬誠先生著『萬葉集 その漲るいのち』冒頭の一文を掲載させて戴いた。迷走果てなき政権の下、内から外から国威が蔑にされてゐる。かかる折こそ千古万葉の声に耳傾けて、眼力識見を養ひたいものだ。(山内)